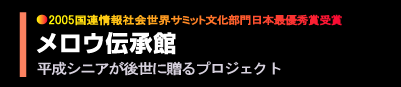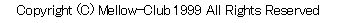メイン メイン 大正の時代 大正の時代
 私の生家「赤壁の家」その1 私の生家「赤壁の家」その1 | 投稿するにはまず登録を |
| スレッド表示 | 古いものから | 前のトピック | 次のトピック | 下へ |
| 投稿者 | スレッド |
|---|---|
| 編集者 | 投稿日時: 2007-1-22 19:50 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
父と島崎藤村・その6 これを披《ひら》いて見た父の困惑は大きかった。四百円といえば、今の金額で約二百五十万円である。いくら赤壁の当主だとはいっても未だ二十三歳の身では、それを右から左にできる力はない。しかし、何とかしなければならない。それで子供の養育費の中から工面してまず百五十円を送り、大正五年までで三百九十円を用立てている。その後も屡々《しばしば》救援の依頼があり、藤村研究家の並木張氏によれば、後のフランス滞在費の援助まで含めると父の支援額は一千八十円に達している。
因に《ちなみに=関連して》藤村からの返金は、生涯を通じて八百六十円だったということである。 実際、「破戒」の執筆に命を賭《か》けて歩み始めた藤村の苦闘と、それを支える父の友情との交錯は劇的ともいえるものだった。四月二十九日、藤村が小諸を去って東京西大久保の寓居《ぐうきょ=仮住まい》に入った翌月に三女縫子が死亡。六月に次女孝子が死去。七月には長女みどりが死亡。冬子夫人も栄養失調で失明した後逝去している。その間、父は西大久保の家を五回も訪ねているが、父の力もここまでは及ばず、如何《いかん》とも為し得ないことに父も藤村と同じ心の痛みを共に苦しんだに違いない。そして一家全滅の中で、幽鬼のようになって只《ただ》ひたすら書き続けた「破戒」の原稿が完成したのは、上京してから七ヵ月を過ぎた十一月二十七日だった。 「草稿全部完了。十一月二十七日夜七時、長き々々労作を終る。章数二十一、稿紙五百三十五。無量の感謝と長き月日の追懐とに胸踊りつつこの葉書を認む《したたむ》」という歓喜のハガキが父に宛《あ》てて届いている。 藤村はこの原稿を持って、岩波書店へ出版の交渉に行った。ところがその原稿を見た社長の岩波茂雄は「いくら自費出版でも、こんな汚い原稿では活字が拾えない」と言って受け取らず、突っ返されてしまった。困って相談された父も憤慨したが、それでは書き直そうということになり、父が特製の原稿用紙を作る事になった。例の得意な篆刻《てんこく》の人脈を生かして大型の版木に枡目《ますめ》を刻み、美濃紙《みのがみ=紙質が強く半紙より大判の上質紙、美濃の国の産物》に朱色で刷った原稿用紙を作らせ、藤村がもう一度こんどは毛筆の楷書で丁寧に書き直した。私は学生時代志賀に帰ってこれを何回も読んだので、「破戒」という小説は活字で読んだことがない。「破戒」というと、あの朱で罫《けい》の引かれた美濃紙の原稿用紙に独特の風格で書かれた美しい楷書の文体が、そのまま小説の内容として頭に浮かんでくるのである。 こうして、藤村の出世作「破戒」は、上田屋から明治三十九《1906》年三月「緑蔭叢書《りょくいんそうしょ》」第一編として自費出版され、絶賛を博した。直ぐに七月、小山内薫《おさないかおる》の脚色演出で伊井蓉峰《いいようほう》一座により、真砂座《まさござ》で上演された。その後、「春」、「家」と次々に名作を発表して文壇に不動の地歩《ちほ=地位》を築いていくのであるが、ここまでに到達するまえ七年間小諸の寓居で「落梅集」、「旧主人」をはじめ、「破戒」もその上で書かれた簡素な松村の机は、小諸を去る時、原稿そのものや愛用の硯《すずり》などと一緒に、お礼のための記念品として父に贈られてきた。私は高等学校の受験で志賀に浪人生活中、一年間その上で勉強して山形高等学校に合格させてもらったので、この机には恩義を感じている。 その後藤村は、昭和十《1935》年に「夜明け前」を完成してから、「日本ペンクラブ会長」に就任、昭和十一《1936》年「朝日文化賞」を受賞、昭和十五《1940》年「帝国芸術院会員」を受諾するなど、急速に社会的繁忙を極めるようになったが、この間も含め、父は四十年の間に二百三十八通の手紙を藤村から受け取っている。 私が物心ついた頃は、先生の作家活動に最も油が乗りきっていた時代で、実業之日本社や春陽堂から「島崎藤村集」が出たり、小諸懐古園に「千曲川旅情の歌」の藤村詩碑ができたりした時分である。この時、昭和二《1027》年七月、詩碑の建立に立ち会った長男楠雄さんと三男蓊助さんが上田の家に寄って、団扇《うちわ》をバタバタさせながら、兄達と談笑していた情景が目に浮かんでくる。二男鶏二さんや柳子さんも来た事があるが、その頃美術学校の学生だった鶏二さんの風格に憧《あこが》れた私は、府立五中を出る頃、美術学校を受けたいと言って、長兄からえらく怒られたことを覚えている。 何れにしても、子供の頃、父や母と一緒に囲む夕餉《ゆうげ》の食卓では、話題に島崎先生の話が出ることが多かったので、私は今でも文豪「島崎藤村」のことを先生と言ってしまう。 以上、父と島崎藤村との関わりについて述べてきたが、前述したように父は非常に懐の広い人だったので、知人の人脈にもまた多士済々なものがあった。父の招きに応じて志賀村の「赤壁の家」を訪れて下さった方は、島崎藤村、高浜虚子の外私の知る限りでも、三宅克己、丸山晩霞、田山花袋、小山内薫、有島生馬、柳田国男、室生犀星などの方々がある。 大正十一年九月には、東久邇宮《ひがしくにのみや》聡子内親王殿下も来臨されている。 すべてもう故人となってしまわれたこれらの方々とともに、父と島崎先生のご冥福《めいふく》をお祈り申し上げたいと思う。  |
| 編集者 | 投稿日時: 2007-1-21 20:05 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
父と島崎藤村・その5 その日、三月四日の父の日記には次のように記されている。
「夜来の降雪、午後二時頃まで降る。後、西の烈風。夕方五時半頃に、今日はこの雪ゆえ来はすまいと思った島崎氏が雪を冒してやってきた。丁度余《よ=われ》は入浴中だったので直ぐ出て、それから夕食後、何という事なしに話して一時過ぎ迄。話題は今後の新作『破戒』の大略に就いて色々、挿絵に就いて、装釘に就いて等色々。」 猛吹雪の中を難行の末にやっと辿り着いた藤村を、父がどんなに感激して温かく迎えたかは想像に難くない。母や家中の歓待も受けてその日は夜中の一時まで、翌日もまた朝から四方山《よもやま=さまざま》の話に花を咲かせて午後まで。そして三時帰路につくのであるが、その間、わざわざそのために雪を冒して訪ねてきたはずの肝腎《かんじん》な金四百円借用の件は、ついに話し出すことが出来なかった。そしてその夜、長い手紙を書いて出している。長文なので、梢《やや》抄記《しょうき=抜書き》する。 「あたたかき湯に身の疲れを忘れ、終宵の物語り、時のうつるを覚えざりしは昨日のことに候ひき《そうらいき》。昨日の今は兄と令閨《れいけい=夫人》と互におかしくおもしろき談話に興ぜしことを思い出でて、身はなお羨《うらやま》しき兄《けい=先輩、同輩に対する敬称》の家庭のうちにある心地いたし候。 この行、風雪を衝《つ》きて静かなる御住居を驚かせしは、兄を見てたのしき日を送らんとの願いの外に、別に生《せい=男子の謙称、小生》の前途に展《ひら》けつつある新事業につきて兄の同情と助力とを得度《た》きの念に満ちたるにて候ひき。されど、静慮《せいりょ=心を静めて考える事》すれば兄に対して交《まじわり》未だ浅き身なり。たとえ文芸の事業に深き感興と同情とを寄せらるる兄とは頼みながら、こは《=これは》あまりに無遠慮なるわざなりと考へ、遂に生は語る能《あた》わず《=語ることが出来なかった》して兄の家を辞したるにて候。 甚《はなは》だ勝手なる申し出ながら、兄にしてもし生を信ぜられ、生の事業を助けむ《ん》との厚き御志もあらせられ候はば、向後《きょうご=今後》三年のあかつきに御返済するの義務を約して、補助費として四百円を御恩借《人の情けによって借り受ける》いたしたきこと。・・・西の国《=西欧》の詩人の上をも見るに、その人を得たるためにゲエテは生き、その人を得ざりしためにシェレイは死せり。 かかる御依頼は甚だ申し上げにくき次第なれど、今は死生を新しき事業に托《たく》するの身、兄の如き人を力として進むより外なき境遇、万々《ばんばん=充分》御賢察御推読を仰ぎ申し候。」 |
| 編集者 | 投稿日時: 2007-1-20 19:13 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
父と島崎藤村・その4 その後明治四十一《1908》年まで毎年一回、一泊または二泊しているが、四十年に亘《わた》る父と藤村との交友の中で最も重要な二日間となったのが、二回目の明治三十八《1905》年三月のことである。
この頃、藤村はそれまでの詩人としての活動から小説家に転向することを決意し、「千曲川のスケッチ」に続いて最初の長編小説「破戒」の出版に取りかかっていた。その挿絵《さしえ》にする写真を父に依頼し、五百頁ぐらい書くつもりだという原稿の最初の二百頁を見せられている。その出版費の四百円は奥さんの実家函館《はこだて》の秦慶治さんに出してもらうことになっていたが、出版するまでの生活費については目処《めど》がついていなかった。 いろいろ思い悩んだ末、半年前に立派な赤壁の家を訪ね、お互いに心を許す友ともなっていた父に頼む以外はない、と決意したのがこの日のことだった。ところが、この日はひどい寒波の襲来で朝から吹雪になっていた。岩村田から志賀まで一里半の道中には、「切り通し」という窪地《くぼち》があって、どうしてもそこを通らなければならない。吹雪の時は十年に一度死人がでるというぐらいの難所である。この日のことを藤村は小説「突貫」に、次のように書いている。 「私は、猛さんに話してみることに決心した。単独で雪を衝《つ》いて倒れるところまでいってみる。岩村田で馬車を下りる頃は、私の身体は最早水を浴びせ掛けられるように成っていた。恐ろしい寒気だった。時々眠くなるような眩暈《めまい》がして来て、何処《どこ》かそこへ倒れかかりそうに成った。私は未だ曾《かつ》て経験したことのない戦慄《せんりつ》を覚えた。終《つ》いに息苦しく成って来た。まるで私の周囲は氷の世界のようだった。もうすこしで私は死ぬかと思った。私の足許には氾濫《はんらん》の跡の雪に掩《おお》われたところがあった。私はその中へ滑り込まないように気をつけながら、前へ、前へと辿《たど》って行った。前へ…、前へ…」 |
| 編集者 | 投稿日時: 2007-1-19 17:18 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
父と島崎藤村・その3 さて、父が志賀で考古学の土器発掘を始めたのは二十一歳の時だったが、その翌年、小諸町の名門校小諸義塾の木村熊二先生が赤壁の家に来訪された。そしてその時のお誘いで明治三十七年三月父は小諸義塾を訪ね、塾長から教員の島崎藤村を紹介された。その日は小諸義塾の卒業式だったが、式後父は藤村に誘われて近郷の素封家を訪ねて懇談の時を過ごした。
この頃、小諸義塾は経営が極めて困難な上、日露戦争《日本とロシアの戦争、1904~5年》が始まって小諸町からの補助金が三百円削減されることになってしまった。藤村は二十五円の薄給だったうえ母校明治学院から六十円出すので来てくれと言われていたので、いよいよ辞任を決意して上京しようとしていた。ところが藤村の実力と生徒間の人気を評価する同僚の職員一同は自分たちの月給二割削減を申し合わせて、島崎先生の留任運動を起こした。 父は、この美談に感動するとともに、小諸町のやり方に憤慨した。そして職員の割く月額の一部の助けにもと、五十円寄付することを木村塾長に申し出た。この話を聞いて、多感な詩人藤村が感激したことは想像に難くない。こうして藤村は小諸義塾に一応留まることになり、このときから父と藤村とは、生涯を通した深い友情で結ばれてゆくことになったのである。 島崎藤村が初めて志賀に赤壁の家を訪ねて来たのは、明治三十七《1904》年十月十五日だった。父の招きで木村熊二、丸山晩霞、立川雲平の三氏とともに二泊し、裏山で松茸《まつたけ》狩りをしている。 家の裏にある正住寺山は、樹齢百年を超す松が何百本と生え茂っている松の山だったから、秋になると昔から良質の松茸がいくらでも採れた。山の中腹には番小屋があって、番人が目を光らせているが、石の寵《かまど?》を築いてあって、お客様が来ると採りたての松茸を焼いてご馳走《ちそう》する。大勢の人たちが集まると、それが松茸狩りになるのである。  |
| 編集者 | 投稿日時: 2007-1-18 19:17 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
父と島崎藤村・その2 考古学と禅《=禅宗》は、父の人生では既に趣味と言えない域に達していたが、もう一つやはり病膏盲《やまいこうこう=どうしようもないほど物事に熱中すること》に近い状態だったのが俳句の世界であった。父の自伝を見ると、「自分が俳句を始めたのは慶応義塾の頃からで、俳号を雨村と定め、友人と句の遣り取りなどをして居った」とある。明治四十五《1912》年三月渡辺水巴《すいは》氏の門を叩き、翌年鎌倉に転地した折、水巴氏の紹介で高浜虚子氏を由比ヶ浜に訪ね、大正二《1913》年十月には水巴、虚子両氏を信州に招き、それから親交を重ねていくことになる。
虚子氏は戦時中小諸に疎開したので、父を訪ねてその後も志賀に来てくださったが、昭和二十一《1946》年に父が亡くなった時は、近在のお弟子さんと一緒にご弔問下さり、父を偲《しの》んで「枕頭《ちんとう》句会」を催してくださった。私も参会した。 父の句作は生涯で二千余句となっているが、それを整理し母の句二百も加えて仮綴じ《かりとじ》にしたものを「双鶴集」と名付けて、虚子先生の序文も貰《もら》い、句集を発行することを父は長い間念願にしていた。然し戦中、戦後父の生存中は誰も皆その日その日を生き抜くのに精一杯で、とても句集の発行どころではなかった。それで昭和四十二《1967》年六月、父の二十三回忌を営むに当たり、父の俳句百五十句と母五十五句に日記と遺稿を加えて「後凋」と改名した追悼録《ついとうろく》を子供達一同で出版した。父にも多分満足してもらうことが出来ただろうと思っている。 俳句についで、趣味として父が打ち込んでいたのは篆刻《てんこく=木や石、金属などに印を掘る》と鎌倉彫《かまくらぼり=素地に彫刻を施して漆塗りで仕上げる漆器》だった。篆刻の方は明治四十三《1910》年、二十九歳の頃から始めたというから長い年季の入った趣味であるが、私の記憶にある限りでも晩年に至るまで、先の鋭く尖《とが》った細い木彫刀を駆使して刻んだ大小様々な印形はかなりの数に上っている。印材を押さえる特殊な形をした木型に挟んで細かく彫っていく父の真剣な眼差しを、心配しながら覗《のぞ》き込んでいた覚えがある。 然し、初めのうちは趣味で始まった篆刻も次第に自己流では収まらなくなったのであろう、大正十《1921》年からは専門家の関野香雲師の門を叩《たた》き指導を仰ぐことになった。そして本格的に刻まれるようになった印形、印鑑は次第に評価されて広く使われるようになり、宗演老師や大眉老師が晩年に書かれた揮毫《きごう=書画を書くこと》や大きな掛け軸、屏風《びょうぶ》、扁額《へんがく=細長い額》などの落款《らっかん=署名や印》を見ると、その大部分が父の作品である。 関野香雲師への師事は、篆刻だけに止まっていなかった。木彫《もくちょう》や鎌倉彫などにも広がり、観音《=観世音菩薩像》、笏《しゃく=貴族が正装の時、右手に持つ木製の板切れ》、掛け軸、横額、小棚、机など、私の知っているだけでも沢山の作品があるが、いずれも素人の作とは見えない職人並みの仕事である。台面の四周と脚の部分に複雑な唐草模様を浮彫にした格調高い机は、いまも軽井沢の別荘で客間に納まり異彩を放っている。 さらにもう一つ、謡曲があった。上田に在住の頃熱中していて、銀行から帰ると座敷の床の間の前へ見台《けんだい=書見台》を引っ張り出し、その上に和綴じ《わとじ=日本風の本の綴じ方》の本を関《ひら》いて載せ、朗々たる声で謡い出した。よく徹《とお》るなかなかよい声で、母も一緒に声を合わせることがあった。 そのほか、子供達を連れて昆虫採集に行ったり、絵はがきやマッチのレッテル蒐集《しゅうしゅう》などにも手を出しているし、兎《と》にも角にも趣味の広い人で、まさにディレッタントというに相応《ふさわ》しいが、私もよく友達からの悪口にそう言われるのを聞くたびに、それは親譲りの性格だから仕方ない、と十分自分で納得できるだけの自信を持っている。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2007-1-17 19:07 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
父と島崎藤村・その1 私の出征に当たり、激しい言葉を浴びせた父猛は、父自身がまた波瀾万丈《はらんばんじょう=波の起伏のように変化が激しいさま》とも言える生涯を送った人だった。今その人生を彩る多才な足跡を辿《たど》ってみると、不肖の息子《ふしょうのむすこ=父に似ない愚かな息子》としてはなにか賛嘆に似た思いを禁ずることが出来ない。
明治二十五年、曾祖父《そうそふ》包重の遺言により十一歳で第十二代目の家督を相続した父は、祖父禎次郎の計らいで、勉学のため直ちに慶応義塾《現慶応大学》幼稚舎に入学させられた。当時の教育界では福沢諭吉の声望が高く、特に私学を選ぶ素封家《そほうか=財産家》達の子弟は多くが慶応義塾に送り込まれた。神津各家の若い当主達も藤平、邦太郎などが既に東京・三田で学ぶ先輩となっていた。 慶応義塾普通科を卒業した明治三十二《1899》年、母てうと結婚、明治四十《1907》年から志賀銀行に勤務、大正六《1917》年頭取となり、佐久地方に段々範囲を広げて大正十二《1923》年、中信銀行頭取となったがさらに全県的な拡張を図り、昭和三《1928》年本店を上田に移して信濃銀行を設立した。 その間、慶応義塾で福沢諭吉先生に品川の古墳跡地に連れて行かれ、じかに土器の発掘を手伝わされた体験を活かして、志賀に帰るとその近辺の古墳に目をつけ、多忙な公務の合間に土器の発掘を始めている。それはまた直接土着の強い郷土愛にもつながっていったのだろうと思うが、村の仕事でもいろいろな役職を引き受けている。二十七歳で志賀村農会長となり、二十八歳から二宮尊徳《にのみやそんとく=江戸末期の篤農家、605ヶ町村を復興した人》の報徳思想を広めて報徳会の事業推進を始め、二十九歳で村会議員、三十歳で東信明徳会の会長を引き受け、三十六歳で志賀村の村長となっている。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2007-1-16 20:22 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
私の生家「赤壁の家」その7 昭和十九《1944》年十二月、私は海軍軍医学校を卒業していよいよ任地に赴任するというとき、最後の挨拶《あいさつ》に志賀の家に帰してもらうことが出来た。その時、父はこの権現さまの前に私を連れて行った。そして「一番」から持ってきた日本刀を私の手に渡すと、じっと私を見つめて、ひと言、「これで、五人分死んでこい」といった。
私の兄弟は十人であるが、男は七人だった。 そのうち上の二人は夭折《ようせつ=若死に》して成人したのは五人だったが、三人の兄達は皆肺結核で、徴兵検査《ちょうへいけんさ=兵役義務に服するための身体検査》は全部丙種《へいしゅ=徴兵検査の結果 甲種、第一乙種、第2乙種、丙種に分けられた》。弟は小児麻疹《ましん》で人並みの男ではない。赤壁の家からは誰も兵隊になったものがいなかったのである。敗戦を前に国中が戦況に一喜一憂し、一人前の男は皆兵隊に取られて命を国に捧げる美談が喧《やかま》しく讃《たた》えられていた時に、「赤壁さんでは、だれも……」と後ろ指を差されているような気持ちで、父はどんなにか肩身の狭い思いをしていたのだろうと思う。 それが、この「五人分死んでこい」という激しい言葉になったのだと思うが、この日本刀は、出征用の軍刀に仕込むとき、刀屋から「旦那、これは勿体《もったい》ないですね」と言われたように、「関の兼永」の名刀だった。家宝の一つにも数えられるような大事な刀と一緒に私を戦場に送り出し、死んでこいというのだから、国を守る使命を神津家の誇りにかけて私に托《たく》そうとした父の気迫には、胸をえぐるような深い感動を禁ずることが出来なかった。 しかしこれは、結局一人もブッタ切るのには使うことなく、敗戦後苦労して持ち帰ったが、占領軍の刀剣類供出命令であっさりアメリカに持って行かれてしまった。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2007-1-14 22:09 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
私の生家「赤壁の家」その6 神津家にはもう百年以上も前から毎年八月一日、親族一同が集まる「お墓参り」という年中行事が続いている。その模様は、父が明治初年には未だ珍しかった写真機をイギリスから購入して、恒例の集合写真を連綿と写してきたので、その時々の着衣や持ち物の様子が明治、大正、昭和、平成各年代の歴史的風俗を伝える貴重な記録写真となって残っている。
毎年、村を離れた遠い各地からも百人近い親類が集まるこの日は、本家の座敷を御殿まで開放してゆっくり一族の懇親を深めたあと、夫々のお墓にご焼香をして、菩提寺の法禅寺に集まり会食をするのであるが、この法禅寺はただお経を上げてもらうだけのお寺ではない。神津家とは一体となっている菩提寺である。 法禅寺は宗家が開基となったお寺なので、その住職の代が替わるときの晋山式《しんざんしき》は赤壁の家で営まれてきた。晋山式には私も参列したことがあるが、盛装した沢山の僧俗達が集まって荘厳な読経を捧げる盛大な勤行を行った後、長い行列が玄関から表門を出て法禅寺に繰り込んだ。神津家からの住職のお輿《こし》入れである。 だから、お墓とお寺は一体となって神津家の裏に位置するわけであるが、その墓地と法禅寺の間に一本の細い道がある。それを北側へ正住寺山の麓《ふもと》の方に少し登ると、権現様という祠《ほこら》がある。こじんまりした石垣櫓《やぐら》の上に組まれた社殿は古いものではなく、たぶん明治中期の神仏混交《しんぶつこんこう=神道と仏教が融合調和すること》、廃仏毀釈《はいぶつきしゃく=仏教排斥運動、仏像の破壊や僧侶への迫害など》の波に圧されて造られたものだと思うが、今も神津家の氏神様になっている。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2007-1-13 21:04 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
私の生家「赤壁の家」その5 志賀村には、長い歴史の中で「神津一族系譜」とは別の神津の各家がある。もちろん同じ親戚で墓地も一緒であるが、その著名な先覚の一人が神津邦太郎である。志賀村から一つ峠を越えた向こう側の群馬県に牧場を開発して神津牧場と名付けた。明治初年、イギリスに渡り日本には初めての乳牛、ジャージーを輸入し、牧犬としてスコッチコリーも連れてきた。日本の牧畜産業産みの親の一人とも言うことが出来る。
また芸術の分野では、日本の洋画界の草分けとして大正初期から昭和後期にかけて活躍した神津港人がいる。大正九年渡英し、ロイヤルアカデミーで学び、帰国後は構造社に加わり絵画部を創設したが、のち帝展の改組に際し構造社を脱退して緑港会を創設、第一美術協会と合併するなどして注目された。 確かな写実と温暖な色調を基にした画風で、風景、人物、静物など幅広い領域に多くの傑作を残している。 しかしいま挙げてきた人物像のうち、現役の善行、メイコ夫妻と羽田孜元首相の他はもう皆故人となってしまった。四百年に亘《わた》る長い歴史の中で志賀の神津家に生まれ黄泉《よみ》の国に旅立って行かれた方が何人になるか、いま手元に正確な資料はないが、その方々が永久《とわ》の眠りに就いているお墓はいま家の裏山「正住寺山」の麓《ふもと》に数多くの奥つ城《おくつき=墓所》となって鎮まっている。 屋敷の北側の隅にある裏目の門を開けると、眼の前に広がる畑の向こうがすぐもう草地の入り目である。かつて父の招きで訪ねてきた白樺派の作家で画家の有島生馬氏が、この墓地について次のように書いている。 「神津家の菩提寺《ぼだいじ》を法禅寺と称し、その墓地は神津家の裏に連なってゐ《い》る。古くは延文、天文、大正時代のものから、現代に至るまで累々《るいるい》二百基という苔《こけ》むした墓石が整然屏立《へいりつ》してゐ《い》る。一家一族の墓所でかく完全に保存されてゐ《い》るのを見たことのない私は、人生の悠久と時勢の推移を思ひ《い》、深い感慨に打たれた。之《これ》も交通不便な僻邑《へきゆう=片田舎》に隠されてゐ《い》た賜物というべきである」 広い墓地の北側正衝には、石垣が一段と高く積まれてご先祖様方の墓石が一列に並んでおり、その真中に一際高い遠祖八代のお墓がある。年代順に奥から手前に並んでいる墓石には夫々《それぞれ》時を物語る特徴があるが、どれも丁寧に刻まれた同じ高さの墓石が粛然と佇《たたず》んでいる墓地には静謐《せいひつ=静か》な空気が漂っていて、何か心温まるものがある。お墓参りのときは、夫々の家族の思いを込めてその一つ一つにお線香が手向けられる。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2007-1-11 22:02 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
私の生家「赤壁の家」その4 四百年続いてきた神津家の家系は、父が晩年に長い年月を費やして調査、作製し、それを長兄得一郎が補遺《ほい=漏らした事項をおぎなう》、整理した「神津家一族系譜」という資料に明らかである。本家十三代、分家三十三軒の詳細な分岐系統図が整然と記されている。
神津一族の中には近世日本の社会に貢献した人が何人かいる。まず曾祖父《そうそふ》の包重であるが、幕末政情不安の最中、小作争議の頻発、莫《ばく》大な御用金や献金などに悩み、新時代の到来を望んでいた時、赤報隊事件に連座。慶応四《1868》年官軍に肩入れをして頭部に三ヵ所の傷を負うような活躍をした。 祖父の禎次郎は、硬骨の父包蔵への反発からか文筆を好む人となり、法律家を目指していた。十六歳で司法省の法学校に入学し、明治十六《1883》年、長野の郡書記から京都の裁判所書記となり、厳しい研讃《けんさん=学問を究める》の末、法律解説書を上梓《じょうし=出版》している。 明治二十五《1892》年、禎次郎は父包重の重体を知って志賀に帰ったが、包重は間もなく逝去し、その遺言により十一歳の猛が神津家十二代目を相続することになった。 神津一族には、明治から大正、昭和初期にかけ、長野県内でさまざまな事業を興した人がいる。信濃銀行を起した父のことはあとで書くことにして、まず日本のスキーのメッカ、志賀高原スキー場を開発し、長野電鉄を敷設した神津藤平。志賀高原という名前を神津一族の本拠である志賀村の名前からとった人である。その業績は志賀村の入り口に銅像となって称えられている。 藤平の弟神津傲佑は、東北帝国大学で初代の地質学教授となり、当時最も注目されていた水晶の結晶構造を解明して世界の学者を驚嘆させ、日本で第七番目の日本学士院会員に選ばれている。 神津一族のうち、現役で最も活躍しているのは神津善行、中村メイ子夫妻である。善行氏は既に三百にも上る映画音楽を手がけ、作曲に演奏に八面六臂《はちめんろっぴ=一人で数人分の活躍をすること》の活動を展開しているので特に記述するまでもないが、本名は充吉、夫人は五月のご夫婦である。 現役といえば、親族でもう一人、神津藤平の娘淑子の婿羽田武嗣郎の長男、羽田孜元首相がいる。昭和四十四年以来衆議院議員に当選九回。農林水産大臣、大蔵大臣、外務人臣を歴任して平成六年内閣総理大臣になった。いま、波瀾《はらん》に富む政界の中で重鎮として活躍している。 |
| (1) 2 » | |
| スレッド表示 | 古いものから | 前のトピック | 次のトピック | トップ |
| 投稿するにはまず登録を | |