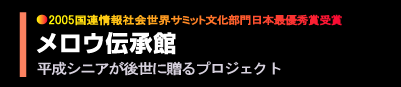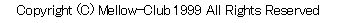メイン メイン 実録・個人の昭和史I(戦前・戦中・戦後直後) 実録・個人の昭和史I(戦前・戦中・戦後直後)
 戦中戦後、少年の記憶 北朝鮮の難民だった頃 (林ひろたけ) 戦中戦後、少年の記憶 北朝鮮の難民だった頃 (林ひろたけ) | 投稿するにはまず登録を |
| スレッド表示 | 新しいものから | 前のトピック | 次のトピック | 下へ |
| 投稿者 | スレッド |
|---|---|
| 編集者 | 投稿日時: 2008-8-5 9:12 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
戦中戦後、少年の記憶 北朝鮮の難民だった頃・31 (林ひろたけ) 満州からお兄ちゃんが一人で逃げてきた・1
その頃、子ども達は退屈だった。お腹がすいてもすることはなかった。「寒いよ。お腹がへった。なにか食べたい」。というのが子ども達から悲鳴だった。それでも外で遊ぶ以外なかった。いつのまにか、男の子たちは、クラブの子ども達と社宅に収容されている子供たちとがわかれて戦争ごっこを繰り返していた。戦争ごっこから本気の喧嘩が始まっていた。あまり理由もないのにいきなり殴り合いになったりした。クラブの子ども達は五年生の寺山君が大将だった。洋武と順ちゃんが副大将格だった。クラブと社宅の間にすこし広場があった。そこがクラブの子ども対社宅の子どもたちの決戦の場所だった。毎日、毎日そこで棒切れを持って「わーっつ」と叫んでは子供同士の本気のちゃんばらがおこなわれた。アカシヤの棒は格好の刀になった。子ども達のいらだちは激しかったのか、怪我をする子も続出して体じゅうおできだらけになった。 こうした事態を心配した大人達は喧嘩を止めるように子ども達の大将を呼んで厳しく注意をした。そのなかで国民学校の再開もうわさされた。しかし、噂はあったが再開は出来なかった。大人たちは自分達の一家をたべさせる心配をするのが精一杯だった。 喧嘩はなくなったが、子ども達は結局は放置されていた。子ども達は、今度、あちこち大人を捕まえてはお話をせがんで歩いた。栗本鐵工所の所長さんの花田さんは、みんなが使役に出ているときも使役を免除されて家にいた。一つの住宅に三家族も四家族も積めこまれて(詰めこまれて)いるときも六畳の間に一人で机に向かっていた。傷痍軍人のせいか、それともお年のせいかも知れなかったが、花村さんが栗本鐵工所で一番えらい人でそうしていたらしかった。不公平な感じもした。でも私たちがいくと「それでは武田信玄と上杉謙信の話をしてあげよう」といって、「川中島の決戦」の話をした。そして上杉謙信が武田信玄に塩を送った話などして、さらに 「ベンセイシュクシュク」という詩吟も教えてくれた。「武田信玄の死んだ話しを聞いたとき、上杉謙信はばたりと箸を落として惜しい人が死んだといって嘆いたそうです」 と話しを結んだ。 砂金会社の営業所長さんで日本人会の会長さんでもある大村さんは体が大きくて柔道の選手だった。大村さんは使役にもどんどん出ていた。しかし、日本人会長だった大村さんは比較的他の人より家にいることが多かった。大村さんの家族は奥さんと子供が二人だった。上のお姉さんの恵美子ちゃんは私たちより二つ下の二年生だった。その一つ下の男の子は学齢がきていたが「ワァーワァー」言うだけの知恵遅れの障害児だった。敦志君で「あっちゃん」と呼んでいた。大村さんは厨司王(厨子王)と安寿姫の話をしてくれた。そして私たちに「君たちしっかりしているね。あっちゃんとも遊んでね」とつけくわえた。二人のお話は不思議なくらいいつまでも覚えていた。 しかし、一番面白かったのは兄の和雄だった。和雄は専門学校入学資格検定試験の勉強をして修身と国語と漢文と歴史の資格を取っていた。あとは数学系の科目が残っているだけだった。和雄は何でも暗記をしていた。教科書もない何もない収容所生活のなかで、暗記していることは強みだった。 椙山君と新井君が暗記して見せた一二四代の天皇の名前もそのときなって兄におしえてもらい覚えた。教育勅語はもちろん天皇陛下が十二月八日にだされた開戦の詔勅も暗記していた。平家物語も「祇園精舎の鐘の声」などと延々と諳んじてみせた。 和雄は地理も教えた。砂の上に日本地図を書いて、「山があっても山梨県。鉄砲かついで鳥取県。すべってころんで大分県」。長崎県はなんというの「馬のしょんべん長崎県」「わー馬のしょんべんてあー」「馬のしょんべんは長いんだぞ」など子供たちは喜んだ。こうして九州から北海道まで県名を覚えた。河村さんの姉さんはこうした子供達の集まりに興味を示していた。お姉さんはものしづかな人だった。そして、和雄が子供らにいろいろ教えている間、側で黙っていっよに聞いていた。遠慮しがちに和雄の間違いなど直していた。和雄も「そうだったけ」などいいながら、それに従った。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2008-8-6 9:05 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
戦中戦後、少年の記憶 北朝鮮の難民だった頃・32 (林ひろたけ) 満州からお兄ちゃんが一人で逃げてきた・2
二月が過ぎても内地に帰れる見こみはなかった。何回も今度は帰れるという話が伝わったがそのたびに立ち消えになった。かなり寒い日だった。みんなで子供達が遊んでいるとき、その一人が 「おれの従兄弟のお兄さんが今機関車の機関士で順安にきているんだ。みんなに来い来いといっているんだ」 と自慢した。私たちは寺山君を先頭に六・七人ぞろぞろ機関車の中に押しかけた。従兄弟のお兄さんはまだ二〇歳前の青年だった。鉄道の帽子をあご紐でしっかり固定して朝鮮人の助手二人をのせてつぎつぎに日本語で指示をしていた。狭い機関車の中に乗りこむと機関車は引き込み線に向かって勢いよく走っていった。朝鮮人の助手につぎつぎと指示をしているお兄さんはすばらしく見えた。機関車の中は初めてだった。前の釜のふたが左右にバッツとひらくと助手の朝鮮人が石炭をシャベルで放り込む、「もっとと(もっと)たくさん、早くしろ」 などお兄さんは命令していた。「おまえらの国のためだ。がんばれ」 と日本語で叱咤していた。朝鮮人の機関士が少ないので日本人の機関士がそのまま仕事をしているんだよと教えてくれた。機関車は、普通江の鉄橋を渡り、砂金会社の引込み線を一〇分ほど走った。そこには米を積んだ貨車が置き去りにされていた。朝鮮人の助手たちは連結の作業のために機関車を離れた。 そのお兄さんは、助手たちが機関車を離れて作業をしている間に、「連中はいまトンニムマンセイ (独立万歳) といえばなんでもやるからな」 といって笑った。 「昭和一八年の戦争中だが、おれが機関士なったその月に、列車が脱線してひっくり返ったたんだ。転轍手が間違ったんだ。でも、軍事列車だったからたいへんだった。すぐにおれも警察に捕まって留置所に入れられた。そこはひどかったな。夜も横になって寝られないほどいっぱいだった。その中に、独立運動家が二人つかまっていた。もう留置所に二年もいるようだったが、彼らに対して強盗やこそ泥たちも一目も二目もおいていた。彼らだけ横になって寝ていたな。おれはすぐに二日で留置所からでられたが、戦争が終わったら彼らは英雄だろうな。トンニムマンセイは今朝鮮人ではおまじないみたいだよ」。子供たちに独り言のようにつぶやいていた。貨車を機関車に連結するとまた順安駅のほうに向かって戻ってきた。 「これから新義州(満州の国境の府)まで行ってくるんだ」。私たちはこのまま三八度線のほうに向けて走って、みんなを内地に返してはしいと願った。「開城(三八度線上の都市)まで五時聞か六時聞かな」とお兄さんはいった。 「どうして日本人を引き止めるんかな。俺たちのように特別の技術を持っているものは別にして。今度君らが内地に帰るときは客車をいっぱいひっぱってくるからな」。そういってわかれた。かえりにお兄さんは石炭をほしいだけ持っていけといった。ポケットいっぱいの石炭を持って顔を真っ黒にして収容所に帰った。石炭は親たちが奪い取るようにとりあげた。 子供達は「寒いよ」というか「お腹がすいた」というしかない状況になっていた。寺山君を中心に「おい松をたべにいこう」ということで日本人墓地に向かった。「共産主義だから人のものは俺のものだ」そんなことをいいながら、墓地の上手にある松林に入った。持ってきた肥後守(小刀)で松の皮をむいて皮と木の間にある薄い白い皮をとりだした。太い幹はどたくさん皮がとれた。立派な松がつぎつぎに皮がむかれていった。皮はすこし甘い感じがして飢えを癒してくれた。私たちがその場所を知っていたのは、戦争が終わる前、松根油をとりいったところだった。松根油とは松の根から油を搾り取り、飛行機の燃料にするために国民学校の四年生以上は勤労奉仕《注1》をしたところだった。日本人墓地には新しい土盛りがしてあり、細い丸太を削り、そこに死んだ人の名前がかいてある卒塔婆が立っていた。「もう何人死んだのかな」。寺山君は 「今度はお前だ」 など脅かすようにいっていた。 私たちは数日続けて、松の薄皮を食べにいった。ただ、ときどき朝鮮人の大人から 「こらあ」と追われるようになった。 ある日「君たちは日本人か」 と中国服を着て、しかもそれがぼろぼろになったひどい姿をした若いお兄さんが声をかけてきた。「ワー」 と逃げようとしたとき 「おれも日本人だ」 といった。 「一人で満州から逃げてきたんだ。君たちの家に案内してくれ」。お兄さんは真っ黒な顔でしもやけがいっぱいだった。綿入れの袖が切れていて物乞いの格好だった。日本人墓地らしいところにさしかかったので、休んでいたところだった。 そのお兄さんは開拓団に入っていたがみんなとちりじりになり、一人で歩いて日本にかえる途中だといった。 満州から歩いてきて、歩いて三八度線をこえるという、このお兄さんを私たちは特別な親しみをもった。収容所に案内し、日本人会の事務所にしている大村さんの社宅に連れていった。お兄さんは翌日もその翌日もわらじを作っていた。お兄さんの靴はぼろぼろになっていて「これからはわらじを履いて歩くんだ」と藁やら麻袋をほどいてわらじをたくさん作っていた。わらじを作る側に子ども達が群がっていた。お兄さんはわらじを作りながら「徐州、徐州と人馬は進む。徐州いよいか住みよいか」など戦争中の軍歌を聞かせた。 「開拓団ではこの歌を歌って元気を出した。 おれは一人で歩く時この歌を歌っている」など語っていた。 お兄さんは満州や朝鮮の話をいろいろしていた。 「満州では、日本人が道ばたで転がって死んでいるんだよ。飢え死しているのか病気かわからないんだがね」「たくさん死んでいるの」「そう。たくさん死んでいるんだよ。死んでも死体を片づける人が居ないんだよ」 「ソ連兵もすごいんだ。日本人の男は次々に捕虜にして収容所に送り込んでいたよ。おれはそれに巻き込まれないように逃げ出したんだ」。 満州では内戦がはじまって中国人同士が激しく鉄砲で撃ち合っている様子を話していた。ソ連兵の横暴が順安での比でないことを話した。「同じ共産軍でもパーロは違う。針一本略奪しない。国民党軍も保安隊もひどい。だがパーロはちがう」。このお兄さんは「パーロは違う」ということを繰り返した。パーロというのは八路軍(中国共産党軍)のことだった。このお兄さんの話を聞いて、ソ連兵がひどいことをくりかえしていたので、パーロに会いたくなった。どんな兵隊さんたちか知りたくなった。お兄さんは数日日本人会にいただけで、いなくなった。無事、三八度線をこえられたかその後の噂は聞かなかった。 私は兄たちにパーロのことを聞いてみた。兄達は「そうらしいね」とあまり関心はしめさなかったが、否定はしなかった。 注1:勤労をもって奉仕活動を行なう事 |
| 編集者 | 投稿日時: 2008-8-7 8:34 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
戦中戦後、少年の記憶 北朝鮮の難民だった頃 ・33 (林ひろたけ) 収容所にも春がきた・1
春になった。日中でも暗くなるほど黄砂が空を覆うと春は近づいた。「寒いよ」と泣く子はいなくなった。朝鮮の春は五月だった。 レンギョウが黄色の小さな花をつけ、それから桜も挑もみんな同時に咲いた。なかでもにせアカシヤの白い花は、朝鮮の林野の特徴になっていた。朝鮮の山ははげ山が多かった。その禿山に朝鮮総督府は、寒冷地で荒れた土地にも適しているにせアカシヤを植えた。 学校や役所のまわりには、日本国の象徴として桜の木が朝鮮総督府のお声かかり植えられ、アカシヤの垣根が作られた。順安にもアカシヤと桜の木が目だった。アカシヤの白い花は甘い蜜がいっぱいあって、私たちが飢えていないときも口いっぱいにたべてその甘味を味わっていた。順安にあった二セアカシヤの中には大きな木になるものもあった。日本人収容所の周りには高いポプラとアカシヤが数本垣根のようにたっていた。順安駅から収容所の側を通ってまっすぐにのびる広い道の街路樹も二セアカシヤの並木だった。 朝がやってくると子供達は二セアカシヤめがけて駆けつけた。そして咲き始めた白い房状になった二セアカシヤの花を手に入れそのまま口に入れた。私たちにとってただ一つの甘味だった。 二セアカシヤにはとげがいっぱいあった。そのとげが子供達の皮膚に刺さりそれがまた化膿しておできの原因になった。しかし、おできがどんなに広がろうと飢えには勝てなかった。二セアカシヤの花が咲いている間、私たちは二セアカシヤのお世話になった。 その頃、どこの家庭でも食べられる野草は何でも料理されていた。春の到来とともに道端や空き地にある野草を採取してきては食卓に載せていた。なにが食べられるかどう料理するのかが話題になっていた。たいていはおしたしにして塩をかけていた。その中でも二セアカシヤの葉っぱは煮付けにすれば、すこし苦かったがもっともおいしかった。 その頃 「大江さんのところは物乞いをしているらしい」。そんな噂がひろがった。大江さんは、終戦の年の六月になって内地から順安に引っ越してきた家庭だった。お父さんは東京帝国大学法学部をでて、四〇才前の若さのなか、雲母会社の社長で順安に赴任してきた。順安では雲母がとれた。雲母会社は従業員四〇名ぐらいの小さな会社だったが、戦争中は飛行機の部品になる重要な軍需会社だった。国民学校三年生を頭に双子も含めて五名もいる子沢山だった。朝鮮に渡ってくる時、荷物をまとめたところ空襲に会い、家具はなにもなかった。終戦前だったが順安の日本人たちは大江さんの家庭に、鍋や釜や布団を含めてみんなで出し合って支えていた。 大江家にとって、もともとなにもない状況での終戦だった。雲母会社の朝鮮人ともまだ知り合いになっていなかった。食糧を得るために行き当たりばったりに 「なにか食糧を」とたのんで歩いていた。 わずかの対価は払っていたが、それを 「物乞い」といわれたようだった。 五月のおわりに突如として晋司と紺野さんがかえってきた。何の連絡もなかったのでわが家ではびっくりもし、喜びもひとしおだった。兄達が迫撃砲弾をかたどった花瓶と手榴弾をかたどった灰皿をわが家の大きな穴の中に捨てた、それで財産隠匿の罪になり懲役三ケ月の刑期を終えて戻ってきたのだった。武器隠匿だったら返してもらえなかっただろう。そして返してもらえなかった長期刑になった多くの日本人は、その後の朝鮮戦争の中でほとんどが獄中で死亡したという。 晋司は命拾いをした。晋司はあまり詳しい話しはしなかった。ただ責任を感じていた兄達に「安田君があれは武器でない。ただの飾り物だ。と証言してくれた」と漏らしていた。そのころ保安隊の隊長だった安田さんこと洪泰保が失脚したという話が伝わった。その理由はわからなかった。 洪泰保はチーネがいっていたようにキリスト教のせいだったか、それとも晋司の証言に立ったことがその理由だったのかわからなかった。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2008-8-8 8:09 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
戦中戦後、少年の記憶 北朝鮮の難民だった頃・34 (林ひろたけ) 収容所にも春がきた・2 そのころ順ちゃんが元気をなくしていた。それは弟の安夫君の病気が重くなっていたからだ。 栄養もなかった。みんな骨と皮ばかりだった。そのうえどうもお父さんの結核が移っていたらしかった。 安夫君はもともと順ちゃんと違って元気のない子だった。収容所にはいっても姉ちゃんや兄ちゃんといっしょに遊びに出ることも少なかった。収容所の生活の中で体力そのものがなくなっていた。ハナがときどき見舞いにいったが、ただ首をふるだけで 「とてもだめだわ」 とつぶやいた。 安夫君は五月を待つことなく死んでしまった。子供の結核だった。お父さんの結核がうつったのだろう。 わが家のスペースは舞台だった。廊下の方に四段ほど舞台に上がる階段がついていた。順ちゃんのおばさんはハナに 「安夫ちゃんがダメだった」 と報告にきた時、おばさんは階段に顔をつけてワァワァと子供のように泣いていた。ハナが肩をだいていたがそれでも泣き止まなかった。順ちゃんもお姉ちゃんたちもどうしてよいのかわからないほど泣いていた。「あとの子供達を大切にしましょうよ」 とハナは慰めていた。 廊下を歩いているおじさんが、そんなおばさんをみて 「泣き女のように泣く女だ」 といって舌打ちをした。ハナは目をつりあげて怒った。「子供が死んでウソ泣きができますか」。「泣き女」というのは朝鮮人がお葬式の野辺の送りのとき、棺のまわりに死を悲しんで泣く女性のことである。朝鮮では葬式の行列に参列する人は大声で泣くことが多かった。特に泣く人が多いほど盛大な葬式だということで、お金持ちはたくさん女性を雇って 「泣き女」 にしたてると噂をしていた。 私もときどきそんな葬式をみたことがある。白い服をきて悲鳴に近い声を上げて泣く女性達を見てあれが泣き女なのかと、ものめずらしくみたことがあった。日本人はその習慣を少し軽蔑してみていた。子供が泣き止まない時など 「泣き女みたいに泣くな」 と叱ることが多かった。私はそうした叱かられ方が嫌いだった。順ちゃんのお母さんは安夫君が死んだときそう悪口をいわれるくらい泣いていた。 大村さんの家のあっちゃんは、年の割に大きな体をしていて大食漢だった。相変わらず 「わーわー」 というだけだった。それでも両親はあっちゃんを大事にしていた。「もう食べるものもないなか、あっちゃんみたいな子は死んでもいいんだ」 という大人がいた。その時、順ちゃんが激しく怒った。「そんなこといったらみんな死んでしまえばいいんだ」。順ちゃんが怒ったとき、順ちゃんちは 「お父さんも、安夫君も死んでしまったからな」 と思った。 それから順ちゃんはあっちゃんを特に大事にしはじめた。あっちゃんのお姉さんの恵美子ちゃんとも仲良しになった。私はすこし二人が仲良くしているのに腹が立つことがあった。でも順ちゃんと遊ぶほかなかったので、大村さん姉弟ともなかよくして遊んだ。遊ぶといっても、いっしょに時を過ごすだけだった。 六月になって激しい雨の日が続いた。雨の日は私たちはどこにも行けず、子供達はクラブの廊下のようなスペースでじっとしていた。順ちゃんが 「ぼくたちどうして日本人なのかな。朝鮮人は日本語を上手に話すのにぼくたちはどうして朝鮮語も話せないんだろう。日本人でなければこんなにひどいことにならなかったのに」 といいだした。 寺山君は一学年上のお兄さんらしく、「日本は一等国民だったのだよ。戦争に負けたから四等国民になったんだよ」 といった。大人たちは 「一等国とか四等国」 とかよくいった。でも順ちゃんは 「それでもなぜ日本人なのか」 ともう一言いった。私たちには難しく重い話だった。「早く内地に帰りたいな。ぼくらは難儀するために大阪から朝鮮にきたみたい」 と寺山君が続けた。寺山君は終戦になるまで、「朝鮮にきて白いご飯も食べられて良かった」 としばしば言っていた。 洋武は朝鮮でうまれ内地に一度も帰ったことはなかったが、それでも内地に早く帰りたかった。 内地に帰れば、こんなにひもじい思いもしないですむし学校にも行けるのでないかと考えていた。 「おれたちなにも悪いことしたわけでないのに」 と寺山君はいった。順ちゃんは 「悪いことした子は神様がちゃんと見ていて、罰があたるんだよ。長崎のおばあちゃんがいっていた」 とまだ戦争が終る前に時々言っていた。洋武は 「小さい時、近所の朝鮮人のこどもをいじめたことがあったが、あれが悪いことかな」 と考えていた。 そのころ内地に帰れる話が大きくふくらんだ。先発隊が栗本鐵工所の若い数家族を中心に三〇名ほど組織された。そして順安駅から一日に数本しか走らない列車に強引に乗り込んで南に向かった。しかし、四日目につかれきった表情でみんな帰ってきた。平壌の駅でおろされて、そのまま平壌のホームで野宿をさせられて、結局送り返されてきた。 「今度こそ帰れる」 という思いは無残に打ち砕かれた。「朝鮮終戦の記録」 という本によるとこの頃、北から日本人の集団が三八度線を越えて次々に南下をはじめていた。アメリカ軍の若い将校が、思いつきのようにソ連軍の将校に 「日本人が乞食のような姿で次々に南下してきて困っている。日本人を送り込むのは止めて欲しい」 と抗議をした。その結果ソ連軍は、日本人の南下を全面的に禁止して三八度線の境界の警戒をいっそう強めた。ろくな食糧も与えず、体面だけ気にしてそれによってさらに多くの犠牲者が生まれていた。その時期と順安の先発隊が送り返されてきた時期と同じごろだった。 春がすぎて夏がやってきた。寒い時にも死ぬ人が多かったが暑くなるとまた死ぬ人が増えてきた。 一人の餓死者がでるということは、その何倍かの人たちが病気で死んでいくことだった。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2008-8-9 7:20 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
戦中戦後、少年の記憶 北朝鮮の難民だった頃 ・35 (林ひろたけ) 収容所にも春がきた・3 河村校長の小父さんは夏の入り口であっけなく亡くなった。それは隣に住んでいたわが家の誰もが気づかなかった。六〇歳前の静かな死だった。その時も兄達が墓を堀りにいった。農業関係の役所の小父さんも亡くなった。 それに続くように小島校長先生の奥さんが二人の子どもを残して死んでしまった。小島校長先生は終戦まじか出征したが、戦後順安に帰ってきていた。中村校長先生の奥さんは活発の人で赤ちゃんを負ぶって教室に現れるなどして生徒達になじみが深かった。しかし、小島先生の奥さんはおとなしい人で生徒達との交流も少なかった。私たちもあまり付合いはなかった。 小島校長先生は校長だったとき、子ども達にたいへん神経質に対応した。戦局が悪化するたびにいらいらして子ども達は怒られていた。奥さんが亡くなると人が変わったように話もしなくなった。子ども達が挨拶をしても顔をそむけて返事をしなくなった。子どもの面倒をみるからといって日本人会の使役にも出てこなくなっていた。「小島先生は変わられた」 母は繰り返しそう話した。そのころ末永先生の姿は収容所であまり見かけなかった。朝鮮人のヤンバンの家庭に家政婦になってお手伝いにいっているらしかった。 日本人はみな飢えていた。大人たちは食事を毎日どうして確保するかでたいへんだった。そんなにお腹がへっているのにみんな下痢をしていた。洋武も他の子供達も、もう下痢には慣れっこになっていた。子供達はもうかってのように動き回ることができないほどおなかがへっていた。 収容所の線路を越えると普通江だった。普通江はあいかわらず濁った黄色い川だった。オマ二たちがその濁った川で洗濯をしているの姿も変わらなかった。白い服が基調だった朝鮮の服を砧でたたきながら洗濯をしていた。 私たちはその岸辺の草むらで蛙を捕まえた。蛙は大きなのもあったが小さいものが多かった。蛇も捕まえた。順ちゃんも寺山君も他の友達も蛙は捕まえることができたが、蛇は苦手だった。 蛇を捕まえるのは、私の役割だった。私は蛇の頭を後ろから素手で抑えこみ蛇を捕まえた。国民学校一年生のとき「女の子をいじめる」とみんなに嫌われた蛇退治が役に立った。蛙も蛇も皮をむいて持ちかえった。拾ってきた石炭に火をおこし七輪の上で焼いた。香ばしい匂いが広がると「このにおいな一に」と収容所の小母さんたちが集まってきた。子ども達も集まってきた。皮をむいただけの蛙の姿を見て 「キヤー」 と奇声をあげた。「これはな一に?」蛇を肥後守(小刀)で五センチぐらいに切って七輪にのせてあった。私たちは得意そうに「蛇だ」といった。みんなは初めは顔をしかめたりしていたが、そのうちに他の子ども達や小母さんたちも蛇や蛙を採りに行くようになっていた。 それでも私たちには望外のたんばく質だった。そのころは朝鮮人の間にも飢えが広がっていた。アカシヤの花も蛙や蛇も朝鮮の子供達と争って取るようになった。 「ロシヤが米をみんな持っていったからだ。日本から独立したが、ロシヤは日本よりひどい」。そういったチーネの言葉を思い出していた。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2008-8-10 10:09 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
戦中戦後、少年の記憶 北朝鮮の難民だった頃 ・36 (林ひろたけ) 第三章 必死の逃避行
逃避行の準備と 「姥棄て」 の悲劇 八月になった。終戦になって一年たった。「もう一冬はこせない」多くの日本人が期せずして語りはじめた。その間も 「今度はかえれる。ソ連が汽車を出すことをみとめた」など噂が広がった。私たちは何度も 「今度こそ帰れる」 という言葉を聞いたがそのたびに裏切られた。 「三八度まで七〇里はある。歩いて逃げるかそれともここでみんな死んでしまうか」。その言葉に子供の私たちにも切実感があった。 大人たちは何度も会議を開いていたが、七〇里を歩いて逃げることになった。満州から歩いて逃げてきたお兄さんのようにあんなに歩けるのだろうか。順ちゃんちのように光夫ちゃんがまだ三つだけど七〇里も歩いて行けるのだろうか。そんな心配が心をよぎった。 歩いて逃げるのだから野宿する以外ない。ということは覚悟の上だった。会議の中では「二週間ぐらい分の食糧が必要」とか「持っていくものはどうするのか」とか話は具体性を帯びてきた。 子ども達もいままで「今度こそ帰られる」という言葉になんどもだまされてきたが、大人たちの動きはいつもと違っていた。 問題になったのは子どもとお年寄りだった。私たち一家と同じ舞台にいた日野さんの家は深刻だった。日野さん一家は満州から避難していたが、足の悪い七〇歳を超えたおばあちゃんと若いお母さんと八歳ぐらいの子供を頭にした三人でお父さんはいなかった。おばあちゃんが必死の形相で孫の食事を横取りしようとしていた。そのすさまじさに私もびっくりしていた。この数日おばあちゃんはなにも食べ物が与えられてもらえず、孫の食事をとろうとしていた。 「子供は背負っても歩ける。しかし、年寄は背負うわけにはいかない」。そのことが歩いて三十八度線をこえるときに最大な問題になっていた。歩いて逃げるほかないという意向が日本人のなかにたかまっていたとき、男手がなく、年寄のいる家庭では深刻な問題になっていた。満州からの避難民には男が極端に少なかった。死んでしまった河村校長先生、お医者さん代わりになった辻村先生、それにロシヤ語の出来る渡辺さんほか数名だった。「姥捨て」が密かに実行されていた。体の弱いお年寄には食事があたえられず、餓死させることが二つ家庭で行われていた。 おばあちゃんと孫の女の子の喧嘩は悲惨だった。順ちゃんは「ぼく、おばあちゃんにあげようか」といったが小母さんは黙って首を横に振っていた。おばあちゃんは大喧嘩のあと二日ほどして死んでしまった。 明日、逃げ出すという夜、各所にあつまって日本人会長の大村さんが説明にきた。 「いいですか。いろいろ努力をしましたが、結局保安隊から許可は出ませんでした。私たちは勝手に逃げるのです。もし、保安隊やソ連兵につかまったら大村勇一が全責任をとります。大村勇一の命令でここを逃げ出したということにしてください」。 大村日本人会長の悲壮なあいさつだった。 八月三〇日、いよいよ逃げ出す日の朝がきた。 子どもの胸には名札がつけられた。帰るべき内地の住所だった。洋武の名札は 「長野県北佐久郡春日村四八二五番地林洋武」 と縫いつけたあった。晋司は 「戦争の時、兵隊さんは名札を身につけている。戦死したとき誰かわかるように体につけているんだ」 といった。子どもにとってはそれは迷子札でもあった。「迷子にならないように。迷子になったらおしまいよ」 と大人たちは子ども達に注意をした。 夜がまだ明けないころみんなルック一つを担いでアルミ製のなべや飯盒ややかんをもって動きだした。鉄製の釜などは重いので持たないようにという指示だった。時計というものがすでに日本人の集団の中になかった。多分午前三時ごろだったと思う。班が三つに分けられた。最初にスタートしたのは、栗本鐵工所の班だった。三〇分ぐらい置いて満州から避難して来た人達だった。 河村さん一家もお医者さんだった辻村先生たちも出かけていった。 最後がもともと順安にいた私たちだった。三つに分かれた班のなかでは一番多く百名近くになった。「子供には絶対に声を出させるな。泣き声は禁物だ」 くり返し強調された。 晋司はルックに大きな鍋をくくりつけた。和雄のルックにも、もう一つの鍋がくくりつけられた。ハナはやかんを手に持つといってみんなから反対されて典雄がルックにしばりつけた。 順ちゃん一家は、おばさんが大きなルックを背負いアルミの鍋と飯金をぶら下げていた。前には敷布で作った大きな肩掛けかばんをさげていた。小母さんは「ミッちゃんを背負うときには肩掛けかばんでないと荷物がもてない」 と二つに荷物を分けた。お姉さんたちもルックを背負って、順ちゃんが小さなルックを背負った光夫君を連れていた。「武ちゃん手伝ってね」 そういわれると洋武は自分のルックだけ背負っただけだったから順ちゃんにくらべれば身軽だった。光夫君はもう聞き分けは出来るようだったが、それでも大人たちの緊張が伝わるのか震えていた。今にも泣きそうだった。あっちゃんが 「ワァーワァー」 言い出した。「静かにしろ」 というするどい声がひびいた。いつも口を開いていたあっちゃんをお父さんが口を押さえたので苦しそうでかわいそうだった。順ちゃんと恵美子ちゃんが口に指をたてるとあっちゃんは不思議にだまった。隊列は順安駅から線路にそって北に向いて歩いていた。「三八度線は南にあるのじゃないのかなあ」と私がいうと 「黙ってついていらっしやい」 ハナがきつい調子で叱った。大人たちの緊張が子供にもひしひしと伝わってきた。そして昔のわが家のリンゴ畑のすそにそってぐるりと周り京義国道を横切ったところで小休止があった。朝の露で足元はぐつしやりとぬれていた。まだ薄暗かった。そこまで幸い朝鮮人や保安隊に見つかることはなかった。 「ここから山に入る。東に行く」とつたえられた。もう光夫ちゃんは歩けなかった。そして姉ちゃんが背負うことになった。順ちゃんがお姉ちゃんのルックを背負った。そして順ちゃんのルックを背中に光夫君を背負ったお姉ちゃんが前に両腕でかかえた。順ちゃんも重そうだった。でもお姉ちゃんはもっとたいへんだった。「お昼に少しの荷をわけようね」 とおばさんがいった。すでにいくつかの家族では持ちきれない荷物を捨てていた。 せまい山道にはいったころ夜は明けはじめていた。 「日本にかえれる。内地に帰れる」 そんなうれしさと遠足でも行けるような気持ちもあって、はじめは夜が明け始めた道をいそいでいた。大人たちは昨夜はほとんど寝ないで準備をしていたのだと思う。十時ぐらいになると大人たちがつぎつぎ休み始めた。「落伍したらそのままおいていきますよ」という声もあったが、やはりしばしば休まざるを得なかった。そのころになると朝鮮人にも会うようになったが、不思議そうに見るだけで問題はなにも起きなかった。お昼はみんな家族毎に集まって弁当を食べた。わが家は、ハナの作った粟が半分以上はいったおにぎりだったが、それはまわりの家族と比べても一番よかった弁当だった。おにぎりが握れないようなバラバラの豆かすなどおなべや飯盒をだして食べている家のほうが多かった。 その夜は、舎人里というところで泊まることになった。部落近くの川原で夕食が作られた。家族毎に石を積んで疲れた体でみんな薪を集めてきた。それからの逃避行の中で川原で野宿することが多かった。水が手じかにあることと川原の石で炊事のかまどがつきやすかったからだった。 わが家では、兄たちが薪と枯葉など集めてきた。火がすぐついたが、順ちゃんのところでは、お姉ちゃんたちの集めてきた薪の量も少なく火が簡単にはつかなかった。兄が集めてきた枯葉でやっと夕食の火がついた。なべや飯盒での炊飯だった。夕食と朝飯はどの家庭でも粟がゆやスイトンだった。「昼は炊事をする時間がありませんので、弁当をつくってください」という注意があった。 団長さんが部落の朝鮮人と交渉して病人と子供だけは夜露がかからないようにと軒先を貸してもらった。私たち一家は、空を見ながら星をみながらの川原の野宿だった。軍隊にいた晋司は野営の経験があってみんなにいろいろ教えていた。「朝方露が降りるのが激しいから顔になにかかぶせて寝るように」とみんなに教えていた。お年よりは敷布や風呂敷をかけて休んだ。洋武と由美は足を立て膝にして縛られた。そうして寝ると疲れがとれるという話があって兄たちが私と由美の足を縛った。この足縛りはこの夜だけだった。あまり役にたたなかったのかそれとも兄たちが面倒臭かったせいかわからない。洋武も由美も足を縛られ、帽子を顔に置いただけで休み始めた。疲れていた。誰もが疲れていた。そしてこれから何日も歩かないといけないと思うとはじめの遠足気分はなくなっていた。いま舎人里を地図でみると順安のちょうど東方になり直線距離で十数キロはあった。しかも、たいへんな山道だった。お年よりや子供も含む一日の行程としては相当の強行軍だった。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2008-8-11 7:58 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
戦中戦後、少年の記憶 北朝鮮の難民だった頃・37 (林ひろたけ) 北斗七星を頼りに 少し眠ったかと思うとハナが洋武と由美の間に割り込んで横になった。みんな空を見上げた。 ハナは二人を揺さぶり起こして怒るように話した。 「いいね。あの北斗七星の先に北極星があるのわかるでしょう。昔の人はあの星を目印にして旅をしたのよ。昼は太陽をみて南に、夜もあの星を背中に南に行くのよ。迷子になっても南に南に行けば内地に戻れるのよ。開城のことはケサン。京城はソウル。釜山はプサンよ。朝鮮人にきいてでも、なんとしても、南にむかって歩くのよ。今日見たとおり道標はないのよ。お前たちは星と太陽を便りに歩くのよ。どんなことがあっても生きて内地に帰るのよ」。 ハナの言いかたはきつかった。ハナはこの子達が迷子になっても一人でも生き延びて帰れと諭していたのだった。洋武にはそこまで理解が行き届かなかったが、由美姉さんは「怖いわ。私は迷子にならないから連れていってね」といいながら泣いていた。 翌朝も早く起こされた。夜露がベットリと体についていた。前日の疲れが体中に残っていたがそれでもみんな励まし合うように朝ご飯の準備をはじめた。 三日目の午後、初めて車が通れるような広い道を歩いた。その日も暑い日だった。誰もがもうおしゃべりはしないで黙々と歩いていた。突然、前の方から「ソ連兵だ。逃げろ。側の高梁畑に逃げろ」という声がきこえてきた。集団はいっせいにチリチリ、バラバラに散った。幸い高梁畑が両側にひろがっていた。悲鳴も上げられなかった。道から高梁畑はすこし低くなっていた。みんながサット道から飛び降りたが、光夫ちゃんはおびえた顔をしながら飛び降りることができなかった。順ちゃんが手を出しても光夫ちゃんには届かなかった。誰かが「早くしろ。見つかってしまうぞ」とどなった。焦るとかえって飛びおれなくなっていた。泣き声になっていた。「泣いちゃだめだ」大人の人が光夫ちゃんを引き吊りおろして口をふさいだ。順ちゃんが光夫ちゃんを引き取って高梁畑に逃げ込んだ。 高梁はトウモロコシのように背の高い作物だった。だから畑で人が隠れるだけの高さはあった。しかし、百名を越す集団が隠れたからと言って相手側が知らないはずはなかった。それでも、みんな必死で顔を伏せたり声を押し殺してじっとしていた。やがて鉄かぶとをかぶったソ連兵十数人の一隊が、あのマンドリン型の自動小銃を腰だめにもって行進してきた。戦争そのもの怖さだった。かくれんぼの時とはまったくちがった緊張が体中を覆っていった。彼らはそのまま通りすぎていった。 「もういいらしい」という声がした時、洋武の前にかぼちゃが一つ転がっているのに気がついた。 そう大きくはなかったが、それでも食べるとおいしそうだった。それをルックにしまいこんだ。 みんなが道路に出て、点呼がおこなわれた。みんなは恐ろしさのあまりがたがたと震えていた。 畑の泥が体中について、そうでなくとも汚れていた服装がいっそう汚くなっていた。子どもが一人行方不明になっていた。またそれをさがしに時間がかかった。行進が始まったのは二時間近くたっていた。 両側に薮がつづく細い道を長く歩いていくといきなり大きな河に出た。その河の水は普通江のようにごってはおらず青々としてゆっくりと流れていた。順ちゃんも私も「大同江だ」と叫んだ。平壌にいったとき大同江をみたことがあった。川の色が青々としているだけで私たちは大同江とわかった。しかし、見える限り橋はなかった。向こう岸がかすんで見えるほど幅の広い大河だった。集団はだらだらと水の流れのほうにすすんだ。 「このまま下流に行くと平壌に出てしまうよ。ソ連兵につかまるよ」誰かがつぶやいていた。 「大同江のすべての橋にはソ連兵や保安隊が警戒していて、日本人の通過を止めている」。と伝えられていた。日本人の逃避行は、橋のないところを選んで渡し場から船で大同江を渡ることになっていた。 午後の日が過ぎていった。その時、渡し場が見つかった。河の岸にあまり大きくない川舟が二隻並んでおいてあった。朝鮮語のできる人がこの船で向こう岸にわたるように交渉することになった。交渉はなかなか成立しないで、大人たちが集まっては話し合いを繰り返していた。船を出すために法外なお金を請求されているらしいことがわかった。集団にはお金がなかった。それでもこの渡し場を渡らないかぎり三八度線にはいけなかった。 結局、まだお金のある個人からお金を借りてみんなで借用書を書いた。わが家も借用書を書いた。朝鮮人の交渉と日本人の話し合いで時間はどんどん経っていった。それでも夕方になって船は出ることになった。船は決して大きくはなかった。集団が二つに分かれても船にあふれるようになった。船に乗った時、みんなはほっとした感じがあった。大同江の川幅は船に乗るとさらに広く見えた。なかなか岸にはつかなかった。人が乗り過ぎていたので予定よりずっと流されて下流に着くことになった。着いたところはほとんど薮の中だったが岸をあがったところで野宿になった。 洋武は夕食前にかぼちゃをそっとハナにみせた。母は黙って受け取るとそれを夕食のおかずにくわえた。洋武は逃避行のさい野荒しをしたのはその時だけだった。しかし、林家はそのかぼちゃがその夜の飢えをしのいだ。 四日目になった。子供にはどこをどう歩いているのかわからなかったが、道はいつも狭いあぜ道みたいな道をせいぜい二列になって、太陽の照りつける中ぞろぞろと歩いた。ときどき子供を叱る親たちの声と泣き出す子供の声がきこえるだけで、話し声もあまりたてないで歩きつづけた。 私は順ちゃんといっしょだったが、歩くのに精一杯であまり話をすることもできなかった。順ちゃんは光夫君の世話を姉弟で交代でみながらお母さんを助けながら歩いていた。 夕方になって保安隊につかまった。保安隊長は日本人の集団から米を取り上げようとしていた。その周辺には水田は見当たらなかった。「米をだしなさい。米を出せばとおしてあげる」とその保安隊長は片言の日本語ではなした。逃避行で出会った保安隊の隊長は総じて日本語が上手だった。しかし、この保安隊長はほとんど日本語ができなかった。ここの土地は米が獲れない貧しい山間の村だった。そこで日本人の逃避行をする集団から米を取り上げようというのがねらいだった。二週間の逃避行に備えて多くの家庭で米を用意していた。各家庭一握りづつ出し合って二升ほどの米が保安隊長にわたされた。保安隊長は、にこにこ顔で数人の保安隊員は歓声を上げて立ち去った。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2008-8-12 8:07 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
戦中戦後、少年の記憶 北朝鮮の難民だった頃・38 (林ひろたけ) 雨宿り その夜も川原に寝ることになった。木の古い橋があって子どもやお年よりはその下で夜露を防いで寝ることになった。ぐつすり寝ていた時、集団が急にざわついていた。朝は空け始めていたが、雨が振り出していた。「ここでは水が増えてきたらどうにもならない。すぐ出発だ」。朝飯も取らずに行動は開始されたが雨は激しくなるばかりだった。 「雨が一番困る」大人たちは嘆いていた。雨は豪雨になってきた。気温が急に下がり寒さも激しくなりあちこちで悲鳴が上がった。 小さな部落があった。そこに数軒の比較的大きな農家が続いていた。瓦屋根が反っている朝鮮家屋で明かにヤンバンの家で、母屋と牛小屋がある農家に雨宿りをしようとした。その時、先頭の人が歓声をあげた。前に出発した満州組があちこちの家の軒先や牛小屋で休んでいた。そこに私たちの班もいれてもらうことになった。満州組のなかにすこしづつあけてもらい雨宿りになった。洋武と順ちゃん一家が入った牛小屋にはすでに河村さんのお母さんと姉妹がいた。簡単な挨拶のあとそのまま私たちはぬれたまま休んだ。「体をふけ。藁でもよいから体をしっかりふけ。」晋司はみんなに号令をかけていた。女の人も半ば裸になって手じかにある藁で体を拭いた。手ぬぐいもリックもなにもかもピッショ濡れていた。牛はいなかったが、数日前まで牛がいた感じのする小屋だった。牛の汚物のにおいが強くした。蚊がブーンととび、蝿が壁にべっとりするほどっいていた。しかし、それでも雨に濡れないだけでもよかった。もう昼近くなっていた。その日は朝からなんにも食べていなかった。お腹がすいても、昼飯にはならなかった。 順ちゃんのおばさんが、洋武と由美姉さんに炒り豆を十粒ほど渡してくれた。「しつかりかむのよ。百回ぐらいかむのよ」。順ちゃんと数えながらかみつづけたが、その途中にねむりはじめた。逃避行のなかで他の家族と食糧の交換はまったくなかった。それはそれぞれの家庭が飢えをしのぐので精一杯だったからだった。順ちゃんのおばさんが、わずか十粒ほどの炒り豆だったけど私たち姉弟に与えたことは菊村家にとってもたいへんなことだった。落ち着くとともに大人もこどもも死んだように寝始めていた。夕方になってはじめて親たちがそれぞれ食事を用意してくれた。母屋は大きな家だった。瓦屋根で順安の新井君の家よりさらに大きかった。そのヤンバンの朝鮮人たちは、時ならぬ避難民にとまどいながらも日本人のこの集団を可能の限り暖かく接していた。娘さんが日本語が上手で日本人と少しも変わらず一家で親切にしてもらった。台所の土間も貸してくれた。それぞれの人が夕食を作った。そして各人のいろいろな頼みごとにも応じていた。 夕方になってやっと粟かゆを食べることができたが、雨に濡れて体が冷えていたので生きかえったおもいがした。 雨は翌日も続いた。一日目は眠りつづけた私たちも二日目の午後になると少し余裕が出てきた。だれとなく雑談が始まった。こんなときに必ず話題になるのが、食べ物の話だった。平壌の三越百貨店の一階にあった「もなか」はおいしかった。という人がいた。私も順ちゃんももなかという菓子を知らなかった。満州組の誰かが新京の百貨店のお菓子のおいしさを自慢していた。 河村さんのお姉さんが「まるで奥の細道のようね。ほら、『のみ虱馬のしとする枕元』 っていう句があるね」。誰に言うともなく話し始めた。和雄は、こことばかり 「月日は百代の過客にして」と奥の細道の最初を暗誦しはじめた。これにはハナもいっしよに暗誦をはじめた。「子供のころ覚えたことは忘れないね」とつぶやいた。「おばさんもよく覚えているのね」みんなが感心していた。 「奥の細道ってな一に」「芭蕉という人の旅日記のこと。昔、芭蕉という俳句を作る人が俳句を作りながら旅をしたときの日記なのよ。昔はね、みんな旅は歩いたの。私たちみたいに」とハナは説明した。 それからも、河村さんと和雄は競争するように俳句を次々に出し合った。「一ツ家に遊女も寝たり萩と月」と和雄が言った時、ハナは「和雄やめなさい」といってぴしゃりと和雄をたたいた。 順ちゃんが「遊女ってな一に」と聞いたが大人たちは黙って誰も答えなかった。ただ、その場の雰囲気が少しまずいものになっていた。ハナが和雄を注意したことがかえってその場の雰囲気を壊してしまったようだった。 順ちゃんは「ぼくたちも内地に帰ったら奥の細道読もうね」と洋武にあいづちを求めてきた。 雨はなかなかやまなかった。その牛小屋に二晩泊まることになった。 父晋司はこのヤンバンの家で藁をもらってわらじを作り出していた。逃避行の中で食事の次にみんなが困ったのは靴がいたんでしまうことだった。終戦後一年以上立っていた。この間ほとんどの家では新しい靴を買うことが出来なかった。子供たちは兄や姉達のお古をはいたが、長男長女は一年の間に足が大きくなっていたし代わりの靴は手に入らなかった。 順安を出発する時から靴の心配は深刻だったが、すでに靴がなかったり裸足になって歩く人も出ていた。晋司は農家出身だったのでぞうりやわらじを作るのは上手だった。 そこのヤンバンの家で藁を提供してくれたが、時間のある限りは晋司はぞうりとわらじを作った。そしてわが家の分をとってそれ以外を靴のなくなっている子供たちに提供した。 次の朝、九月四日になっていた。やっと、雨もやんで出発することになった。北朝鮮から引揚げてきた難民達の記録にはこの三日にわたって続いた雨の中、三十八度線を越え、多くの犠牲者が出たことが書き残されている。南へ南へ、歩いて逃げ出した日本人達にとってうらみの雨だった。私たちはともかく牛小屋でこの雨を避けられただけでも幸運だった。 河村さんたちや満州組が先に出かけていった。大人たちの準備が遅れている時、順ちゃんが「武ちゃん。紙ができているよ」と声をかけてきた。 牛小屋の続きの細長い倉庫の部屋に、日本語の上手な娘さんが年輩の男の人と並んで仕事をしていた。白いにごった液が張ってある大きな水槽の中に障子の枠のようなものをいれて、ゆすると薄い白いものが広がっていた。それをていねいに側の板の上にのせていた。ハナもやってきた。 「よく見ておきなさい。日本の障子紙もこうして作るのよ。内地の田舎でも紙をこうしてすくのよ。朝鮮で見るのははじめてね」。私たちに話し掛けた。若いおねいさんは上手な日本語で「君たちどこからきたの。そう順安。これからも三八度線まで、まだまだ歩かないと行けないね」などと言った。「うちは平壌の女学校をでたんだよ。だから順安の友達がいたんだ。朝鮮の人だけど」。 私たちは「美代子姉さんも平壌高女だよ。末永先生も平壌高女だよ」といってすっかり親しくなった気分になった。 「君たち知っている。紙もね。瀬戸物もね。昔、みんな朝鮮人が日本人に海を渡って教えたんだよ」 「だって朝鮮人は瀬戸物でなくてサバリ(真鍮のお鉢)で食べているのじゃない」。洋武はその家でも真鍮のサバリで食べているのを覗き見していたのでそういった。「でもね、黒い水瓶だってあるでしょう」。朝鮮のおねさんが笑って言い返した。「日本人はいままでみんな日本のほうが優れているって言っていたが、朝鮮人も昔はみんな日本人に教えたのよ。日本の歴史は二千六百年でしょう。 朝鮮の歴史は五千年もあるのよ。日本人がまだ紙など知らない頃、朝鮮ではもう国ができていたのよ。朝鮮では今年は檀紀四二七九年なのよ」。そのお姉さんは朝鮮人が日本人にいろいろ物を教えたことを繰り返しながら、仕事を続けていた。朝鮮の歴史が五千年もあることは知らなかった。日本の歴史は、昭和十五年皇紀二千六百年祭を迎えたとき、「キゲンは二千六百年」という歌がつくられ、その後も学校ではその歌を教えられ歌っていた。「こんなに長い歴史をもつ国だから、神国だから日本は負けることはない」と教えられていた。朝鮮が日本より長い歴史を持っていることや、瀬戸物まで朝鮮の人に作り方を教えてもらったということは初めて聞くことだった。 順ちゃんは「へえ知らなかったな。そんなに長い歴史があるのにどうして朝鮮は日本に併合したのかな。」とつぶやくように問い掛けてきた。お姉さんはすかさずに「日本が朝鮮に攻めてきたのよ。日本が戦争に負けたので今度朝鮮は独立するの」。独立するという言い方に力が入っていた。「朝鮮は四等国。日本は一等国」戦争中は何度も日本人社会では語られてきた。しかし、戦争が終わると今度は「朝鮮が一等国になった」というようになった。その朝鮮人のお姉さんは朝鮮が独立しようとしていることを誇りにしていた。私たちが収容所で一年を過ごす間に、朝鮮の人たちは民族の歴史と誇りを語り合っていたのだ。この姉さんも控えめだが、昔日本人にものを教えたのは朝鮮人だと私たちに強調していたのだ。お姉さんは話しながらも手を休めず、紙すきは絶え間なく続けられていた。その手さばきを見ながら、そのときいやな感じはしなかった。そのお姉さんが親切に私たちの面倒を見てくれたこともあった。同時になにかほんとうのことをいっているんだなという思いもあった。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2008-8-13 9:20 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
戦中戦後、少年の記憶 北朝鮮の難民だった頃・39 (林ひろたけ) マラリヤ熱の発熱とハナの胃痛
その日も黙々と歩いた。歩かされた。順ちゃん一家はみんなで光夫君の世話を交代で面倒を見た。大村勇一会長のところも大村さんは世話人会の会長さんでなにかとみんなのことを気遣いながら、アツちゃんの面倒も見ていた。アツチャンは体が大きくて小母さんがおんぶするわけにはいかなかった。疲れてくると「おんぶ」というアツちゃんを大村さんは自分のルックを小母さんに渡してアツチャンをおんぶした。それから見ると成人した男が三人もいるわが家はめぐまれていた。 その日の午後、川にぶつかった。普段は浅い川の様子だったが、雨で川の水は勢いよく流れていた。橋はなかった。大人の一人がまず歩いてジャブジャブと渡っていった。大人の腰ぐらいの深さだった。「さあ、みんな渡ろう」という声でいっせいに川を渡り始めた。私も順ちゃんといっしょに渡ろうとした。しかし、川の勢いに流されて思うように進まないうちにみんなから大きく遅れてしまった。しかも深みに足を取られていた。恐怖が走った。しかし、声を出すことが出来なかった。水が首のところまできてルックが浮き、それに体の自由を失っていた。順ちゃんが大きな声で「おばさん。武ちゃんがたいへん。武ちゃんがおぼれている」。私は大人たちの歩いたところよりかなり川下に流されていた。 母ハナが必死の顔で戻ってきた。体の小さなハナも川の流れに流されていたが、ともかく私の手を支えて引きずるように引っ張り出した。和雄兄さんももどってきた。びしょぬれになって洋武は対岸まで歩くことが出来た。「順ちゃんありがとう。洋武を助けてくれて」。ハナはそう声をかけたが、順ちゃんの一家も光夫君を中心にたいへんだった。おばさんは川を二回も往復して荷物を渡していた。 ハナは洋武の額に手をやった。 「まあ、熱がある。ひどい熱」。ハナは叫んでいた。体温計など誰も持っていなかった。 ハナは「四〇度近い熱よ」と強調した。洋武は高熱で頭がぼんやりとしていた。「マラリヤよ。きっと」 ハナは恐ろしい顔をした。マラリヤは蚊を媒介とする伝染病だった。それまでもときどき朝鮮ではマラリヤが発生した。だから誰もがマラリヤを知っていた。毎日か一目置きか、同じ時刻に激しいふるえとともに四〇度をこえる高熱が出る。そして、体が衰弱して死を迎える熱帯系の伝染病だった。マラリヤには絶対の特効薬キニーネがあった。しかし、集団にはキニーネをもっている人はいなかった。持っていたにせよ、人にあげる余裕はなかった。 洋武は川を渡ったところでぐつたりしていた。熱がどんどん上がっていくのが自分にもわかってきた。それでも歩かなければならなかった。一目目は二時間ぐらいの熱に苦しんでともかく終わった。その夜、ハナの腹痛が出てきた。ハナには胃痙攣か胆石痛かわからないが胃痛という持病があった。その持病が洋武のマラリヤと同じ日に出てきた。 その夜、林家は晋司を中心に輪を作っていた。私は晋司の膝を枕に横になっていた。今まで父の膝に頭をつけて横になるようなことはなかった。ハナは胃の痛みで顔をしかめながら「私をおいていってください。洋武は将来ある身だからなんとしても連れていって。私はもう歩けない」。悲鳴に近い声で晋司に訴えていた。私は熱は醒めていたが疲れた頭で、あの食事を与えられず死んで行った満州からのおばあさんのようにハナが死んで行くのかと身の毛がよだってきた。 晋司は「心配するな。男が三人もいるのだから集団からはづれても最後までいっしよに歩こう」とハナを励ました。晋司のこの一言は林家の気持ちを一つにした。 「ぼくたちも背負うよ」。兄たちも答えていた。 翌日は、朝からハナを晋司がおぶった。兄達が晋司のルックを持った。洋武は午前中は熱がなく疲れた足ではあったが歩きつづけた。和雄もハナを背負った。 前の日に熱が出た時刻が恐ろしかった。マラリヤには毎日熱がでるのと一日おきに出るものとがあった。一日おきに出ることを期待したが、その日の午後激しい震えを感じた。「ああっ!マラリヤだ」。洋武は毎日熱のでるマラリヤにかかったことを実感した。 確実に熱は上がってきた。熱が出てきたが洋武はもう誰にもかまってはもらえなかった。少しでも横になりたかった。しかし、横になれば取り残されることははっきりしていた。洋武は知恵を出し、必死に先に向かって走った。 「元気じゃないか」という声もあった。しかし、集団の隊列から離れて五〇メートルほど先に行くとそこでバタンと倒れて休んだ。隊列が近づいてくるとまた立ち上がって、走った。はじめはそうして進んだが、二、三回目にはもうたちあがれなかった。晋司はその私に向けて杖で激しくたたき「洋武おきろ。置いて行かれたらそのままだぞ」と叫んだ。ハナは父の背中から「そのままでは死んじまうよ」と激しく恐ろしい顔で叱った。洋武にとってその時のハナの悲痛の顔を忘れない。二時間の地獄は続いた。 熱が出て三日目だった。乗里(りつり)という街にはいった。そこは少し大きな町だった。同時に、日本人の避難民を救済するセンターみたいなものがあった。朝鮮の保安隊やソ連軍の公認ではなかったがトラックの斡旋をしていた。相当な運賃を出さなければならなかったし、運賃はまだお金をもっている人から借りて支払われた。わが家も借金をした組だった。それでも順安組は全員トラックに乗ることができた。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2008-8-14 7:23 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
戦中戦後、少年の記憶 北朝鮮の難民だった頃 ・40 (林ひろたけ) ぼく、このままでは死んでしまうよ。 栗里をでてしばらくたったところだった。トラックが止められた。保安隊の臨検だった。「みんな見せろ」。保安隊は子供のルックの中までさらっていた。そして金目の物を遠慮なく取り上げていた。ときどき女の人の悲鳴があがった。「それは形見です」とか「命に代えてください」など声が広がった。そのたびに保安隊は威嚇の空砲を撃った。何度も威嚇射撃で脅かされたのでその頃には、子供の私たちでも空砲と実弾との区別を音だけで聞き分けることができた。 晋司のルックが開かれた。ルックは川を渡った時にぬれたあと少し変形していた。保安隊はそれを見逃さなかった。ルックの底がナイフで切られるとそこから厚手の紙の束が出てきた。紙の束が濡れて膨れてしまっていた。数人の保安隊たちが顔を寄せて紙の束を見ていた。朝鮮語で話した後、「なにか。これは土地の権利書じゃないか。帝国主義者は、お前たちは土地まで日本に待ちかえるのか」。 土地の権利書が十数町歩もあることがわかると若い保安隊員たちはいっそう激昂した。銃架で晋司は激しくなぐられた。晋司は道路の上に靴をはいたまま正座で座らせられていた。隊員達が交代で殴りつけていたが、晋司は殴られるままにたえていた。洋武は砂利道路にエビのように転がり土に頭をつけて晋司の側に横たわっていた。やがて、その権利書に火がつけられた。保安隊員は朝鮮語でなにかわめきながら権利書を焼いて歓声をあげた。その時、私は初めて父の涙を見た。 父晋司は、大正元年長野県松本連隊に徴兵になり、そのまま満州で兵隊暮らしをした。南満州鉄道の守備を任務とする公主嶺独立守備隊の一員として、第一次世界大戦とシベリヤ出兵を経験した。優秀な兵士として兵隊として軍曹にさらに再応召で少尉にもなっていた。軍隊を除隊するとその退職金で朝鮮に土地を求め、植民地地主となった。大日本帝国のアジアへの侵略を、その末端の先兵として生涯を過ごしてきた。 「俺は裸一貫でここまできた」。しばしば酒を飲みながら子ども達に自慢して見せた。その生涯の最後の証拠が、土地の権利書であったに違いなかった。晋司は、生涯をかけて作り上げてきた財産が一瞬のうちに消えていった感じがしたのだろう。それまでの晋司は帝国陸軍少尉であり、涙を見せることはなかった。また、洋武が泣いた時にも涙を見せるとかえって激しく殴られた。その晋司が涙を流していた。 私は熱に苦しめられていた。道端に転がるように横になって、晋司が殴られ涙を出すのを、見てはいけないものを見ている思いで、じつと見ていた。 トラックから降ろされ略奪をうけた順安の集団は、時間が長引く原因を作った林家を非難の目で見ていた。苛立ちとざわめきがあった。 二時間はたっぶりとられてトラックが出発することになった。トラックに担ぎ上げられたとき、トラックの上で郵便局長だった小父さんが「お前の親父が悪いんだ」といきなり洋武を激しく殴った。なぜなぐられたのかはじめはわからなかった。殴られた痛みはなかった。そんなことよりもマラリヤ熱とたたかわなければならなかった。 トラックは一時間ほど走っていたが、洋武にとって熱の出る時間と重なっていた。 「どうせ載せるのだったらもっと南まで連れて行けばよいのに」という不満を残してトラックは私たちを降ろして立ち去っていった。 トラックを降りて、その日も一人で熱に耐えなければならなかった。ハナは晋司の背中から激しく洋武を叱りつけ、晋司は杖で前よりもいっそう激しく殴りつけていた。「もう死んだほうがいい」私は道端にころがったままそう思った。体も動かなかった。由美姉さんと順ちゃんが覗きこんできた。「武ちゃん元気だそう。もうすぐそこで休みになるんだ」。その一声でまたたちあがって走った。その日の熱が下がり始めていた。 次ぎの日も歩きつづけなければならなかった。体力がなくなって、あまり集団の前に走って進むことは出来なかった。次第に集団から遅れることが多くなった。そのたびに父晋司に杖で激しく殴られ、ハナから激しく叱られた。わが家の誰もが人の顔をみれば「キニーネはありませんか」とたづねていた。 市辺里という少し大きな部落が近づいてきたとき、「市辺里にはソ連兵がうろうろいるから避けるように」という連絡があった。そして私たちより先に行っている満州組が道に迷っていていっのまにかいっしょになっていた。満州組には辻村先生もいた。晋司もハナも洋武のマラリヤを訴えて「キニーネを探して欲しい」と頼んでいた。 マラリヤの熱は四日目を迎えていた。私は明日も熱がでることに恐怖心がはしっていた。その時、末永先生と一緒になった。マラリヤで苦しんでいることは集団のなかで知られていたのだろう。先生は立ったまま私の頭を抱いてくれた。 「たいへんのようね、でも辛抱するのよ。がまんしてもう三日ほどで三十八度線・開城だからね」。 当時「がんばって」という言葉はあまりなかったように思う。その代わり「辛抱して」とか「耐えて」とか「忍んでね」とか言う言葉が多かった。それはあの天皇の「忍びがたきを忍び、耐えがたきを耐え」という終戦の詔勅の影響ではなかっただろうか。私はその暖かな手に思わず「先生!キニーネという薬何とかならないの。もうぼく死んじゃうよ」と必死の思いで訴えた。わが家には相次ぐ略奪でもうお金はなかった。キニーネを買うお金もなかったし、キニーネそのものが手に入る当てもなかった。 末永先生はしばらく洋武の頭を抱いたままじっと考えていた。「なんとかしてみましょうね」と辻村先生に相談した。そして、辻村先生と末永先生は二人連れだって市辺里の街にはいっていった。とある医院を探しだし、末永先生がお金を出してキニーネを手に入れてくれた。「市辺里の町にはソ連兵が多いので町にはでかけるな」そんな指示がある中での決死のキニーネの購入だった。 その夜の泊まりは市辺里をはづれた河原だった。河原ゴミがいっぱい捨ててありほこりっぼい一角だった。しかし、病人と子どもたちはコンクリートの橋の下で早めに休むことができた。洋武がぐつすり眠り込んでいたときハナが起こしに来た。「キニーネよ。末永先生と辻村先生が見っけてくれたのよ。きっと効くはずと辻村先生がいっていたのよ」。そういいながらハナはろうそくの火がゆれるなか、一粒のキニーネになんどもお辞儀をしながら水とともに洋武に渡してくれた。 次ぎの日にマラリヤ熱は出なかった。洋武はその一粒のキニーネで熱がおさまった。私は死ないですんだ。命は助かった。洋武にとってのこの命の恩人の二人は、日本に帰ってから結婚したことをハナから聞かされた。その時、洋武は三〇才をこえていた。 |
| « 1 2 3 (4) 5 6 » | |
| スレッド表示 | 新しいものから | 前のトピック | 次のトピック | トップ |
| 投稿するにはまず登録を | |