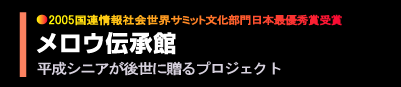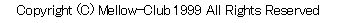メイン メイン 実録・個人の昭和史I(戦前・戦中・戦後直後) 実録・個人の昭和史I(戦前・戦中・戦後直後)
 戦中戦後、少年の記憶 北朝鮮の難民だった頃 (林ひろたけ) 戦中戦後、少年の記憶 北朝鮮の難民だった頃 (林ひろたけ) | 投稿するにはまず登録を |
| スレッド表示 | 新しいものから | 前のトピック | 次のトピック | 下へ |
| 投稿者 | スレッド |
|---|---|
| 編集者 | 投稿日時: 2008-8-29 9:09 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
戦中戦後、少年の記憶 北朝鮮の難民だった頃 ・51 (林ひろたけ) 引き揚げ列車の中で 学生同盟の人達・3 信越線篠ノ井駅で乗り換え、田中駅についたのは、十一月四日の昼十二時前だった。「これからはバスで二回乗り換える。汽車とは違って座れないかもしれない」と晋司がみんなに注意をした。バスはこんでいた。異様な格好をした一家がバスに乗り込むと激しい悪臭もしたのだろうか、他の乗客たちは、私たち一家を露骨にさけだした。大人たちは博多で軍服の支給があったが、子供にはなかった。だからとりわけ洋武の姿はひどかった。顔と頭にはおできとおできのあとだらけで異様な風貌だった。もう十一月というのに長ズボンは半分きれて半ズボンになっていた。上着も長袖のシャツの上に夏物のシャツを重ねてきていた。靴はなかった。おかしな形をしたぞうりだった。物乞いの集団というより他はなかった。同時に由美も洋武ももう立っていられなかった。ルックサックのままでバスの狭い通路に座り込んだ。 次の停留所で大きな籠を背負い、白いエプロンをし、もんぺ姿をした若いおばさんが乗りこんできた。この小母さんは 「よっこらしよ」 と荷物を置くと、私たち姉弟の顔を見て、すかさず「おやげねー。(かわいそうに)この子たちどうしたずら。ガリガリに痩せてしまっているでねえか。」 そういって立っていた晋司に話し掛けてきた。それは洋武にとって初めて聞く信州弁だった。晋司は他の乗客にも聞いてもらえるように、少し大きめの声で 「北朝鮮からルック一つで命からがら引き揚げてきたところです」と説明した。はじめ邪険に扱っていたそばにいた小父さんも私たちのためにすこしスペースを作ってくれた。バスの雰囲気が同情的になってきた。そのおばさんはもう一度、私たちを見なおしてぼろぼろと涙を流して泣いた。「まあ、おやげねいずら。そこのお兄ちゃん、いまにも死にそうに疲れてしまって」と洋武をさした。「今日の私の弁当だけどたべるのなら」そういって差し出した。私は弁当に手をださなかった。遠慮をしたというより実際つかれきってもう食べる意欲もなかった。 晋司が「ほんとうにありがとうございます。洋武、姉ちゃんといただいたら」と声をかけた。 その弁当箱はほうろう引きの白い弁当箱だった。そしてご飯も白米だった。おかすは何だったろうか、覚えていないがきちんとした弁当箱から食べたのは一年半ぶりだった。半分をたべて、あとは由美にわたした。若いそのおばさんの顔と白いエプロンともんぺ姿はいつまでも忘れられなかった。 「内地の人はなんて親切なんでしょう」ハナはくりかえし御礼を言った。 一時間ほどで望月についた。バスの停留所のまえに「引揚者のみなさんご苦労さまでした。どうぞ休憩につかってください」とかいたビラが張ってある家があった。道に沿って幅広い長い廊下のある家だった。望月は古くからひらけた中仙道の宿場町だった。東側から山が迫り、谷川の流れる水の音が聞こえてきた。 十一月の寒さが身にしみていた。わが家が帰る春日村の家はまだそれからバスの乗り変えねば ならなかった。バスを一時間も待たねばならなかった。 洋武は板の廊下に横になった。いつか、マラリヤで苦しんだとき 砂利道の道端に転げ込んだことを思い出していた。「生きていたんだ」と子供心に生への喜びが沸いてきた。 やがて、そこのエプロン姿のおばさんが出てきて「お帰りなさい。どちらからの引揚げでしょぅか。」などいいながらお茶をいれはじめた。そして晋司と話していた。晋司は「陸軍士官学校がここに疎開していた!」とおどろきの声をあげていた。 バスが春日村の終点についた時、もう日が暮れ始めていた。晋司の従兄弟の人が自転車で迎えに来ていた。「何時のバスになるかわからねえずら。バスの着くたびに迎えにきた」そう言うながら父との再会を喜んだ。 晋司の実家は、それからさらに三キロほどの登り坂を歩かなければならなかった。従兄弟の小父さんの自転車に洋武を前に由美を後ろにのせて押しながら上りの坂道を一家は歩きつづけた。 晋司の実家についた時はもう日はすっかり暮れていた。 晋司の兄の伯父さんとハナの姉の伯母さんが迎えていた。 「よう帰った。一時期は死んでしまったとあきらめていた」そう囲炉裏の側でつぶやくようにはなした。 両親は、並んで正座をして「一家でお世話になります」とていねいに頭を下げた。私たち兄弟も同じように並んで頭を下げた。伯父さんの家は二〇才過ぎの娘さんが一人の三人家族だった。 そこに六人の家族がいきなり飛び込んできてあきらかにとまどっていた。 十一月四日の夜だった。昭和二〇年(一九四五年)八月一五目の敗戦以来、一年三ケ月たっていた。順安を出たのは八月三〇日の朝だったから、六十五日の長い長い旅が終った。 信州の山村はもう秋というよりは冬の初めだった。由美も洋武もそれまでもたえず下痢に悩まされていた。しかし、伯父さんの家にたどり着いてからさらに激しい下痢に見舞われた。伯母さんが出してくれるささやかなご馳走がもう体に合わなくなっていた。「せっかくのご馳走もうけつけない」。ハナが悲しい顔をした。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2008-8-30 8:16 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
戦中戦後、少年の記憶 北朝鮮の難民だった頃 ・52 (林ひろたけ) 引き揚げ列車の中で 学生同盟の人達・4 春日村入片倉は、蓼科山の北麓に南北に長くのびた幅五百メートルほどの谷間の東側に張り付くような村だった。朝日があがると谷間の西側の山と家並みを照らした。南にはお椀を伏せたような蓼科山が見えた。真っ赤やまっ黄色に色づいた山が明るくなると東側の崖の麓にある林家にもおそい朝日が差してきた。晋司の生まれた家は、話に聞いているより大きかった。間口が一七間奥行きが六間もある、二階屋だった。白塗りの土蔵が表に二つ裏に一つ、三つもあった。その上、周りは白壁の土塀に囲まれて大きな門がありお城のような家だった。晋司の曾祖父が任侠の世界にも関わったという伝えがあったように土塀には銃眼があった。 「これが内地の秋よ」。ハナは由美と洋武を門の外に連れだし、子ども達に自分のことのように自慢した。ハナにとっても満州に嫁にいって以来、二〇数年ぶりの内地だった。真っ赤に色づいた山にまだら模様で黄色に色づいた山々は、朝鮮では見ることはなかった。 一日休んだだけで、六日には由美と洋武は晋司に連れられて春日村立国民学校にむかった。南にある蓼科山を背中にして、学校までの三キロの道のりは疲れた体にはつらかった。一年ぶりに学校に行くという感慨はなかった。 私たち姉弟は、学籍簿も通知表も持っていなかった。職員室の片隅にある校長先生の机の前で、晋司と校長先生とが私たちを何学年に転入するか言い合っていた。 晋司はそれぞれ進級を求めた。「特に洋武は男の子でもあるので落第させるのは可哀想だ」と強調した。 校長先生はほっそりとした凡帳面な感じの先生だった。順安の小島校長先生のように神経質の感じのする先生だった。「来年から学制がかわって新制中学まで義務教育になるので姉さんの方は六年生になるのが一番よいのです。今まで国民学校といっていたのを昔のように小学校と名前も変わります」。「弟さんも一年以内ならともかく、一年三ケ月も学校にいっていないので原級にとどまることにしてほしい」。 洋武はそばから口を出した。「僕ね。教育勅語も天皇…四代もみんな暗記できるよ」。校長先生は少しびっくりした顔をし、顎に手をやって少し考えていた。それから 「いま、民主主義になったから、あれは覚えなくてもよいのです」 と応えた。晋司は 「洋武の奴がいらんこというから校長先生は、やっぱりこの子は遅れている思ったらしい」 と後々までその一言を気にしていた。しかし、私にはそれが原因で原級にとどまったとは思えなかった。 結局、洋武は四年生、由美は六年生に原級どまりになった。教頭先生に連れられて教室に向かった。春日村国民学校の四年生は、まだ男女別々のクラスで男子組は五十名ほどだった。もう一クラス女性だけのクラスがあった。生まれて初めての大きな教室だった。担任の先生は病気で長期欠勤だった。教頭先生は 「今度、朝鮮から転校になった林君です」 と紹介した。誰かが 「先生、林は三名もいる。名前を教えてほしい」 といった。「入片倉ずら」 と部落の名前を言った。入片倉から林姓の子供が三人来ていて私は四人目だった。私は 「ひろたけさん」と呼ばれることになった。「教科書をあげますからきてください」 と先生につれられて、職員室の隣の図書室兼保健室のようなところに連れられて行った。そこには由美姉さんがもう来ていた。何種類かの教科書は、それぞれ大きな一枚の紙だった。女の先生が 「こうして折り目にしたがって折るのよ。教科書の印刷が間に合わないので印刷が出来しだいこうして配給になるの」 と洋武の分を折ってくれた。教科書は一冊になっておらず、ページが途中で切れていた。 それでも私たち姉弟にとって一年三ケ月ぶりの教科書だった。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2008-8-31 8:00 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
戦中戦後、少年の記憶 北朝鮮の難民だった頃 ・53 (林ひろたけ) 麹種を売り歩く・1
菊村家との連絡はあの時以来絶えていた。洋武が考えているほど大人達は菊村家のことを気にしていなかった。大人達は生きることに必死だった。NHKのラジオは訪ね人の時間で戦後のばらばらになった家族、親類、知人の連絡を求めていた。しかし林家には菊村家の行き先を訪ね人に投書するような余裕はなかった。 本家も急に家族が増えて食糧の確保がたいへんだった。山間地で水田は少なかった。本家も水田は三反しかなかった。供出もすんだ後で六人の家族が増えたため米の確保ができなかった。毎日のご飯には大根を刻み込んで混ぜご飯にした。夜遅くまで、伯母も母も大根を小さく刻んで朝飯の準備をしていた。 林一家は少しでも現金になる仕事に取りかかることになった。典雄は望月の中学校に転入して、残りの五年生を終えることになった。その通学途中、製材屋で内職の仕事を見つけてきて働くことになった。和雄も全くしたことのない、山仕事にくわわり、人夫賃をえていた。 五〇戸はどの入片倉の部落ははとんどが林姓を名のっていたが、二戸はど藤井を名のっている家があった。藤井さんのおじさんは、戦争が終わるまで林本家の小作人だった。正月の餅つきやしめ縄作りのさいには、一日中付きっきりで林本家の手伝いをしていた。そこの息子の昌弘さんは洋武と同級だった。学校に行くのも、学校のかえりも部落の男の子たちはいっしょだった。 入片倉の男の子供たちは、正月を道祖神のまつりの準備に余念がなかった。洋武も昌弘さんに誘われるままに道祖神のまつりに参加した。氏神の所有林(部落林) から落葉松材を切り出し茅葺きのピラミッド型の大きな小屋を部落の入り口に作った。その小屋を根城に獅子舞いをし、甘茶の接待をして正月を祝う行事だったが、その仲間にすんなり入り内地での生活をスタートした。 その昌弘さんが 「洋武さんも稼ぎ仕事にいかざ」 と誘ってくれた。 東京はじめ都市では、空襲で焼かれ、春日村のような山村からは復興のための木材が次々に切り出されていた。また、薪炭類も毎日トラックがきて荷台にあふれるように薪を積んで東京に向かっていた。通常なら伐採してから二五年から三〇年たって切り出す、くぬぎやこならの薪炭の山も二〇年前の成長不足のままで切り出されていた。山から、トラックの通る道路までは人手で薪や炭を運ばなければならなかった。山村の子供たちはこうした手間仕事に加わって、ちょっとした小遣いを得ていた。 父の晋司は、私のために裏山から白樺の木を切り出し子供用と少し大きめのそりを作った。初めは子供用のそりで 「割っ木」 (薪) 五束ほどを運んだが、慣れてくると大きめのそりで十束、二十束の 「割っ木」 の薪運びを手伝いをはじめた。山からトラックの荷揚げ場までの薪をそりで引き出す仕事に就いた。二キロ近くの道をだしても一束、二〇銭とか三〇銭の手間賃しか得られなかったが、現金のない林家にはそれで子供たちの教科書代になった。雪はあまり降る地帯ではないが、高冷地だったので一度降るとなかなか融けなかった。慣れるにしたがって一度に二〇束三〇束も運べるようになった。これには由美も参加するようになった。北朝鮮の冬になれていた由美や洋武にとって寒さはたえられたが、激しい労働で手や足にしもやけやあかぎができ、それがなにかにふれると飛び上がるはど痛かった。 正月には俊雄が長野の家に戻ってきた。俊雄は中学校から進学のために伯父の家に預けられていた。それだけに、伯父の家を自分の家のようにふるまった。洋武を連れて表や裏の土蔵を案内して俊雄の使い古した教科書や雑誌、岩波新書や文庫など積んであるところを教えた。俊雄の物はなぜかあちこちに散らばっていた。俊雄の使ったスケートやそりなども放置してあった。 俊雄も「学生の内職のことをアルバイトとドイツ語で言うんだよ。内職があるから早く帰らないといけない」とあわただしく京都に向かった。 俊雄の残した土蔵にあった古い書籍を、一年半近く活字に飢えていた林家の兄弟たちは、お互いに争うように読みふけった。冬のきびしい寒さの中で、山仕事ができないときはこたつに潜り込んで読みふけった。その多くは、戦争中の書籍で、軍国主義はなやかなりし時のものであったが、洋武にとっては心に残るものがあった。なかでも、昭和十年頃の少年倶楽部にあった西郷隆盛の話は、たいへん気に入っていた。誰かに話したくて仕方なかった。 学校では二月に学芸会があった。四年男子組は、担任が病気で長期欠勤だったので、授業などほとんどやられていなかったし、学芸会の準備など全くなかった。学芸会の五日ほど前に、四年女子組の担任の先生が、「このクラスから何も出し物がなくてよいのか。歌でもお話でもやってみないか。」 と男子クラスを集めて話したが、誰も名乗りを上げなかった。「僕やってもいいけど」と手を挙げた。あの西郷隆盛の話をみんなにしてみたいと思っていた。他に誰もいなかったので、先生も 「四年男子組も学芸会にでられてよかった」 と私を指名して帰っていった。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2008-9-1 8:00 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
戦中戦後、少年の記憶 北朝鮮の難民だった頃・54 (林ひろたけ) 麹種を売り歩く・2 話の中身は、西郷さんが鹿児島で浪人中に塾をやっていた。そこに弟子入りを希望する青年が、入門料の代わりに泥の付いたサツマイモをもって訪ねてきた。他の弟子たちが、『なんだ泥のついた芋じゃないか』と笑った。西郷さんはこれをとがめて 「泥の付いた芋であっても人の誠意を大切にしないといけない」 と諭したものだった。少年倶楽部の見開き二ページのお話には、講談形式に人に話せるようにと 「ここで声を大きくして」 とか 「ここはゆっくりかみしめるように」とかルビがふってあった。学芸会までの短い間私はくりかえし暗記をした。 学芸会は、全校生徒高等科まで八百人近く参加した。また、学校の近隣の父母たちも参加していた。そんなたくさんの人の前で話すことはなかったが、おぼえたての 「西郷さんのお話」 をせいいっぱいの声を張り上げて話した。学校にはマイクはない頃だったが、声は講堂には十分とどいた。話しが終わったとき講堂から大きな拍手とざわめきが広がった。それは今までの出し物の比ではなかった。「みんなが喜んでくれている」という実感が私の心に響いた。 それから、私は洋武さんではなく西郷さんと呼ばれることが多くなった。噂は学校だけでなく小さな村に広がっていった。村に一つしかない雑貨屋で鉛筆を一本買ったとき、そこの小母さんが「君は西郷さんのお話をした子ずら。おばさんも聞いていたよ。あれはよいお話しだったね。今日は鉛筆をもう一本おまけしておくよ」。私はいっぺんに鉛筆を二本も買うことはなかったので、なにかたいへんな大きな褒美をもらった思いがあった。学芸会が終わって三月になると、まだ雪の残っている田圃や畑で農作業をはじめる農夫の姿も見られるようになった。同じ部落での子供たちと学校帰りに、農作業をしていたおじさんに呼び止められた。「おめえ、西郷さんの話をした子か。」手ぬぐいで顔を拭いながら声をかけてきた。「はい」「学芸会でええ話しをしたつうが、ここでやってみねいか。」おじさんは鍬をおき、キセルを取り出して腰を下ろした。私は少し忘れかけたが、五分ほどの話しをして見せた。「ええ話しだ。おめいもこの話しのようにがんばるんだな。」キセルを二回ほどたたいた。 その年の春、学制が変わった。それまで国民学校高等科は、新制中学校になって義務制となった。国民学校は小学校になった。由美姉さんは、新制中学校一年生に、私は小学校五年生になることになった。そして男女共学になった。春休みのある日、ハナがどこからか、味噌麹種を仕入れてきた。「これを五円で売ると一袋につき五十銭もらえる。お前たち二人で売ってきてくれ。」 ハナは引揚げのとき朝鮮から担いできたルックサックを取り出し、姉と私のルックにありったけの麹種を入れて、肩掛けの布の鞄を用意してくれた。「当面売れる分は肩掛け鞄にいれて、もしなくなったらルックからだすのよ。五十銭のもうけでおまえたちの教科書代がでるんだからね」。 ハナは、小学生たちに物売りをさせることに、ためらいながら言い聞かせた。由美と私は、入片倉よりも南の立科山の方の集落に向けて麹種売りに出かけた。一軒一軒訪ねては、「麹種はいりませんか」と声をかける。多くの家庭のおばさん方は初めのうちは、キョトンとしているが、麹種売りだとわかると急に態度を変えた。 「おらあところは、塩の段取りしていて麹のことまで考えていなかったべえ。」多くのおばさんたちは、二袋三袋と買ってくれた。当時の春日村では、ほとんどの家庭は、味噌は自家製だった。 そして春に仕こみが始まっていた。味噌作りの原料の大豆は何とか山畑で収穫しても、塩がなかった。どこの家庭でも塩の入手が至難を極めていた。同時に、麹がなければ味噌にはならない。麹種も戦争で農村には品不足だった。 ある家庭で、おばさんが 「ねえ、父ちゃん四袋ほど買っておこうか。」 と奥にいるおじさんに声をかけた。おじさんは中腰になりながら、「五円は高い。すこしまけてくれねえか」 と冗談のように言った。おばさんは「引揚げで苦労している子供をいじめるでねえ。この子はあの西郷さんの話をした子だ。」おばさんは四袋を買って、乾し餅を添えて、「がんばりいや」と激励してくれた。学校から一里近く離れていた集落のおばさんがどうして「西郷さんの話」を知っていたかはわからない。しかし、西郷さんの話は、村中で評判になっていた。戦争直後の昭和二十二年の春には、どこも物不足だった。そして誰もが貧しかった。私の「西郷さんのお話」は、そうした村の状況にも合っていたのかもしれない。ハナが持ち込んだ味噌麹種は、ほとんど売り切れた。 「これでお前たちの教科書代がでそうだね」と喜んだ。村の人々は「よそ者」いじめなどせずにみんな私にはやさしかった。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2008-9-2 8:24 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
戦中戦後、少年の記憶 北朝鮮の難民だった頃 ・55 (林ひろたけ) 一家離散へ・1 林家は年があけてもなかなか落ちついた生活には戻れなかった。由美も洋武もよく病気をした。 理由のわからない高熱が二日ぐらいつづいた。ハナの激しい腹痛の発作は、春日村に帰ってきても続き、そのたびに洋武はお医者さんを三キロの道を呼びにいかされた。ハナは胆石と胃痙攣が持病のようになっていた。そのためお医者にはいつも支払いがたまっていて、とても子どもの医療費まで余裕はなかった。由美や洋武の病気は医者にかかることはほとんどなかった。国民健康保険はまだなかった。とくに洋武は奇妙な病気になっていた。痛みが胸やお腹や背中など体中はいまわるような病気だった。瞬間的に痛みに襲われることもあったが、数日苦しまなければならないときもあった。地元の人の話で落葉松(からまつ) のヤ二がよいということだった。ヤ二をとってきてあたためてやわらかくなったヤ二を新聞紙にのばし体中にはって痛みにたえていた。落葉松はちょうど二キロほどはなれた長者ケ原の落葉松林が、開拓でつぎつぎに切り倒されてその株にいっぱいヤ二がでていた。それをたんねんにあつめては体に張りつけていた。病気はかなり執拗だった。五年生と六年生になってもつづいた。年間で三〇日から四〇日も休む病弱な子供になっていた。ハナは「由美も洋武もあんな苦労を丸一年過ごしたから、体中おかしくなってしまったのね」と嘆いた。 洋武はよく寝小便をした。ソ連兵からおそわれ川に逃げ込んだり、高いところから飛び降りたりする夢をみたが、きまってそのたびに寝小便をしていた。ハナは寝小便をしても叱ることはなかった。「洋武は朝鮮ではこんなことはなかったのに。すっかり体質がかわってしまったのだろうか」 といいながら布団をほしていた。 引揚者になった晋司は、親戚から激しい非難が繰り返された。それは朝鮮で成功していたというのに何の財産も郷里に残さなかったという点だった。晋司はもともと長野に帰るつもりはなく朝鮮に骨を埋めるつもりだった。敗戦後も朝鮮にとどまることを考えていたほどだった。それだけに外地に出かけた成功者達がやるように、山(山林)も田畑も長野県には残していなかった。 伯父はそのことを愚痴のように繰り返したし、他の親類達は戦前の成功を羨望を持って見ていた人ほど激しく非難した。ハナは「私たちは天皇陛下が、骨を埋めるつもりでやれとおっしったのでその通りにしただけなのに」と憤慨した。同時に、「一度内地に帰って来ておけば親戚の人たちの様子も分かったのに。兵隊さんにはそんな考えはなかったのだから」と晋司への皮肉混じりに憤懣をぶちまけた。 朝鮮での唯一の財産は朝鮮でかけていた生命保険金が満期になって戻ってきたことだった。インフレが激しくなっていたが八千円の保険金は大きなお金だった。引き揚げ途中に大同江の渡し船にのったり、トラックに乗ったりしたときの借金をそれぞれの人たちに送金をしていた。「昔なら八千円といえば一財産だったのに。今では一ケ月の生活費ね。戦争はいやね」。インフレの激しさをハナは嘆いた。晋司の軍人恩給も停止になり恩給も当てにはできなかった。晋司の軍人恩給は、新兵以来満州や外地で軍人生活を送ったので、軍歴一五年にもかかわらず、二〇数年にも換算されて、終戦後にも 「どんなに貧乏になっても軍人恩給だけはあるから」 とたよりにしていた。しかし、敗戦で頼りにした軍人恩給もなくなっていた。 晋司は身の置き場がなかった。長野の田舎から再起をかけて親類をたよって昭和二二年の春には東京にでかけた。 ハナと本家の兄嫁のイソとは、実の姉妹だった。夫同士が兄弟でその妻同士が姉妹だったから問題は起こらないと考えられたが、実際は二人の仲は日に日に悪化していった。イソは戦後の農地改革で林家の田畑や山林が次々に縮小して気が動転していた。そこへ夫の弟たちが転げ込んできたというより、自分の妹一家が転げ込んできて林家の財産が見る見る減少していくことに気がかりだった。しかし、ハナにとって実の姉が林家の財産のことに気をとられ、貧困のどん底にあるハナ一家に冷たくすることに耐えられなかった。「これが実の姉のすることか」と時々激しく非難していた。二人の仲は近所でも評判になるほど悪化していった。 典雄は地元の中学校に一時編入したが、卒業すると川口市にある鋳物工場の丁稚小僧にだされた。典雄はその丁稚も一年でやめ自動車会社の旋盤工として働きながら東京物理学校、さらに東京理科大学と九年間夜学に通った。 ハナは、お医者で従兄弟の奥さんが病気で家政婦を求めているということを聞いて、由美と洋武を本家に預けたままで東京の従兄弟の家に家政婦として出かけた。それは半年にも及んだ。 その頃、洋武はノートの切れ端に詩や短歌を書き付けては、先生のところに持っていった。その中で先生が三重丸をして返してくれた短歌があった。 「今日もまた 母のいない淋しさを 月を眺めて時を忘れる」母との別生活には由美も洋武も寂しさが募った。 ハナは、本家の伯父と由美には手紙をよこしたが洋武にはくれなかった。それが洋武には不満だった。ハナは、後になって弁解するよう洋武にいった。「その家にはお前と同じ年の男の子がいた。学校から帰ると自分のお部屋に入って毎日勉強をしていた。わたしは一度、東京の子に負けないように勉強しましょう。と手紙に書いたが破って捨ててしまった。お前が、本家で大人顔負けに山仕事や百姓仕事をしているのに、勉強しろなどいってはいけないと思ってね」。 洋武が東大に進んだとき、その子も東大に在学していた。 和雄も病弱の体だったが、昭和二十三年には働きに東京にでていた。長野の田舎には、由美と洋武が残されていた。伯父さんの家は大きな家だったが、いつまでも世話になるわけにもゆかず、伯父の持っていた小さな薪小屋を改造して、家政婦の仕事から戻ってきたハナと三人で住むことになった。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2008-9-3 7:22 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
戦中戦後、少年の記憶 北朝鮮の難民だった頃 ・56 (林ひろたけ) 一家離散へ・2 晋司は、上京したあと親類の経営しているさつま芋から焼酎をつくるアルコール工場の工場長になっていた。しかし、アルコール好きの晋司にはこの仕事は向かなかった。半年もしないうちに、製品を飲んでしまうという理由で首になってしまっていた。その後、川崎市などでさまざまな仕事についたが、六〇歳を前にした晋司には、結局土方や日雇いの仕事しかなく、とても田舎に仕送りするような余裕はなかった。京大の電気工学科を卒業した俊雄は、東京の電気会社に就職していた。俊雄が就職して少しは楽になったかと思ったが給料は一人食べるのが精一杯だった。 ハナは、由美と洋武の三人の暮らしをささえるために下駄の行商をはじめた。小諸市にある問屋から下駄と鼻緒を仕入れ、背負い篭にいれて村の一軒一軒を訪ねて下駄を売り歩いた。下駄は当時の農村の必需品だった。下駄の台はしっかりしていても鼻緒のきれた下駄がどこの家にもあった。母は新しい鼻緒を買ってもらい、泥だらけの下駄に鼻緒をつけた。 ハナは不思議な明治の女性だった。学歴は高等小学校を出ただけだった。朝鮮にいるときも日本に戻ってきても、本など読む姿を、子供には見せたことはなかった。しかし、朝鮮からの逃避行のさなか「奥の細道」を暗唱して見せた。洋武が中学に進み、一次方程式の応用問題をⅩとかYとかいいながら解いているとき、そばからのぞきこんで「あら、そんなの鶴亀計算だったら簡単よ」といって正解をだしていた。ハナは、故事やらことわざにもくわしかった。下駄の行商は泥だらけの下駄に鼻緒をつけてささやかな利益を上げていた。泥だらけの下駄を投げ出され屈辱的な言葉も投げつけられながら、たいした利益のでない商売を続けた。ハナは、しばしば行商からかえってくると、その日にあった屈辱をしばらくじっと耐えているようだった。「韓信の股くぐり」(大望のある者は目前の屈辱に平気で耐えるものだ)の故事を漢文で引用しながら子どもらに話した。また「落ちぶれて袖に涙の かかるとき 人の心の 奥ぞ知らるる」という太平記にある短歌をよく口にした。朝鮮での豊かな生活と貧乏のどん底の生活の落差のなかで人生の悲哀を味わっていた。そして「戦争がなければね」と愚痴のようにつぶやいた。ハナは五〇歳を過ぎていた。 わずかのもうけではあったが、それでも三人の生計費と姉弟の学費を賄えるものになっていた。そのわずかの代金も貧しい農村ではたえず貸付けになっていた。由美と洋武は、その集金の手伝いをさせられた。夜遅くたずねても、思うようにお金は手にはいらなかった。母はそんなとき「いい。商売は最後の五歩(五%のこと)が儲けになるのよ。あなたがお金をあつめてこなければ商売をどんなにしても儲けにならないし、学校にもお金は持っていけないし、わが家は飢えて死ぬ以外ないのよ」とお金を集めてこない洋武を叱責した。年末には、他の家が除夜の鐘を家族で聞いているときも由美も洋武も下駄の鼻緒の集金に歩いた。 けっして豊かでない山あいの農村でも、わが家の引揚者としての貧しさは極端だった。 私たちの住んでいた小屋は十畳ぐらいの板張の一部屋で囲炉裏が真中にあるだけだった。家族は囲炉裏のまわりに折り重なるようにして寝た。食事も台はなくそのまま床上に茶碗をおいて食べることにしていた。勉強机もリンゴ箱だった。 屋根は板で葺いてあったから、乾燥が続いた後には板が反っていて、夕立が降ると必ず家中に雨漏りがした。雨漏りをを受け止めるたらいやどんぶりも不足した。「お母さん、お金がたまったらまず洗面器をたくさん買おうね」という冗談が冗談でないような深刻な貧乏だった。服は引揚者のために配給になる古着を着ていた。 ハナは戦後になっても天皇崇拝は変わらなかった。新聞で地方巡業にでかける天皇陛下の写真を見て 「なんともいたわしい」 などつぶやいた。そのハナは、「天皇陛下のいわれるとおにやって、貧乏になったのだから堂々としようね」 というのが口癖になった。しかし、子どもの洋武には 「天皇のおかげで貧乏になった」 と聞こえるようになっていた。東条英機もおかしいが天皇陛下はどうされるのだろう。それが洋武の政治への関心でもあった。 東条英機が東京裁判の結果、絞首刑になったときハナは涙を流した。「どうせアメリカに殺されるんだったら、杉山元帥のように自害されればよかったのに。生きて虜囚の恥辱を受けたのは東条さん自身だったのよ」。ハナにとって 「東条さん」 はなにか戦争をいっしょに戦った戦友のような響きを持っていた。 ハナは下駄の行商のほか、伯父がわけてくれた二反ほどの山畑を山研して食糧を確保することにした。由美も洋武も時間があれば農作業の手伝いをさせられていただけでなく、伯父の家の農作業の手伝いもさせられていた。伯父の家は小地主だった。戦後の農地改革のなかで水田のほとんどが農地解放になり、わずかに家の前にある三反ほどの水田が残されただけだった。従来農作業を手伝っていた小作人もいなくなっていた。私たちはその不足を子どもながら支えなければならなかった。 私たち姉弟は、小学校、中学校では修学旅行はもちろん、金のかかる遠足でも参加することはできなかった。小学校六年生になったとき、修学旅行があった。信州の山間地では、長野市の善光寺と新潟県の直江津にいって海を見ることが主な行き先だった。洋武は初めから旅行に行くことはあきらめていた。「僕は四十二日間も、海の上で過ごしたから海を見に行くことはない」 と強がりをいっていたが、旅行が迫りガリ版での案内書が生徒の間に配られはじめるとさすが落ち着かなくなっていた。明日が旅行の出発日という日の朝、先生から 「役場が修学旅行に行けない子に特別にお金を出してくれるそうだ。遠慮しなくてもよいからお母さんに聞いて旅行に行かせてもらいなさい」 といわれた。洋武は息を切らして三キロの山道を家までハナの返事を聞きに帰った。しばらく考えていたハナは、「私たちはお国のお役に立つと思って満州や朝鮮まで苦労しに行った。ここで扶助など受けては先祖様にすまないことだ」 といって役場からの修学旅行の援助を断った。学校への帰り道は下りだったが、重い足取りだった。 修学旅行も終わったころ、学校の成績はぐんぐん上がってきた。そのとき今まで自他共に一番と思いこんでいた同級生がくやしがって、「おまえなんか一年上に行けばいいんだ」 と激しくなじられた。「なに!天皇陛下のパンチみせてやろうか」。洋武はその同級生に向かっていきなり殴りつけた。パンチは彼の顔面にあたりひっくり返った。なぜ天皇陛下が出てきたのか洋武自身にもわからなかった。しかし、その一発でみんなは陰口もいわなくなった。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2008-9-4 7:59 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
戦中戦後、少年の記憶 北朝鮮の難民だった頃 ・57 (林ひろたけ) 第四章 戦争はもういやだよ・1 そんな貧しい生活の中でもたった一つの楽しみは、本を読むことだった。でも、その本は自由には手に入らなかった。 一年三カ月にわたる放浪生活のなかで書籍というものにはまったく手にしなかった。本家にあるすべての本を手にして読むようになった。それは俊雄が本家に残していった戦前の本が中心った。戦前の少年クラブや数冊の岩波文庫があるだけだったが、本というものは手当たり次第読みつづけた。学校の図書室にあった本は数は少なかったがほとんど読んでしまった。 そんななか、小学校五年生になった時、旧制の高等学校を卒業して大学にすすむため勉強をしいた白線浪人といわれていた先生の机のうえに「赤とんぼ」という子供むけの雑誌があった。 私はその「赤とんぼ」に魅せられた。とくに連載ものの「ビルマの竪琴」という物語に興味をひいた。ビルマで戦争が終った時、そこにいた兵隊さんたちがみんなで合唱し合いながら励ましあっていた話だった。先生に頼んで古い月遅れの号もふくめて貸してもらい学校で遅くまでかかって読んだ。行方不明になっていた水島上等兵がみんなとわかれてビルマにのこり、戦死した日本兵の骨を集めて供養するという長い手紙を読みきったとき何度も涙を流した。三十八度線を越える時、たくさんの日本人のお年よりや子どもの遺体が放置されていたことを思い出していた。「ぼくも水島上等兵のように、骨を拾いにいこうか」そう思うこともあった。 中学生になる頃、洋武の健康も回復にむかい、徒競走も一等賞をとるようになった。学校の成績も月毎に回復し中学一年生になったとき、級長になっていた。 学校の図書室には二百冊ぐらいしか本はなかったが、それも残らずよむことになった。中学一年になったとき、図書室で新しく購入した少年少女みすず文庫の一冊に「長征三千里」という本をみつけ一気に読んだ。それは自分が朝鮮の山野を七〇里も歩いたという思いがこの本を手にした最大の理由だった。中身は中国の解放闘争の毛沢東や朱徳の物語だった。中国人民が長い圧迫から解放されるためにどんなに苦労して戦ったのかという点も心をうたれた。そして中国共産党が、ソ連兵とちがって規律正しい人民軍軍隊だったことを朝鮮の収容所できいた「パーロ(八路軍=中国共産党軍)はよい」という噂を確認したようでうれしかった。 昭和二十四年(一九四九年)新中国が誕生したことを新聞の決して大きくない記事で読んだとき、洋武の心は複雑だった。毛沢東や朱徳の長い苦闘が実ったことに共感できたが、共産党の政府ができたことに釈然としなかった。「ソ連のような国にならなければいいのだが」。中学生の知識でも政治に関心をもたざるを得なかった。 旧中仙道の宿場町望月には洋武の家から、二里(八キロ)以上もあった。子供たちにとって望月は大都市だった。一年に二・三度歩いて出掛けることがあった。望月には小さな本屋が一軒あった。その本屋の軒先には「改造」とか「リーダースダイジュスト」とか雑誌が並んでいた。その雑誌を立ち読みしている中で「真相」という雑誌に魅かれるものがあった。薄い雑誌だったがグラビヤに「戦争に反対した人たち」の写真が並んでいた。徳田球一や志賀義雄など共産党の幹部の顔写真だった。「あの戦争に反対し、獄中一八年間、不屈にたたかった」という解説記事を丹念に立ち読みした。小遣いのない洋武は、雑誌を買って帰るわけにいかなかった。しかし、洋武はあの戦争に反対した人たちがいたという驚きがあった。 そして菊村の小父さんも生きていたらこうして写真にのるのだろうかそんなことを考えた。わが家は新聞を取っていなかった。ラジオもなかった。本家に行って新聞を読むしかなかったが、「子供の癖に新聞など読みたがるな」と伯父は嫌がった。しかし、私は新聞が好きだった。朝鮮でも国民学校四年生で一通り新聞を読み理解していた。 戦争中、さかんに戦争をあおっていた評論家がいた。その評論家は戦後、一転して左翼の論陣を張っていた。こうした人が嫌いだった。戦争中も左翼だったら許してやるんだが。しばしば洋武はそう思った。 ハナの従姉妹が結婚した相手は、戦争中に「転向」して共産党を辞めてしまっていた。そして右翼になったのではないかと噂されていた。ハナは「私は共産党はきらいだが、途中で節を変わるのも大嫌い」 といっていた。 東条英機首相がピストル自殺に失敗したり、大人達は「いいこといっていても、戦争が終れば、みんないっていたことと違ってしまっている。」大人たちへの不信感が身体中にひろがった。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2008-9-6 7:27 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
戦中戦後、少年の記憶 北朝鮮の難民だった頃 ・58 (林ひろたけ) 第五章 戦争はもういやだよ・2
図書室に「長崎の鐘」という本がはいることになっていた。長崎で原爆被害者の永井隆医学博士の書いた本だった。新聞やラジオで紹介されて前評判も高く、早く読みたかった。しかし、図書室にはその本はなかった。先生に聞いてもはっきりした返事がなかった。そのうちにその本が、先生の間を先に読みまわされていることを知った。「先生達ずるいぞ。生徒に先に読ませるべきだ。」私は図書係の先生にくってかかった。「わかった。昼間読んでおけ。先生達は家にもって帰るので読むのが遅いんだ。」 洋武は特別扱いで図書室で読むことになった。 妙に表紙の厚いその本を開いたとき、最初のページにあった写真にあっと驚きの声をあげた。黒焦げになった「少年」 の写真があった。ほとんど裸に近く、おチンチンのところが少し膨れていた少年の姿は、私が原爆被害者をみた初めての写真だった。その後原爆被害者の多くの写真を見たが、忘れることのできない写真だった。 本の内容は難しいところが多かった。半分も理解できなかった。それでも必死で読み上げた。 本はもうあちこち痛んでいた。質の悪い紙には、涙でにじんでいる頁もあった。「長崎の鐘」 は先生達が一生懸命読んでいることがわかった。原子爆弾の恐ろしさを知ったのは初めてだった。そして、放射能という得体の知れない物質に驚きをもった。朝鮮時代平壌の道立病院でレントゲン写真をとったこと思いだし、病気を治す道具がなぜ人間をこんなに不幸にするのだろうかとおもった。 「長崎の鐘」は一日で読み上げたが、半分以上を「マニラの悲劇」という文書が占めていた。 私は翌日その残りを読むことにした。「マニラの悲劇」にも写真があった。写真の説明のなかに「日本兵は幼児を銃剣で刺し殺した。大声をあげた母親を銃殺した」という文書があった。順安の収容所で満州から避難してきた母子がソ連兵に銃殺されたことを思い出した。それは「ソ連兵が日本人にやったことと同じことをフィリッピン人にしていたのだ。」と思い、かなり難解だった文書にひかれていった。「マニラの悲劇」は、日本軍がフィリッピンのマニラで残虐なことをした記録だった。中国の南京で大虐殺をした新聞記事もすでに出ていた。しかも、シンガポール占領の英雄だった山下泰文大将が、フィリッピンでの残虐行為で絞首刑になっていた。でも、順安のわが家にあった写真集で匪賊を討ち取った父晋司の写真を思いだし、終戦後のソ連兵の残虐を思いだし、「戦争はみんなあんなものだ。戦争になればよい人はいなくなる」と思った。 「マニラの悲劇」という文書が、どうして「長崎の鐘」に載っていたかわからなかった。その理由を知ったのは原水爆禁止運動に熱中していた十数年後だった。「長崎の鐘」があまりにも悲劇的なので原子爆弾を落とした反米感情が広がることを恐れたアメリカ軍が検閲の結果、「日本軍もひどいことをした」証拠のためにこの文書を、つけて発行を許可したものだった。経過はどうであれ、私にとって日本軍の残虐行為を知る最初の文書だった。そして、戦争への恐怖はいっそう強くなった。 引き続いて「この子を残して」という永井隆博士の本が図書室にはいった。永井博士と子供たち一家の愛情あふれる生活とやがて死を覚悟しないといけない博士の運命に心を動かされた。 「順ちゃんの小母さんはどうしているだろう。恵子さんや美代子さんはどうしているだろう。順ちゃんのおばあちゃんもキリスト教だった」。「長崎の鐘」はその後映画にもなったし、歌も繰り返し歌われた。貧しさのため映画など見ることができなかった私は繰り返し二つの本を読んだ。 中学生二年生になった時、「新しい憲法の話 文部省」「民主主義 文部省」という本が教科書として配られた。当時、教科書は有料だった。新学期には教科書代を捻出するのがわが家の一大事だった。しかし、「新しい憲法の話」はなぜか無料で配られた。この憲法の本を開いた時、戦車や軍艦が大きな釜の中に放り込まれ、下から電車やら自動車やらでてくるカットに新鮮な驚きを感じた。「武器がなくても心配はいりません。世界の人々となかよくできます」という解説がっいていた。社会科の先生がていねいに平和の大事さを教えていた。洋武は「新しい憲法の話」よりいっそう「民主主義」という教科書に魅力を感じて何回も読みかえした。「日本が民主主義の国だったら、無謀な戦争はおこらなかったでしょう」というフレーズを繰り返し確かめた。その頃、疎開をしていた子供たちが次々に東京など都会に戻っていった。お別れのさい、その子供たちと一言ノートにサインをして交換した。 洋武は、そのたびに「おれは行く 君も行かぬか一筋に 行く手を照らす 光求めて」と自作の短歌を書き印した。光が何であるか私にはわからなかった。しかし、戦争だけはいやだった。 戦争のない国こそが光であった。 由美は望月の高等学校に進んだ。由美はまわりの人達が「あそこの子が高等学校にいく」と貧乏の中、望月の高等学校に進んだことに驚きを隠さなかった。姉達の同級生で高校に進んだのは二割に満たなかった。 中学二年生の田植え休みがやってきた。当時の農村ではこどもたちは貴重な労働力だった。中学校は農繁期が始まるたびに田植え休みとか稲刈休みとか一週間程度の休みがあった。田圃のないわが家も本家の田植えをハナも由美も洋武も農作業の手伝いにいった。田植え準備(準備の)ために肥担ぎをし、牛をつかっての苗代かきのとき、牛の鼻面をもって田圃をコネ歩き、また田植えのさいも重要な労働力だった。 あすで田植え休みも終わりだという日曜日、ハナと洋武は本家の農作業の手伝いで昼の食事を待っていた。雨の多い田植え時期だったが、その日は晴天で夏の到来を感じさせる暑い日だった。 蓼科山には夏を思わせる雲がわいていた。わが家にはラジオはなかった。田植えの時期には二時間以上の昼寝の時間をとったが、昼休みをまえに、「のど自慢」 を聞こうと伯父の家の昼のラジオのスイッチをいれた。 しかし、 昼のニュースはあわただしかった。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2008-9-7 9:19 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
戦中戦後、少年の記憶 北朝鮮の難民だった頃・59 (林ひろたけ) 第六章 戦争はもういやだよ・3
「今朝早朝、北鮮軍は南北鮮境界線である三八度線にそった開城、春川付近と東部海岸地区において北鮮軍と韓国軍ととの間に戦闘が開始された。韓国政府は同日北鮮との間に全面的内戦が発生したと公表したが、同日朝、北鮮側平壌放送は韓国軍(韓国軍に)たいして正式に宣戦を布告した」。「北鮮軍は戦車を先頭に激しく攻勢をつづけており、先頭部隊は京城に肉薄し、京城に危機が迫っている模様」。当時のラジオニュースは、北朝鮮のことを北鮮といい、ソウルのことを京城と植民地時代の用語をそのまま使い報じていた。北朝鮮が三八度線全線で戦車を先頭に南朝鮮へ攻勢をかけており、また日本海海岸では艦船による攻撃も始まっていることも報じた。開城では、甕津(おうつ) 半島ではとか、議政府ではとか朝鮮で聞き慣れていた地名が次ぎつぎに出てきた。そこでは戦車戦が繰り返しおこなわれ、つぎつぎに北朝鮮軍の占領地域が広がっていることを伝えていた。「のど自慢」どころではなかった。集まっていた家族はそのニュースに釘づけになった。 「朝鮮で戦争がはじまった」。洋武は身震いがした。つぎの瞬間、三八度線をこえた戦車が、そのまま蓼科山の雲間をぬって、列をつくって殺到してくるかのような錯覚に陥っていた。それは順安で見たソ連軍の戦車の行列だった。洋武はまだ手も顔も洗わず泥だらけで土間に立っていた。 「いやだよ。もう戦争はいやだよ」。体を二つに折ってラジオにむかって叫ぶとともに声は泣き声にかわっていった。そしてわんわん泣きだしていた。自分の肌がどんな戦争も受けつけなかった。「この子ったら。中学生にもなるのに。泣くなって」 ハナはそういいながらラジオの音を大きくし、「そう戦争はもういや。どこの国でもどんな理由でも戦争はもういや」と相づちをうった。 九年前、真珠湾攻撃にわいた林家の姿とはまったくちがって、凍り付いたような雰囲気がラジオのまわりにひろがった。おそらくそれは日本中の国民がうけた衝撃でもあった。昭和二五年(一九五〇年)六月二五目の日曜日の正午のことだった。 以 上 |
| « 1 ... 3 4 5 (6) | |
| スレッド表示 | 新しいものから | 前のトピック | 次のトピック | トップ |
| 投稿するにはまず登録を | |