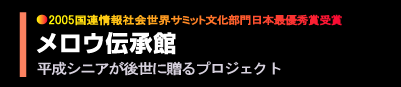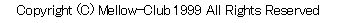メイン メイン 実録・個人の昭和史I(戦前・戦中・戦後直後) 実録・個人の昭和史I(戦前・戦中・戦後直後)
 捕虜と通訳 (小林 一雄) 捕虜と通訳 (小林 一雄) | 投稿するにはまず登録を |
| スレッド表示 | 新しいものから | 前のトピック | 次のトピック | 下へ |
| 投稿者 | スレッド |
|---|---|
| 編集者 | 投稿日時: 2007-11-18 8:26 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
捕虜と通訳 (小林 一雄) (11) くそ度胸で通訳奮闘す・その3 ある時、病棟に行った。ある捕虜はベッドに体を起こして読書、ある者は患部を押さえうなっている。彼らに「どこが痛むのか?」と声をかけ、雑談して時を過ごすこともあった。そうしていると「あなたと話しておれば痛みを忘れるよ」と笑顔をみせる彼らだった。 オランダ兵(DUTCH)捕虜(本国兵ではなく東南アジアの植民地兵)のバラック棟を巡回した時など、いっそう哀れを感じたこと思い出す。私たちと同じアジア人、同じような顔つき、おとなしい性格だっただけに、とくにそう感じたのかも知れない。 そのオランダ兵たちは、便所に行く時に必ず、長さ1メートルぐらいの縄を持って行く。まさか首を吊《つ》ったりはしないだろうな(?)と疑問に思ったものだ。それは用便後にふくために使うことがわかったが、民族が違うと、同じアジアに住む人びとでもこうも習慣が違うのか、とまるで新しい発見でもしたかのように驚き、民族文化の差を見せつけられて本当にビックリした。同時に他国の人びとのことをまったく知らない私を恥じる心もチョツピリ湧《わ》いた。 オランダ軍捕虜約六十人には、本国の将校一人と植民地の東南アジア系の准尉《じゅんい=将校と下士官の間に位置する武官》一人が指揮官としていた。本国将校は巧みに日本語を話し、理解できた。もちろん英語もベラベラ。アメリカ軍将兵との連絡も彼が当たっていた。日本軍とくに陸軍に三か国語を理解し、話し、書く将校が果たして何人いたのだろう? もっとも、この収容所のアメリカ軍捕虜でも三か国語を理解できる人間は一人もいなかった。 そのアメリカ軍とオランダ軍の兵士たちとの直接、つき合う風景は見たことがなった。英語をオランダ兵が理解できず、アメリカ兵もオランダ語やその植民地語を理解できなかったせいかも知れない。それにもまして、異民族文化、習慣の違いが大きすぎて、これが両国捕虜同士の接触のブレーキになっていたのかも知れない。 アメリカ軍捕虜の専任軍医はキャンベル軍医大尉(GEORGE・W・CAMPBELL)だったが、彼とはよく気が合った。 家族のこと、学生時代のことなどをよく話した。大きな庭っきの家で撮った彼の妻子の写真を見せながらよく話した。「人間はどんな場所でも同じ生命。医者の私は、その生命を大切にして元気に生活させるための使命をもって戦場に臨んだ。捕虜になっても、この使命は当然、やり通す義務がある。これが本当の人間なんだ」という彼の持論には敬服した。しかも日本の文化にも造詣《ぞうけい=学問や技芸に通じていること》が深く感心したものだ。菊を賞(め)ず日本人、武士道を重んじる伝統、義理と人情を優先させる国民性…こんなことばがボンボンと飛び出し、 こんなヤリトリをしながら、小声でマンボを口ずさみながらも彼らは靴直しの手を休めることはない。そんな中で、国に残した妻子をなつかしむことばが必ず一度は出た。「ワイフは美人じゃないが働き者で、子供の世話を人一倍する女だ。必ず生きて帰ると信じており、私が帰る時には化粧して出迎えるという手紙が来た」といって微笑んだ。 「豊かな暮らしではないが、日本人よりもよい暮らしをしている。第一、家も、家具も大きいし、みんな余裕があるよ。でも日本人は真面目だから好きだよ」ともいっていた。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2007-11-19 7:40 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
捕虜と通訳 (小林 一雄) (12) くそ度胸で通訳奮闘す・その4
厨房《ちゅうぼう=調理場》棟にも出入りするようになった。炊事班長のエドワード・コイル軍曹 (EDWARD・COYLE) ら十人近くの炊事兵が、所外の労役作業を免除され専任でアメリカ兵捕虜全員の食事の世話をしていた。 コイル軍曹ら炊事班は、日用、食料品などを買いに時々、通訳つきで町に出る。店の人との会話で覚えた片言の日本語を使って買い物をするので、少なくとも他の一般捕虜よりは日本語を話すことができた。分所の管理・運営担当の峰本善成・軍曹 (奈良市東大路町八二四) からも日本語を教えてもらい、かなりうまく話していた。 彼らと親しくなり、食事に誘われ、よく厨房棟へ通った。しかし彼らも私との雑談の中で何か新しい情報を知ろうと必死だったように思えた。もちろん、素知らぬ顔で私はしゃべり、聞き、笑って過ごしたものだ。時々、窓越しにチラリ、チラリと事務所のある管理棟の方を見て、日本人のようすをうかがっていた態度をいま思い出す。その表情は絶えず、日本軍のようすを知り、自分らのこんごの運命を占う資料にしようと考えていたに違いない。しかし、表面は、ひょうきんで、とくに私にはどんな些細《ささい》なことでも話し、訴え、逆に聞く態度だった。友好的だった。日米の女性の違いについてもよく冗談をいって笑わせたものだ。 炊事班のナンバー2、エンライト伍長 (ENLIGHT) ともよく話した。「平和になったら、あなたもアメリカに来ていっしょに楽しく家族同士で話し合いたいですね」「平和になったらね。いまはお互い戦争中で敵と味方に分かれているんだから、そんな考えをしようにも無理だ。でも平和になったらぜひそうしたいね」当時、勝者の立場で話をしていたので、弱者の彼らへの思いやりは私自身、欠けていたかも知れない。 "平和″ということばを使ったエンライト伍長の胸の内を考えると、虜(とりこ)となり不自由な生活を強いられている立場にある者にとって、平和をいかに切望し、一刻も早く、自由で、伸び伸びした暮らしにもどりたいか、当然、出てくる、切実なことばだったに違いない。 町に買い出しに行った時、一般の人は彼らに冷い眼が多かった。しかし行きつけの店では必ず「こんにちは、ママさん」とていねいに、明るいあいさつから始まった。最初はびっくりしていた店の人たちも、慣れるにつれて「元気ですか?」「今日は何を買ってくれますか?」そして 「キャンプにいる人にもよろしくね」と会話を交わし、ひとときか〝友情〟がお互いの間に湧《わ》き、異常な時期の、短い〝国際交流″が、大阪・泉州の片田舎で行われていた。いま思い出しても、あの風景はなつかしい。収容所暮らしの彼ら捕虜にとって、厳しい監視の下、明日の生命を握られている立場からすれば、所内での日本人、とくに私のような若僧で、一見、なんでもしゃべり、交際してくれる人間、所外で付き合う日本人の誰彼《だれかれ》なく、貴重な情報源であり、一方では気をまざらわせてくれる、よき人間だったのだろう。 確かに、彼ら捕虜に対する日本の衛兵、監視兵はいつもきびしい態度、謹厳実直《きんげんじっちょく=慎み深く厳格で誠実》な態度で臨んでいた。バラック棟のアメリカ当番兵が 「異常ありません」ということばを言い遅れると、すかさず 「もっとテキパキと手早く報告せよ」 といったぐあい。ちょっとでも棟内の寝具や書籍類が散らばっていると、厳重な注意を与える。通訳の私がそのまま、正直に伝えるのだが、私は必ず「集団生活を楽しく、規律あるものにするために必要なことだから、お互い、よく理解して暮らしていこう」とつけ加えることを忘れなかった。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2007-11-20 8:47 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
捕虜と通訳 (小林 一雄) (13) くそ度胸で通訳奮闘す・その5
慣れてきて、捕虜みんなのロから漏 れてくることばーそれは「捕虜はいつ殺されるかわからないので、毎日が恐しい」ということだった。キャンベル軍医大尉も「捕虜は執行期のわからない死刑囚のようなものだ」といったことがあるが、このことばは、全捕虜に共通することばだったように思う。これを知った私は、捕虜への対応に細心の気配りが必要であることを痛感した。 所内勤務に慣れ親しんでくるにつれ、こんな捕虜の心情を知ったことは、かけがえのない収穫だったと、いまつくづく思う。弱者の立場に立った人間は、強者の意のままに動かざるをえない。人間という集団の宿命がこの収容所に凝縮されていると思った。公にできない小さな苦情を聞くことも、弱者への配慮の一つという、別の視点の通訳業の意識も湧《わ》いてきた。 きれいな星のきらめく夜空を仰ぎながら、鉄条網に囲まれた粗末なバラック棟からもれる薄明りを横目に歩いていると、ここだけが〝安住の地″である寝静まった捕虜たちの「きょう一日」に命を賭《か》ける姿が、妙に哀れに感じられた。もちろん、当時、全般的には「いや、敵兵なんだ。そんな甘さを見せてはならない」という雰囲気だったが。 とはいえ、星空の夜、バラック棟のこもれ火、暗い収容所の一角に唯一灯、まるで輝くような電灯の明りの下でコツコツと靴や古びた軍服を修理する笑顔の二人の捕虜・・・遠くからこんな風景を眺めていると、戦火の真っ最中、多数の敵兵を武装した日本軍が管理する場が、不思議と〝平和な夜景″のように見えてきた。だから余計に〝敵〃〝味方〃の感情を越えて〝人間〃として同じステージで接する気分が、私の心にグッと湧いてくる。"きびしい現実〟を逆に情けなく感じさせた。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2007-11-21 9:14 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
捕虜と通訳 (小林 一雄) (14) 第四章
私を支えた〝収容所語学校″その1 この捕虜収容所に勤務することになった原因の一つは、せっかくマスターしかけた英語を実際に使って英語国民のナマの文化の一端に触れることができれば、ということだった。だから、慣れるにつれて、その欲望は強まり、生来のオッチョコチョイ性も手伝って、暇さえあれば、所内をうろつき、捕虜たちと話し、ナマの発音を吸収しょうとつとめた。 私のこうした欲望が彼らに伝わったのか、勤務二か月ともなるころから、私の姿を見ると「日本語を教えて下さい」という。ただ「代りに日常英語のうちコバヤシさんが知らないことを話してあげよう。しかし私らは捕虜としての立場にあるので、日常会話を単に話すだけです。この私たちのいう意味を素直に受けてください」彼らは一見、大ざっぱで、明るく振舞っているように見えても、常に自分の立場を冷静にみつめ、われわれ日本人に対応していた。 所内をうろつき、捕虜と会話をすることが職務の一つとして日課のようになっていったが、これが私にとっては日常英会話とアメリカの庶民文化を教えてもらう、またとない機会となっていった。捕虜たちも日本語を私から習い、日本の庶民の風習・文化の一端を知るきっかけとなったことは事実だ。私はこうした所内での彼我《ひが=相手と自分》の関係を「収容所学校」と勝手に名づけ、職務を兼ねて積極的に彼らに接していった。 ある日、私は町の本屋で一冊の日英語読本を買った。外国人向けに英訳譜を入れた日本語と英語の日常会話読本で、彼らに対する私のテキストに使った。もちろん、この本は彼らにプレゼントし、暇なときに教える時間には彼らがこれをもとに、私にいろいろと質問し、正しい日本語を覚えていった。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2007-11-22 6:48 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
捕虜と通訳 (小林 一雄) (15) 私を支えた〝収容所語学校″その2
〝収容所学校″は特定の時間と場所で開かれたのではない。ちょっとでも暇があれば、立ち話のかっこうでも行った。生活棟でも、病棟でも、厨房《ちゅうぼう》棟でも、天気のよい日はグラウンドに座って、ある時は将校と、、ある時は下士官や兵士らと…という風に、一対一あるいは一対複数で行った。相手によって会話のキッカケや仕方はマチマチだった。炊事班のメンバーと話すときには「これはどうやって味つけしたのか?」「日本人の舌には少し甘過ぎる」と言った風に。 病棟では「傷の痛みぐあいはどうか?」「この傷はいつ、どうしてできたのか?」「病気の時には静かに横たわっているのが一番。早くよくなってみんなといっしょに暮らせるようにならなければダメだよ」 ケース・バイ・ケースの切り口でしゃべり、相手の発音を覚えていった。 「サノバピッチ」-ある時、一兵士と話していると、彼はとつぜん、こう発音し、ぐっとにらみ返したように、私には思えた。「何? サノバピッチとは何という意味?」「おっと失礼、あれは悪いスラングで、正しい英語ではない。たまたま、昨日、所外の作業中に日本人の監督から理由もないのに怒鳴られたのを思い出し、余りにも腹が立ったので、つい口に出した。すみません」「一体、何という意味か、教えてほしい。私にはチンプン、カンプン、意味がわからない」「つまり、こんちくしょうという意味。サン・オブ・ア・ピッチ=SON (息子)・OF・A・BITCH(雌犬)=」「ああ、そういうことなのか」〝サノバピッチ″と彼らは発音するが、二人とも顔を見合わせて大笑い。私は初めて知った悪いことばの、この英語を繰り返したが、このことばの真の意味は辞書を引いても出ていない。相手を見下げ、罵倒《ばとう=激しくののしる》する卑猥《ひわい=下品でけがらわしい》なことばである。日常英会話は、直接、彼らと接してみないと、容易に身につかないと、しみじみ考えさせられたものだ。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2007-12-2 10:02 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
捕虜と通訳 (小林 一雄) (16) 私を支えた〝収容所語学校″その3
「コバヤシさん、あなたのことばには真実味がある。マナーも紳士的で、つねにわれわれの立場で応待してくれる。他の通訳に比べことばはまだ、うまくないが、人間の味があり、大好きだ」こういうフォーブス大尉(ALFRED・W・FOBES)からもよく英会話を習った。 「どこの国のことばも、主語と述語、形容詞の並べ方は違っていても、人間の造語だから、心を知れば.すぐ覚えられると信じている」というのが彼の主張であり、持論だった。私もその言い分に賛成、家のこと、習慣のこと、学園生活のことなど、よく話し、お互いに双方の国語を教え合い、習い合ったものだ。 ガルブレイス大尉は、つねに小さなノートを持ち歩き、私が教えた日本語を正しくノートに記入、発音まで書き込んでいた。また私に教える英語も、そのつどノートに書き、後日、同じことばが出てきたときなど「一回教えたのに、まだ十分理解していない。もっと努力しなさい」とたしなめてくれるほどだった。これでは英語を習う私も、うかうかしておれない。彼の厳しい教え方に敬服した。 全般に捕虜のうち、将校はさすがに発音がきれいで、聞きとり易く、私のいう日本語の英訳の理解の仕方も早かった。一般兵士のなかには、なかなか理解できないものもおり、彼らの話す英語も、私にはすぐ理解できないことがあった。それでも〝耳学問″で、日とともに慣れ、しだいに理解もできるようになった。会話と暮らしの関係を身をもって知った、貴重な所内生活の世界だけでも随分あることを知って驚いたが、彼らと生活をしたことのない日本人の話す英語が、いかに彼らに通用しないか、ということも知らされ、驚いた。 もう一つ勉強できたのは、聞きかじりのまま、例えばGIスラング (軍隊用語) を自己流に解釈してしゃべることの恐さということだった。英語は、意外に語呂のよい発音が〝強調″のために使われるケースが多く、これを勝手に流用して話すと、ある場合には相手を傷つけ、ある時には、英語を非常に理解していると受け取られ、まくし立てられることがある。例え〝耳学問″でも、こと会話に関しては、そのことばの意味をよく理解してから、使うことの必要さを痛感させられた。 私にとって〝収容所学校″の経験は、学校ですばらしい英国人の英語教授に習った英語では決して身につけることのできなかったナマの英会話の修得のむづかしさを知ったこと。同時に、まがりなりにも日常英会話をこうした接触によって身につけることができた、喜びを知らせてくれたことだった。いま、あの収容所で話し合い、教え合った多くの捕虜たち、戦後のよき友となった人びとの顔、笑顔、憂え顔が目の前に髣髴 (ほうふつ) とする。なつかしい。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2007-12-3 7:56 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
捕虜と通訳 (小林 一雄) (17) 私を支えた〝収容所語学校″その4
そのうちに捕虜将校たちは、私を〝ファイヤー・ボール(FIR!BALL)のニックネームで呼びはじめた。なぜこう名づけたのか彼らに聞いても教えてくれず、私はただニコニコと応待する以外、対応の仕方がなかった。今でもファイヤー・ボールの本当の意味は判りかねている。 いずれにしろ、この収容所勤務で私の学校英語はそのスタートから崩れ去り、新たな英会話を習得する再出発となった。ガルブレイス大尉ら将校たちも暇をみて、近づく私に初歩の発音から指摘してくれた。もちろん、私も日本語の発音や意味を、イロハ…から教えたものだ ”交換教授″は熱が入った。 ブロードウォーター中尉もよく日本語を勉強した、美しい金髪の若い将校で、とくに日本人に親しみを持ち、私たちにも親しみを感じさせるタイプだった。彼の話によれば、彼の家族は戦前、松岡洋右さんと親交があったという。(国際連盟脱退の時、松岡氏は全権大使だった)。その彼は日本側との連絡としてよい印象を与え、所内の管理についても常に円滑に処理できた〝有能な人材″だった。彼もガルブレイス大尉と同じように私とはとくに仲の良かった将校であった。日本語と〝英語″のチャンボンでよく話し合った、忘れ得ぬ一人である。 ともあれ、旧専門学校時代の英文法、単語力は相当なつもりだったのに、この収容所で味わった現実は無残だった。でもここでの〝再教育″は、毎日が楽しく、驚くほど旦く進歩したと確信している。辞書にもない、学校でも習ったことのない単語や文章を毎日、聞かされ、教えてもらってそれに慣れ、ヒヤリングと発音がスムーズにいくようになれば、英会話に自信がつく。いま、日本での外国語教育への反省が叫ばれているが、実用外国語の教育方法は真剣に、かつ根本的に考え直すべきだと訴えたい。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2007-12-4 7:39 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
捕虜と通訳 (小林 一雄) (18) 第五章
捕虜たちと泣き笑いのカケひき―虚々実々《きょきょじつじつ=計略や秘術を尽くして戦う》の所内・その1 収容所で、顔なじみとなり、親しく話し合う仲になったとはいえ、きびしい太平洋戦争の最中、し烈な戦火を交えながら、食うか、食われるか、生死を決する戦争を繰り広げている敵と味方。捕虜と日本軍という立場で、すべてに一線が画されている。当然、監視下に置かれている彼らには、表と裏の言動があるハズ。保護し、監視する立場の日本軍側もこれを承知し、これを前提に作戦を練り、対応している。彼我のかけ引きが四六時中、陰に陽に行われていたことは否めない。それは、ある場合には笑いを巻き起こし、別のケースでは泣くに泣けない悲壮感さえただよう雰囲気をかもし出した。 そんな泣き笑いのかけ引きのなかでも、もっとも大きな原因となったのは、ことば、会話によるものだった。 一般捕虜の兵士たちは所外に作業動員される。現場の作業場では、日本人の現場工員といっしょに、あるいはその監督の下に作業する。日本人は彼らに当然、命令形で「作業せよ」「タバコを出せ」「休め」そして怠ける捕虜には「ドあほう」と大きな怒声があびせられる。日本語を十分に理解できない彼らは、そのことばを正しい言い方だと誤解したまま、意味もわからないで日本人と話す時に使う者が多かった。 ある時、こんな経験をした。一兵士が宿舎前で私に会うなり「タバコを出せ」と日本語を使い命令形でいうではないか。「君、そんな言い方はないよ。他人からモノをもらう場合には、…してくれませんか、とていねいに言い給え」私もさすがにムッときて怒鳴った。「毎日、作業現場ではこんな日本語を日本人が使っている。正しい日本語だと思っていたのに」とその兵士はむくれ顔だ。「英語もそうだが、日本語もていねいにいうことばと、命令調でいう場合のちがいがあるんだ。君の理解の仕方が間違っている。改めないと、これから日本人と話す場合、大変なことになるよ」と、ていねいな言い方を教え、タバコをプレゼントした。 後で他の兵士から聞いた話だが、この兵士、実は日本語の命令形とていねいなことばの使い分けは知っていたそうだ。しかし、私の評判が彼らの間で意外によく、他の日本人通訳よりも親しみがある。わざとそうしている裏には、われわれに近づいて情報をとるなど、何かあるのではないか (?)と、かんぐって、一度怒らせれば本音が出るIとふんで、わざとやったというのだ。真偽のほどはさておき、これを聞いて、あきれるやら、悲しいやら…私はそんなことは考えたこともなかっただけに、一瞬、恐い感じがした。同時に捕虜収容所内の彼らの笑い、怒りが本当にそうなのか、どうか、疑ってかからなければならないと思うと、悲しかった。そうはいっても、全部がそうだとは信じたくなかった。事実、私の周囲にいたアメリカ将兵の多くは、裸のつき合い、真実の心でつき合っていたと、いまでも確信している。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2007-12-5 8:02 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
捕虜と通訳 (小林 一雄) (19) 捕虜たちと泣き笑いのカケひき―虚々実々の所内・その2 もっとも、本当に耳で日本語を聞き、覚え、使う〝場″とことばの真の〝意味″を知らずに、聞きかじりの日本語を、そのまま使う兵士も多く、さまざまな波紋を描いた。私自身も、初めのころは、彼らがよく使う「サノバピッチ」 (SON・OF・A・BITCH) ということばの真の意味を理解せずに使ったことがあった。ところが、私はこのことばの発音を、聞いた通りに「サルバベッチン」といった。ある兵士は首をかしげ、ある兵士からは失笑を買った。そんななかでも「通訳なんだから、わざとあんな発音をしてわれわれの気を惹《ひ》き、情報をとろうとしているのかも知れない」と思っていた捕虜がいる-という〝うわさ話″を聞いたときには驚き、悲しかった。 〝かけ引き″ではないが、「ガッデム」 (GOD・DAMN=この野郎め) ということばも、悪ふざけとか、立腹した時などに強調の意味でよく使われる。「ユー・アー・ガッデム・ライト」(YOU・ARE・GOD・DAMN・RIGHT=いやあ、その通りだ)、「ヘロ・バァ・グッド」 (HELL・OF・A・GOOD (そいつは、ええなあ) というように。 RIGHTやGOODを強調し、リズム感のよい語呂として慣用語のような役割を果たすことばである。英語の場合なら、親しい間柄で使えば本当に理解し合えることばだが、聞きかじりの単語をそのまま正しいと勘違いして使うと、えらいことになる。 ある捕虜兵士が収容所内で私の日本人の友人に会うなり「津田さん、ドあほう」といってニコニコしていた。キョトンとして彼の顔を見据える津田さん。しばらくして「君のことばは悪いことばだ。こんご、そんなドあほうということばは使うな」と命令しながら大笑い。会うなり「ドあほう」といわれた津田さんも驚いたが、労役現場で日本人の監督から叱られた時のこのことば〝ドあほう″が正しいと信じていた兵士もかわいそうだ。聞きかじりの双方の国語を、意味もわからずに話していると、しだいに双方の間にカベができ、不信が疑惑となってまん延する。捕虜収容所という、特殊な場所では、そうしたわずかなことが、親密さを増すこともたまにはあったが、むしろ集団を動揺させ、善意も悪意となって混乱をつくり出す恐れがあることを思い知らされた。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2007-12-6 8:29 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
捕虜と通訳 (小林 一雄) (20) 捕虜たちと泣き笑いのカケひき―虚々実々の所内・その3
さて〝かけ引き″といえば、私も相手の捕虜たちも、お互いに相手方の情報を知りたい。だからよく使った手は、タバコや薬をプレゼントし、仲良しのしるしを提供してそれぞれの情報をとったものだ。 一方では、捕虜同士の間でも特定の捕虜をみんなでマークしていた。最年少のエルモア二等兵(ELMORE) もマークされていた人物だった。神経衰弱症でつねにイライラし、仲間からはずれ、それが余計に彼を孤独にし、みんなの動静を逆に盗み見しながら暮らしているふうだった。こうした彼は、だから他の捕虜たちの動静には詳しかった。彼らだけの秘密もエルモア二等兵は意外によく知っていた。だから彼を手なづけ、好きな物を与えて捕虜の動きや考え方を事前にキャッチすることもしばしばだった。彼は病棟の雑役を担当していた。 もちろん、捕虜も日本側から常に何かを知ろうとしていた。「捕虜は、いつ日本軍に殺されるかも知れない身だ。拘束された人間は、いつも相手に疑惑心で迫っているものだ」とは、当時の捕虜たちから聞かされたことばだ。その手段、つまり日本軍から情報をとるために、故意に彼らが所内で私を食事に誘っていた。もちろん、故意ばかりでなく、本当の善意で誘ってくれたことが多かったと信じているが、雑談中に何か暗示することばがないか、どうか-例えば戦況はどのように進んでいるのか、捕虜をどのように適しようとするのか、等々。 終戦の年、昭和二十年初めには、こんなこともあった。ある日、大型のアメリカ空軍のB24爆撃機が収容所のはるか上空に飛来した。「日本の爆撃機がアメリカ軍基地へ爆撃に行くところだ」-私はわざと堂々と捕虜たちにこういった。捕虜たちもそれを信じて 「日本には素晴らしい飛行機がたくさんあるんだなあ」と感心することしきり。しかし、それも束の間、日本の戦闘機 (通称・赤トンボ) が迎撃に出たが、すぐB24に撃墜され、黒煙を出しながら墜落していった。赤い日の丸のマークもハッキリ見えた。「小林さんはウソをいった。あれはアメリカの爆撃機だ。わがアメリカ空軍は日本の本土にまでやってくるはどの戦況なんだ」I結局、不利な戦況をかくそうとした私の態度は、一度に逆転し、現実の爆撃機によって彼らは〝有利なアメリカ軍″の実情を分析していた。彼らは、日本軍側が捕虜に対し、つねに日本有利を〝故意″に知らせようとしていたことを、この爆撃機事件で知ったようだった。 捕虜たちの情報源は、所外の軍需工場で働く場にもあった。つまり、当時、こうした国内の軍需工場には徴用工という名で第三国の人びとが数多く働いていた。彼ら第三国の人びとから捕虜たちは意外と多くの情報を手に入れていたようだった。例えば日本の新聞をもらってその掲載写真などで現状を分析したり、食事が日ごとに悪く粗末になっていくようすを知り、ひそかに「全員、元気でがんばろう。必ず本国へ帰る日がやってくるんだから…」と励まし合っていたようだった。それを知っていたからこそ、所内では意外と明るく、彼らの表情にかげりが少なかった原因の一つだったのではないか、とはいま思い出す感じである。 |
| « 1 (2) 3 4 5 6 » | |
| スレッド表示 | 新しいものから | 前のトピック | 次のトピック | トップ |
| 投稿するにはまず登録を | |