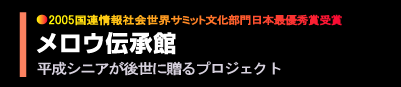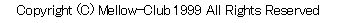メイン メイン 実録・個人の昭和史I(戦前・戦中・戦後直後) 実録・個人の昭和史I(戦前・戦中・戦後直後)
 捕虜と通訳 (小林 一雄) 捕虜と通訳 (小林 一雄) | 投稿するにはまず登録を |
| スレッド表示 | 新しいものから | 前のトピック | 次のトピック | 下へ |
| 投稿者 | スレッド |
|---|---|
| 編集者 | 投稿日時: 2007-10-30 7:42 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
捕虜と通訳 (小林 一雄) はじめに
この記録は、著者、小林一雄氏の了解を得て掲載するものです。 同氏は、大正11年生まれ、お元気です。 なお、この記録は1989年のものです。 メロウ伝承館 スタッフ 序 章 ある日、NHKテレビを見ていた。「世界は今」という、戦後《=第2次世界大戦、1939~1945》四十二年目の旧アメリカ兵捕虜の証言を放送したドキュメント特集が私の目を惹《ひ》いた。戦時中、日本軍に捕えられたアメリカ軍捕虜の生存者が過去をふり返り、現在の日本の繁栄に驚き、同時にアメリカの経済発展を謳歌《おうか》するさまが描かれていた。 当時、敵国だった日本に対する協力を拒んだアメリカ軍のある捕虜の証言だというその内容をナマの声で録音、放送したのが気にかかった。「東京の捕虜収容所での生活は惨めなものだった。食も与えられず、空腹に耐えかねて花びらや茎、マッチ棒、シーツなどをちぎって食べた。人間の扱いではなかった。収容所側は国際法を無視したひどい待遇でわれわれに接した」という意味のものだった。話の途中から私の胸のうちは憤りに燃えてきた。話が進むにつれてその怒りはいっそう燃え上がる思いだった。「そんなバカな。捕虜収容所で食糧を与えないところなんか、あるはずがない。全収容所を同一にみているような発言ではないか。裏打ちのある証言なんだろうか。どうもキナ臭い《=なんとなくあやしい》」怒りがこみ上げてきた。 というのも、私自身、大阪府下の捕虜収容所に勤務していた経験から、彼等捕虜への食事、医薬など対応には細心の注意を払っていた。彼らからこうした点について、いろいろな要求や文句もあったが、そんなにひどいものではなかった。むしろ感謝されることが多かった。こんな体験をもつ私にしてみれば、NHK特集での、元捕虜の一人の発言がどうしても納得できなかった。捕虜収容所に勤務した者の名誉にかけても、何とかその真相をつかみたい衝動にかられた。すぐさま東京のNHKに電話をかけた。 「あの特集で捕虜がいったという証言は裏打ちがあるのか?」電話を担当に回され、しばらく待たされたあげくの回答がはね返ってきた。「実は取材した全般の状態から判断して、元捕虜の発言をそのまま録音して放送したものです。具体的な証拠や物件の裏打ちはありません」何ということなのか。公正を期し、信用を第一とする、公器《=おおやけの機関》を自認するNHKの、これがやり方なんだろうか。怒りと嘆きの入りまじった複雑な気持ちになった。特殊な環境下の捕虜もいただろうが、一般的な捕虜取り扱いを報道せず、特異な一面だけを取り上げたやり方は、平均的な一般の捕虜収容所関係者にとって実に不公平で、誤解を招くもとだ。 この疑問点への結論がハッキリした途端、私の心にはもうNHKを責める気はしなくなった。 私の電話で反省し、これからの放送と取材のあり方に報道機関としての権威にかけて、十分公正な気構えと体制で臨むことを期待したからだ。私自身、NHKは大好きなのである。視聴者に誠意をもって応える法人だと信じたい。それよりも、これをキッカケに、私が全力でぶつかり、見聞し、体験した捕虜収容所の実情、ナマの姿、そこに暮らした捕虜たちの素顔と日本側の対応、交りの実態、それにまつわるさまざまなことを率直に活字にしたい気分に駆られた。 思い出すままに記憶をたどれば、活字に素人の私でも何とかなるだろう。その道のベテランに相談すると、ぜひ実行し、世に問い、訴えれば、あの時代の一つの貴重な証言となるはずだといってくれた。 ついに決意した。そしてベテラン専門家の助けを得て活字化のためのスタートをきった。時代の証言とか、捕虜収容所の実態とか、そんな肩ひじを張った考えではない。あの収容所でともに働いた旧軍人のなかから、いわれなき罪で〝戦争犯罪″の汚名をきせられたとの呪《のろ》いにも似た声も戦後、何度となく聞かされた。 《=終戦後、多数の軍人が捕虜を虐待したと指名されて戦争犯罪者になった》 これも活字化への動機となった。私のささやかな体験でも勝者に裁かれた敗者の苦しみと受けとれる事象があった。もちろん、これがすべてだとはいわないが、戦争はまさに人間を狂気に追い込み、勝者にも敗者にも、あと味の悪い残滓《ざんし=のこりかす》をふりかける。その戦後処理には、勝者の論理が優先する。このことは歴史が証明するところだ。 こうした根元となる戦争をなくすることが人類の至上《しじょう=最高》の命題であり、悲願である。営々と築き上げた人類社会のすばらしい文化を、われわれの手から次世代、さらに後世に無痕《むこん=傷跡を残さない》で渡し、遺し、伝えるためにも、私のささやかな体験が、微小な役割の一端を担えればと心から願っている。 「大正」に生まれた私だが、偶然にも「昭和」の終焉《しゅうえん=最後》にぶっかり、新しい「平成」のスタートに生きることとなった。戦争と平和の交錯した「昭和」は、史上稀《まれ》な長期を記録したが、それはまた歴史を疑縮《(凝縮)ぎょうしゅく=まとめ固める》した一時代であったともいえよう。いま、過去の私の小さな体験をまとめるに当たって、旧時代の持つ意味と、新時代への限りない期待が〝切瑳琢磨《せっさたくま=互いに励ましあって学徳をみがく》″を呼びかけるように脳裏を去来する。小著がこの大きなうねりのなかで、いかほどの役割を果たすかはわからないが、少くとも過去と未来へのすばらしい飛躍台にするという平凡な役割の何分の一でも果たせれば幸いである。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2007-10-31 7:47 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
捕虜と通訳 (小林 一雄) (2) 第一章
運命の出会い 生涯の扉を開く・その1 どんな人にも、予期せぬ出会いが、予期せぬ運命の糸で結びつける。それが生涯のすばらしい広がりをみせるチャンスをつくってくれる。 私にとってそんな出会いにふさわしいチャンスを与えてくれたのは、まず旧制大阪府立堺中学校 (現・大阪府立三国丘高校)の恩師、英語担任教諭の倉西泰次郎先生(故人)だった。きびしい授業のなかに、文明先進国の英語を通じてさまざまな欧米諸国の生活様式や文化をわかりやすく、面白く解説、当時、少くとも欧米の人たちの暮らしぶりの一端をおぼろげながら描くことができた。進学も倉西先生の、うるさいほどの叱咤激励(しったげきれい)があったからこそ、できたのだ、と感謝している。それにもまして世界通用語である英語を通して、地球のあらゆる人たちが〝人間″という共通の、かけがえのない文化で結ばれ、地球という唯一のステージで、つきつめれば同じヒューマン・カルチャー・ライフを演じていることを折りにふれて教わった印象は、生涯、私の心に焼きついて離れない。 その倉西先生と別れて進学したのが旧制兵庫県立神戸高商 (現・兵庫県立神戸商大)。ちょうど太平洋戦争《注1》の始まる直前、昭和十六年 一九四一)春だった。経済商業の実務学を通じて、生涯の職すなわち食を口にすることができれば、社会の役にも立つはず…という、全く単純、常識的な考えで入学した。 ところが、入学早々、目についたのは課外活動として積極的な活躍をする勉強会グループ・ESS (英会話クラブ)。これに所属する先輩たちが青い目の外国人教授の指導のもとに、すばらしい英語を駆使して自由自在に日常会話を交わしている。あこがれにも似た気持ちで 「これが私の将来を支えてくれる突破口になれば」 と、ESSへの入部を決意した。矢もたてもたまらず入部を申し込み、すんなりと許可されたことにも驚いたが先輩諸氏がスマートなもの腰、流暢《りゅうちょう=すらすらとよどみのない言葉遣い》な英語で応待したのには参った。気おくれするような気分に陥りながらも、まず入学最初の〝わが道″のゲートを通過した気持ちで、そう快だった。 それからは授業はまあ、平均的に聴講、一日も欠かさず出席したのはESSだったと記憶している。英語学担当のアメリカ人、ロイ・スミス (ROY・SMITH) 教授が週に一回、ESSに顔をだし、みっちり英会話を教える。下手で慣れない私にもマン・ツー・マンで指導。 温情味のある口調ながら、日常英語の発音にきびしいスミス教授の教え方は徹底していた。ESS所属の学生は、校内外をとわず、お互いに終始、英語で話すことを義務づけられていた。クラブ活動とはいえ、実に徹底したきびしい規則にしぼられていた。高商時代といえば昭和十六年(一九四一)十二月八日に端を発した太平洋戦争の真っ只《ただ》中。〝鬼畜米英″が国策として叫ばれ、英語は敵国語として忌避され、外国人の英語教師は、まるでスパイ視されボイコットされた時代。それでも私たちESSクラブ員は、校内を出ると近くの喫茶店 (当時、気のきいたこの種の店は稀《まれ》だった)などで、英語を使って雑談しながら、お互い、英会話力をつけ合った。道を歩く時にも英語で話し合う、といったぐあいだった。 ところが、この英会話、何も事情を知らない、町の一般の人たちからみると、何とも奇妙で、反戦論者がわざと敵国語を使い、反戦をあふっているのでは(?)とすら感じたに違いない。 「君たち、いいかげんにしろ。米英は敵なんだぜ。英語を使うとはもってのほかや」怒りもあらわに私たちに説教する紳士。「英語をそんなに使っていると憲兵《けんぺい=軍事警察に属する軍人》に引っ張られますよ」こわばった表情でそっと注意する愛国婦人会《=1901年創設の婦人団体、出征兵の世話や社会事業に従事》の会長さん。みんな変な目でわれわれを眺め、わざと避けている風に思えた。いま思えば、何ともバカバカしい。純粋に学生として、世界語である英語会話の力をつけたい一心でやっていた行動だったのに。ESSのメンバーは、学生気質もあらわに、こうした町の空気に反発して、余計に町の中で英会話を話すことにし、全員がよく繰り出して大きな声でしゃべり合ったものだ。 注1 太平洋戦争 第2次世界大戦のうち、主として東南アジア・太平洋方面における日本とアメ リカ・イギリス・オランダ・中国等の連合軍との戦争 |
| 編集者 | 投稿日時: 2007-11-6 7:51 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
捕虜と通訳 (小林 一雄) (3) 生涯の扉を開く・その2
当時、日ごとに戦争の火花が激しくなり、最上級の三年生は学徒兵《=1943年、学生も兵役につく制度になった》として出陣する者が多かった。一人去り、二人去り、われわれの仲間は歯の抜けたように少なくなっていった。とくにESSのグループからも軍に入隊する者が多く、会話相手が日ごとに少なくなっていった。 メンバーの一人に日系アメリカ二世のポール・保・池田君がいたが、彼も予備学生《=大学生が志願して訓練を受け予備士官になる》に志願、学徒兵の一人として日米決戦のために出陣した。私とはつねに英会話を交わす、いや教えてもらった同輩だった。彼の場合は、英語が日本語と同じように流暢《りゅうちょう=すらすらとよどみなく話す》だったため、日本人の英語教授による「英語」の時間には、「出席しなくてよいから図書館で自由にしてきなさい」と、ムリヤリ、聴講を拒否(?)されたほどだった。それでもESSにはスミス教授が出席を指示し、彼はよりすばらしい英会話マスターに懸命だった。その池田君も、海軍士官として学徒出陣する際「わが身は日本にある。アメリカ二世でも日本人としてアメリカ領土爆撃に行ってくるよ」と笑って勇躍、出発した姿をいまも忘れない。 彼は戦後、日本占領連合軍総司令部(GHQ) のスタッフとして財閥解体に活躍後、アメリカ日綿実業社長として実業界でも活躍、いまはアメリカ国籍で日米両国の架け橋として頑張っている。 旧高商時代のアルバムをめくると、あの太平洋戦争時代の戦意を燃やした学生気質を思い出す。「我、大空に散り大東亜《=戦時中の呼称、東アジア、東南アジアの周辺》の礎とならん」「安らけき学舎から誠もて、南海の大空へ、日米決闘場へ」「祖国は我等を求む。いざ行かん南の決戦場へ」神戸高商の卒業アルバムには、同窓生の口々から、三星霜《さんせいそう=三年の年月》を学んだ学舎をあとに巣立つ若者の心情が赤裸々《せきらら=包み隠し無く》に描かれている。 ある者はそのまま学徒兵として出陣する決意にあふれ、ある者はやがてやってくる”戦乱〟の運命に、人生の崇高な悟りの心で飛び込む気迫に満ちている。昭和十八年一九四三)秋、神戸高商を卒業したが、当時の社会の姿を見せつける寄せ書きだ。 それにしても高商時代に出会った恩師、同僚、先輩等々のうち、私の一生を左右する出会いも少なくなかった。いま思えば、ここでもそうした運命の糸は確実に私に垂れ下がっていた。 太平洋戦争の真っ只《ただ》中、体の弱かった私は学徒出陣からも除外されたままの卒業だった。当時の風潮としては肩身の狭い思いが先行して、外出することさえ屈辱に感じたものだ。それでも、職もなくぶらぶらできる世相ではなく、国策スクールの堺青年学校に教師として勤めた。 その最中に召集令状を受けて応召したものの、ここでも痔(じ)疾患が原因の虚弱体質のために、即日、応召を解かれて帰郷した。 一億総動員の時代、成人の若者は何らかの形で軍隊経験をし、多くの先輩、友人は各地の戦線で戦死する悲報がつづく日々。一日の軍隊経験もしないで応召にも拒まれ、銃後《戦場とならない後方の内地》の職を求める若者の心情…つらく、悲しい思いにひたらないのが異常といえる時代だった。 そんな昭和十九年(一九四四)三月のある日、「若者は、戦線に立たなくても何かの形で間接的に国家に奉仕して職につかんと心身ともに再生できなくなる。若い君だ。せっかく培った能力を生かす職場にこないか?」と、就職口をもって来て下さったのが、あの中学時代の恩師、倉西先生だった。陸軍中尉のりりしい軍服に身を包んだ倉西先生の姿に驚いたが、次いで出たことばにも驚いた。「捕虜たちの通訳としてこないか?君なら十分、通用するから」 当時、敵国だった英米などの軍人が捕虜として日本の本土へ移送されているのを知ったのもこの時だった。大阪にも各地に捕虜が隔離、移送されていた。倉西先生は大阪捕虜収容所多奈川分所(大阪府泉南郡岬町多奈川)の分所長だったのだ。軍服のナゾも解け、結局、日常英会話が多少でも話せるか、どうか自信もないまま、恩師・倉西中尉の強い説得にねじふせられたかっこうで同分所へ「民間人通訳」として就職した。昭和十九年(一九四四)春、二十一歳の時だった。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2007-11-7 7:56 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
捕虜と通訳 (小林 一雄) (4) 生涯の扉を開く・その2
いま考えると、高商時代のESSとの出会いを、倉西先生が知っていたのがこうさせたのだろうか。 当時、多奈川分所の捕虜たちはアメリカ軍三百人、オランダ軍六十人。すべてが民間の建設土木会社「飛島組」が軍から請け負っている軍需工場の建設工事に狩り出され、労役に従事していた。私も彼らの通訳ということで即日、飛島組の社員として採用され、勤務地は多奈川分所。就職初日、恐る恐る鉄条網の張りめぐらされた板塀囲いの収容所の門をたたいた。 陸軍の衛兵が威丈高に用件を聞いた。「倉西中尉に面会にきた」といっても、すぐには通してくれない。イガグリ頭の小さな体躯《たいく=からだ》の私が分所の陸軍最高責任者に会いに来たといっても、信用してくれないのが当たり前だろう。それでも、連絡の末、やっと中に入れてくれた。倉西中尉に会った時に初めて笑顔が出た。ほっとした。軍隊にも拒まれたひ弱な若僧が、捕虜とはいえ、弾丸飛びかう第一線をかいくぐった兵士たちの集団収容所の中に初めて入ったのだから無理からぬことだった。 ここの捕虜は、戦争史のなかでも特筆される、あの、フィリピンの〝バターン死の行進″を体験した将兵、コレヒドール島の生死を分けた激戦のさい捕えられた将兵らで、当時の敵将マッヵーサー直属軍団の歴戦の戦士だった。まだ見ぬ敵国兵への興味が段々と湧《わ》き、倉西分所長の指示もなかば、うわの空。私の任務は、捕虜管理に当たる収容所事務所と捕虜たちとの連絡係。「相互の意思疎通を円活にして軍需産業に役立つよう仕向けることと、それとなしに捕虜の動静を観察する、いわば情報・宣撫《せんぶ=上意を伝えて人心を安定させる》を担当すること」 倉西分所長のきびきびした口調と動作には、かつて教壇で見た英語教師の面影は見出せない感じだった。しかし「捕虜として国際法のワクをはずれた接し方はしないように。戦時中とはいえ日本人の持つ文化を損うことにもなるのだから…」という静かな口調には、教師としての香りを嗅《か》ぎ出せた感じで、あらためて〝倉西中尉〃を〝倉西先生〃とダブらせて見出せた。その柔和な眼が、私の心を安堵(あんど)させてくれたようだった。とはいえ、収容所は捕虜の管理と保護が任務だが、鬼畜米英を叫ぶ戦争の真っ最中に、アメリカ軍捕虜を保護する仕事とは…心の中は複雑だった。 多奈川分所は約一万平方メートルの敷地内に、五十人ぐらいが一棟に起居するバラック小屋十棟、このほかに同じバラック建ての病棟と大きな炊事棟、浴場棟、倉庫、靴修理棟、別に日本軍の管理事務所のある管理棟、唯一か所の衛門と衛兵詰所、大きな防空壕《ごう》、それに大きなグラウンド。収容所の周囲は高い板囲いでその上に有刺鉄線が高く張りめぐらされ、板囲いの四隅には高い監視塔が設置されていた。各起居棟の一部には将校専用の特別室があり、下士官と兵士は同じ場所。どの棟も真ん中の通路をはさんで左右にワラを敷きその上に畳をのせて毛布でごろ寝というような長い部屋が上下二段に並んでいた。冬は薪やオガクズでドラムかんストーブをたき暖をとるという、バラック建てそのものだった。 監視護衛は、和歌山の歩兵連隊から約十人が一週間ずつ交代で当たった。管理事務所には倉西分所長のほか庶務、経理担当軍曹二人、衛生兵一人、民間人の通訳二人、傷い軍人《=戦場で傷を負った軍人》上がりの軍属《=軍に所属して軍人でない文官》十人が常時、勤めていた。このほか日本人管理棟の掃除、炊事係の中年婦人三人が雇われていた。私は毎日、堺市湊の自宅から配給米やサツマイモを中心にした手弁当を下げ、南海電車で片道約五十分の通勤。職務の指示を受けたその日は、そのまま帰宅したが、まだ見ぬ外国軍人、敵国兵とこれから毎日、接して話し、通訳するという〝仲介業″に不安と興味半々の何ともいえぬ奇妙な気持ちから、その日はなかなか眠れなかった思い出を、いまでもハッキリ覚えている。 それでも「さあ、あすから想像の世界にしかなかった異文化との遭遇が現実のものとなる。思いきってぶつかるしかない」と自分にいいきかせ、やっと深い眠りにつくことができた。とはいえ、英語の勉強ができる興味と、敵国人との対話。しかもわれわれ日本人が保護している敵国軍捕虜に直接、接する日が明日からやってくる、という複雑な思いが心をよぎっていたことは否めない。 それにしても、中学校時代に教わった英語の教師との出会いがなければ、あすから勤務する捕虜収容所への就職の門も開かれなかった。高商時代のESSとの出会いがなければ、それに応えることもできなかった。運命の出会いとはこんなことをいうのだろうか。〝倉西先生〟とは、よくよく運命の糸で結ばれていたのだろう。そして軍隊入りを拒まれた虚弱な一青年が、歴戦の敵将兵の捕虜を集団で管理する収容所で〝民間人通訳″として働くことになるとは…怖いような〝運命の扉″に立っているという感じを持たずにはおれなかった。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2007-11-8 7:33 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
捕虜と通訳 (小林 一雄) (5) 第二章
新米通訳、初出勤 捕虜収容所の門をくぐって・その1 捕虜収容所に正式勤務の初日。早朝まず全員が所内の広場に整列して点呼。約三百六十人のアメリカ、オランダ両国の非武装将兵がズラリと並んで武装した日本軍兵士の前で訓示を聞く姿を見て、私は驚き、同時に奇異に感じた。 「ウーン、これからこの捕虜たちとどうやってつき合っていこうか?」一瞬、戸惑った。が「奴らが学友を死に追いやった張本人だ」と、わけもなく〝敵衡(てきがい) 心″が起きたことも、一瞬とはいえ事実だった。 アメリカ兵はいずれも一・七五メートルを超える〝大男”。小柄な私にはとくにそう思えた。オランダ兵は本国兵ではなく東南アジアのオランダ領兵士で、日本人よりも比較的小さく、皮膚の色も茶褐色、人数も少なかったせいか、極端な驚きと奇異な感じはしなかった。それでも、(当時の)〝植民地兵″が捕虜としていまここにいる、と思うと、植民地、戦争、捕虜ということばを通じて歴史の不可解さと現実の恐ろしさを感じずにはおれない。 捕虜たちは、最初に予想したほど決しておどおどした、いじけた態度ではなかった。むしろ、初体験の私の方が緊張して他人目にも驚くほど堅くなっていたのではないか。簡単な倉西分所長の指示を通訳したが、自分で何をどう訳していったのか、あとで考えても思い出せなかった。ただ、捕虜全員が私の英語訳を黙って無表情に聞いていたこと。これは私に勇気を与えてくれた。「通じた英語」という自信を与えてくれた、と思った。 人間、落ち着くと逆に心に余裕が出てくる。彼らへの初印象で得た〝驚き〟は「よーし、この調子でこれからじっくり捕虜を観察してやろう」と心理的に変化してきた。「われわれは勝っている。彼らに戸惑うことはない」自分で自分にいい聞かせる余裕もでてきた。 こうして〝新米通訳″の勤務が始まった。朝の全員朝礼、点呼から、収容所を出て外部での建設作業、夕方の帰所で始まる所内の生活と、毎日、決められた時間表に従う彼らの生活とのつき合いがスタートした。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2007-11-10 8:36 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
捕虜と通訳 (小林 一雄) (6) 捕虜収容所の門をくぐって・その2
ある朝、食堂で食事する彼らを見たが、当然ながらスプーンとフォーク、ナイフだけで、箸《はし》は使わない。三百六十人の大世帯がガチャガチャ、フォークやスプーンの音を立てながら食事する風景は、日本的食事様式に慣れきった私には異様だった。 「これが異文化だ」同時に「箸を使うわれわれの方が指先は器用なんだ。繊細な心情、自然を愛し、花鳥風月を賞(め)づる心もここに原因の一つがあるのでは?」 こんな心に駆られもしたが、どうしても〝戦争″に結びつけた考えは、こうした思いからは出なかった。 捕虜の起居する生活棟などは一定の時間に日本の武装衛兵が見回る。その時は私も同行したが、ある夜、私一人が彼らの夜の生活を見てみようと無手勝流にバラックへ行った。入り口に立っている当番のアメリカ兵が不動の姿勢で挙手の礼を私にする。あわてた私も挙手で返礼したが、軍人でもない私は一瞬どきまぎした。アメリカ兵から敬礼される自分自身、てれくさい反面、けったいな感情も湧《わ》いた。でも少くともこの所内では捕虜たちはわれわれに絶対、服従している証(あかし)を敬礼で示したんだ、と安心した。こんなことがきっかけとなって、私の彼らに対する行動も一日ごとに大胆になってきた。 一人で彼らのバラックに出かけ、一対一で話すこともしばしばだった。しかし、ちょっとした会話にも、私の話すことばに、彼らは首をかしげ、的確なことばが返ってこないことが多い。「なぜだ?」自問自答してもなかなか理由がわからない。自分としては高商時代のスミス教授直伝の英会話を思い出し、懸命に正しい英文法で話しているつもりなのに…。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2007-11-11 9:03 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
捕虜と通訳 (小林 一雄) (7) 捕虜収容所の門をくぐって・その3
そんなある日。アメリカ側の連絡将校、ガルブレイス大尉(JOHN・M・GALBLAITH)と雑談中、突然「小林さん、あなたの英語は私らに正しく理解できません。あなたの表情と手ぶりなどから理解する努力をずっとつづけているんです」と遠慮がちにいうではないか。 一瞬、びっくりした。すでにここに来て二週間近くなり、毎朝、朝礼で倉西分所長の指示を全員に通訳し、彼らは指示どおり職務を遂行しているというのに。にもかかわらず私の英語が理解できないとはどういうことだろう。恥ずかしいやら、腹が立つやら、身の置きどころに困った。ブロードウォーター中尉(ROBERT・BROADWATER)ともこんな話をよくした。 「でも小林さんは親切で誠意のある通訳ぶりがわかりましたから、われわれもそれに応えて理解につとめようと、みんなで了解しているんです」というガルブレイス大尉。その表情は決して私を侮辱しているのではない。むしろ好意の目で私を見つめ、「友人だから率直に言ったんだ」といいたげな表情だった。「英語の標準語はイングランドの古いしきたりをもつ人びとならいざ知らず、アメリカの庶民、とくに軍隊ではなかなか通用しません。とくにアメリカ軍の特殊な用語、GIスラングがありますからね」とつづけるガルブレイス大尉やブロードウォーター中尉。私はますます赤面する面持ちだった。そんなことも知らずに大きな顔をして通訳していたことを恥じた。学校で習った英語、それもESSで精いっぱい努力して頑張った英会話がこの結末なのである。日本の英語教育に対する反省をしみじみ味わったのも、この時だった。 とくに〝英語の発音″の未熱さは恥づかしいほど痛感させられた。しかし正しい文法に従った文章になるよう努力して話したので、彼らにも何とか理解できたのかも知れない。逆に彼らの話す英語の早口の発音には困った。つまり、彼らのことばのヒヤリング(聞くこと)になれるのに時間がかかった。私のスピーキング(話すこと)は、まづい発音でも、彼らが注意深く聞いてくれたこともあって、通じたのだといまも思っている。 それはともかく、彼らが仲間同士で話す会話は、GIスラングと早口でサッパリわからなかった。チンプン、カンプンとはこのことだと思い知らされた。耳に入ったことばを、一語、一語、分解して辞書で調べても見当たらない。ついに、私は、聞いたままを自己流の単語にして、理解できない文章のまま、しゃべったものだ。しかし、発音は〝OK″だったが、文章は〝NO″だった。 つまり、そんな文章に使うGIスラングではなかったので、全体として意味がサッパリわからないものになっていた。悲しかった。 GIスラングというのは、無意味な単語が、意味のある単語の間に、適当に語呂《ごろ》、語感のよいように入れられていることがわかったのは、ずっとあとになってからだった。大阪弁に例えていうと、「まったくダメだ」 という場合、「どっと、さっぱり、わやや、ドあほう…」 というようなものである。正式に日本語を学んだ外国人には、まったく通用しない。これと同じような例になるわけだ。もちろん、公然と使えないような、下品、非礼な単語が妙に多く、アチコチの会話の中に挿入されているので、学校英語しか学んだことのない私、正しい文法だけを指標に外国語教師に学んだ私には、そんな〝ムチャ、クチャ″な英語が理解できるハズがなかった。 私は、自分が理解できない特有のスラングを熱心に彼ら、とくに将校に聞いた。すると彼らは、単語を書き並べて発音、意味のないスラング単語を消去し、正しい英文に仕立て直して解釈する方法を教えてくれた。なるほど、こうすると時間はかかるが、1〇〇%理解できた。私の〝通訳″もこうしたことがキッカケとなってやっと進歩しはじめたように思えた。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2007-11-12 7:15 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
捕虜と通訳 (小林 一雄) (8) 捕虜収容所の門をくぐって・その4
それはともかく、こんな苦労(?)の道程も経て、彼ら、とくにガルブレイス大尉と私は、まだ下手な私の英会話ながら心が通じ合うようになった。いろいろなことを話し合った。 いまでも忘れることのできないのが〝生死観″というか、〝捕虜観″の違いだった。彼との会話だけでなく、どのアメリカ兵にも共通する考えがわかった。彼らは捕虜になることを恥とは思わない。「戦場で死ぬよりは生きて捕虜になることが、授った生命に対する真の答礼であり、後日、再び社会のためにその命を役立てることになる」(ガルブレイス大尉)という考えからだという。「生きて虜囚 の恥づかしめを受けず」という旧日本軍の戦陣訓《1941年日本軍が定めた将兵の心得》に象徴されるように、わが国では古来、ずっと捕虜を恥とする思考が優先してきた。負ければ死しかない。囚われの身は敵の軍門に下ることであり、軍人として許されない行為である、というわけだ。それにしても日中戦争もふくめ太平洋戦争でも数多くの日本軍の捕虜がいたというのに、戦時中は一般に公表されなかった。民族文化の差がこの考え方の違いを生んだのだろうか。つくづく考えさせられた。 「捕虜になることは不名誉なことではない。もちろん英雄的なことではないがアクシデントである。不運な兵である」アメリカ版戦陣訓のこのことばば 「脱走が捕虜の義務である」とも述べている。ということは捕虜になっても戦いはつづいているのだ。アメリカでは捕虜になっても決して恥とは思わない。日本的な物の考え方では想像もつかない。 この日本とアメリカの捕虜観の違いは、生死観の差でもある。この違いが、国際的な捕虜に関する条約を基準に旧日本軍とアメリカの軍隊を比較すると、人間的な自覚とその水準の開きを生んだのではないか。生まれて初めて見た捕虜の姿。こうも驚くこと、恥づかしいことがたくさんあったことに、むしろ驚かされた。「よし、彼我の違いを克服するためには徹底して彼らの生活にのめり込み、彼らのことばをマスターすること。これが彼らとのミゾをなくする先決条件だ」私は心に誓って収容所の広場でしばらく一人で瞑想《めいそう=眼を閉じて静かに考えること》した。それまで無意識のうちに肩を張り。〝背伸び″の姿で勤めていたのかも知れない。新米ということで堅くなっていたのかも知れない。英国で生活経験のある英語ベラベラの先輩の通訳に負けまいと、変なあせりがあったのかも知れない。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2007-11-16 10:05 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
捕虜と通訳 (小林 一雄) (9) 第三章
くそ度胸で通訳奮闘す・その1 収容所の勤務も一か月を過ぎると、人にも環境にも慣れてきた。所内の日本人職員では私が最年少で、もっとも多感、情熱的だったと思う。だから余計に図太っさもでてきた。本来の通訳らしいポーズも、自分ながらとれるようになったと自負できた。 そうなると、単に言葉の仲介者だけにとどまらず、単身、所内のいたるところをぶらつくことが多くなってきた。捕虜たちの顔も覚えてきた。フォーブス(FOBES)、ライレイ(RILEY)、ブラウン (BROWN)、ジョンソン (JOHNSON)、トーマス (THOMAS)各大尉、ファーレル少尉 (FERREL)、ディクソン軍曹 (DIXSON)、グレゴリー曹長(GREGORY)……彼らとよく話した。 昼間、捕虜の兵士たちは所外の労役作業で留守になる。将校たちは国際法の捕虜規定で労役に服させることはできないので、専ら留守役となる。昼間は、することもなく、なかには畑を耕やして農作物の収穫を喜ぶもの、読書と所内スポーツに明け暮れるもの、所内の整理整頼に精出すもの…とさまざま。 ただ軍医だけは医務病棟に釘づけとなって多忙な毎日だ。その将校連も交代で当直に当たっている。私が暇をみては所内をうろうろしていると、こうした当直将校から話しかけてくることが多くなった。自然に彼らとの友情も日ごと深まり、英語と”日本語”の交換教授″も進んできた。とくに夜間がそうだった。 裸電球一つの薄暗いバラック棟の中では、左右両側から聞こえてくるイビキや寝息…そんな中を注意深く巡回し、不寝番の捕虜兵士に 「異常はないか?」 と小声で問いかけて歩きながら、彼らを何とも哀れに感じたこともあった。彼らに対して〝敵″ を越えた〝人の情″が湧《わ》いてきた。 ある夜、当直将校の一人、ジョンソン大尉 (OEL・JOHNSON) と話す機会があった。 「日本人は短気な国民だと思う。部下が昼間、労役作業中、よく管理・監督者の民間班長から文句をいわれ、殴られたと不平をいっている。あんなに殴打する国民を見たことがない。だから短気な国民だと思うようになったんだ」 という。捕虜には日本側に対等に闘争する術がない。 口頭による抗議が精いっぱいという、泣き寝入りに近いありさまが、〝彼らの無念さ″としてあったことがよくわかる。 「いや、そんな短気者ばかりではない。いま日本全体が戦時体制下で管理されており、とくに軍需工場などでは一刻も早く軍需品を完成させ、修理を終わらなければならないので、ダラグラしている者をみると、つい文句をいうのだろう」と私。 「まあ、所長にいってなるべくそうしたことのないよう配慮してほしい」「よし、わかった」そう思いながらも、殴ることがあるのだろうか(?)と半信半疑の気持ちが先に立っていた。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2007-11-17 9:06 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
捕虜と通訳 (小林 一雄) (10) くそ度胸で通訳奮闘す・その2
所外労役から帰った捕虜たちの抗議に何度か立ち合ったが、いつもこれ以上、トラブルを大きくしないよう、日本側と捕虜の双方に適当な〝インチキ通訳″をして和解につとめたことを、いま思い出す。 ある夜、捕虜バラックに行った時だった。当番の兵隊の敬礼を受けて中に入ってみると、まだ消灯時間には間があったせいか、みんな起きていた。ジョンソン大尉の姿もこの兵士棟に見えるではないか。他の数人の兵士が険悪な表情でまくしたてている。よく聞いてみると、昼間の作業中、理由もなく日本の労役監督から殴られたという。しかも通訳も悪い口調で罵倒(ばとう)したという。こんなことでは指示された労役に服すことはできない」「何とか是正するよう力になってくれ」と、しまいには懇願調だ。 労役作業現場の通訳は高木芳一氏(当時三十五歳)。イギリスでの生活が長く、英語はベラベラ。GIスラングも自由に聞き、話すことができるほど、うまかった。彼の話によると、現場の日本人軍属が、休憩時間でもないのにズル休みしているアメリカ兵にビンタを張ったという。 その時、高木氏も日本人監督のことば通り、きついことばで、その捕虜を叱《しか》りつけた。捕虜にいわせると「こちらの言い分を少しも取りつごうとせず、まるで監督のような振舞いをして侮辱された」-ざっとこんな事情だった。「実情を所長に報告して、本当にそうなら二度と不合理なことの起きないよう善処する措置を進言する」という私のことばに、ようやく一件落着。こんな昼間の所外でのトラブルが、夜になっても尾を引くことが多く、所内の通訳を担当している私にとっては、事情の真相がわからないまま〝トラブル延長戦〟を収拾することが多かった。 その高木通訳。私からみれば冗談をよくいい、笑わせる人だった。捕虜たちも流暢《りゅうちょう》な彼の英語を聞いてよく笑い、話し合っていたのを覚えている。私にも捕虜の扱い方などを教えてくれた。実直な人だった。所外の強制労役作業に付き添う通訳という職務柄、日本側のきびしい労役条件と環境の中で、時には誤解によって捕虜から憎まれることもあったのではないか。毎日の所外でのことなので、私に真相がいまひとつ明白に理解できないのは残念だが。戦後、これらのことが重なり、原因になったのか、高木氏の運命を大きく左右することになるとは、当時、誰も推測すらできなかった。 |
| (1) 2 3 4 ... 6 » | |
| スレッド表示 | 新しいものから | 前のトピック | 次のトピック | トップ |
| 投稿するにはまず登録を | |