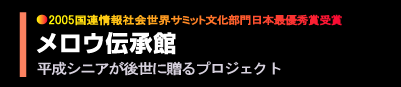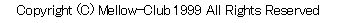メイン メイン 実録・個人の昭和史I(戦前・戦中・戦後直後) 実録・個人の昭和史I(戦前・戦中・戦後直後)
 『肉声史』 戦争を語る 『肉声史』 戦争を語る | 投稿するにはまず登録を |
| スレッド表示 | 新しいものから | 前のトピック | 次のトピック | 下へ |
| 投稿者 | スレッド |
|---|---|
| 編集者 | 投稿日時: 2007-8-24 7:39 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
『肉声史』 戦争を語る (21) 「ノルマで変わる食生活」
藤沢市 小林 正雄(大正15《1926》年生) (あらすじ) 昭和20年、私は南満錦県の飛行隊にいた。戦局は厳しさを増し、対ソ連特別攻撃隊員として日々特攻戦技に励んでいた8月に終戦となり、武装解除。愛機を捨て去るのは忍びがたいことだった。同年秋、帰国できると信じて乗った列車は、荒涼とした平野を北へ向かいシベリアヘと走っていた。バイカル湖畔をさらに奥地へ行き、ヤーヤ収容所に着いた時は日が暮れていた。 零下30度、極寒のシベリアで重労働が始まった。私は伐採した木材を貨車に積み込む作業。ロシアの労働者には女、子供もいて馬ソリで木材を運んでいた。私達の作業はノルマ制の能率給食で、80%以下は黒パン250 g 、100%で300 g 、と薄味のスーブ1椀《わん》。半年もすると体力も衰え、栄養失調で倒れる友も毎日のようにいた。私は腐敗した馬鈴薯を拾い、ペーチカで煮て食べ飢えをしのいでいた。2度目の冬がきた頃には亡くなる友は日に日に増え、苦衷《くちゅう》この上なく言葉に表すことはできなかった。 ロシアの思想教育があり、何ケ月か過ぎたある日、一日の作業が終わり、ラーゲル(収容所)に戻った時、収容所長、政治将校、通訳を交え、待ちに待った帰還発言があった。そして夢にまで見た懐かしい故郷日本へ帰ることができたのは、昭和23年5月のことだった。 「爆弾、穴埋め、また爆弾」 藤沢市 大野ひろし(大正8《1919》年生) (あらすじ) 昭和16年、私は22歳で3月に卒業して就職したばかりだった。ラジオで開戦を知った。 体が震えて「ああ始まったか」。1月10日入隊。甲府の連隊から麻布の3連隊へ。国民は何も知らされてなかった。その後ハルピンの司令部へ行き、初年兵の訓練が始まった。寒さに強い兵隊を作ろうと、ソ連と戦う準備だった。雪の中で病気や凍傷との闘い。そのうち貨車で九州へ。大分の港で大きな輸送船の中、どこへ行くのかも知らされず船底で隠れて持っていた。 船団組んで昭和19年に沖縄へ行った。半月程してさらに宮古島へ。島の人達は私達を日の丸の旗を振って歓迎してくれた。島を守るんだという気持ちで降り立った。島内を歩いて偵察し飛行場をエンピとハンマーで整備した。夜になるとグラマンが爆弾を落としていく。爆弾であいた穴を埋めているところへまた爆弾を落とされシーソーゲームのようだった。毎朝6時に起床、陣地構築が日課だった。 困ったのは食糧が内地から来ないこと。せっかく来ても島に降ろす前に攻撃で沈められてしまう。島の人が食糧を分けてくれた。島には4年いたが、私はマラリアに罹った。肝臓が腫《は》れ、黄疸《おうだん》が出ても任務遂行。島民がヤギの乳をくれたり、魚を差し入れてくれた。ありがたかった。20年12月沖縄の捕虜収容所へ。沖縄は山が平らになっていて戦いの壮絶さを物語っていた。 21年3月に浦賀へ戻った。両親の死に目も会えず、戦争にはズタズタにされた。戦争は一人ひとりが自由にならず、皆同じ方向を向かされる。恐ろしい。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2007-8-25 7:03 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
『肉声史』 戦争を語る (22) (お話を聞いて①)
私がお話を開いて一番印象に残ったことは、“運命”の不思議さということでした。「もしあの時沖縄に残っていたら死んでいた。」そんな、死まで常に紙一重である。“戦争”という苦しくつらい中で「こんな中でも生き抜いてやるんだ、コンチクショー。」という精神力を持っていたことにより戦争を切り抜けてきた人がいます。運命の中で精一杯頑張りぬいたからこそ今の命、幸せがあるのです。だから、3年間の勉強が報われずに私立に行くことになってしまった今、私はしっかりこの“運命”を受け止め前を向いて歩んでいこうと思います。いまのこのつらいときが、3年後「このときがあってよかった。」と思えるように運命は全部が全部受け身であるわけではなく、努力次第に変わるものだから。 (聞き手 定村美幸 平成2《1990》年生) (お話を聞いて②) 今まで、いろいろな場面で戦争の話をきいたことかあります。 しかし今回のように実際に戦争を経験した人から話しを聞いたことは無かったのでとても勉強になりました。話を聞く中で一番強く思ったことは、人生ってわからないなあということです。大野さんが、沖縄から宮古島に移ったときのことを当時は沖縄にいたかったといっていましたが、今思うと宮古島に移ってよかったと言っていたことがとても印象に残っています。私はこのことばを聞いて勇気が出ました。これから生きていく中でそのときは失敗したと思っても将来の成功につながるかもしれないと思えたからです。失敗したと思うならそれを受け入れて生きればいい、信じた先に素晴しさを見出すことができる。そう思いました。 このような発想の転換ができたのも水野さんの話しを聞くことができたからだと思います。私もこれから何かあっても大野さんの話しを思い出して明るく生きたいと思いました。戦争が終わり、それから何年も経っている今でも当時のことを思い苦しんでいる人はたくさんいると思います。過去に負った傷は消えても傷を負った過去はいつまでも消えないのです。だから今回の話しを通して、戦争は絶対やってはいけないものだと再認識することができました。 (聞き手 田中翔子 平成2《1990》年生) |
| 編集者 | 投稿日時: 2007-8-26 8:19 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
『肉声史』 戦争を語る (23) 「うれしかった出征見送りと差し入れ品」
藤沢市 小菅 信雄(大正3《1914》年生) (あらすじ) 23歳で補充兵として出征。昭和12年10月12日、赤紙がきて1週間後のことだった。 東京近衛3連隊へ。まず「上官の命令は如何を問わず直ちに服従しろ」と言われた。礼儀作法ばかりで軍隊の事はやらず、19日に出動命令。「明日午前2時品川駅集合」で各自家に連絡し家族や職場の人が駅に見送りに来てくれた。品川を7時に出発、8時頃列車が藤沢駅を通過する時、村中の人が屋根に乗って「万歳」と見送ってくれた。途中、小田原駅と静岡駅での国防婦人会《=陸軍支援の本女性の戦争協力機関》の茶と菓子の接待が嬉しかった。夜には広島へ到着。練兵所で銃を渡されて1週間演習。宇品《=広島市南部の港》から行き先分らず「おはいお丸」へ乗り、朝鮮の木浦へ。 そこで11月3日「くらま丸」に乗り換えたが、北支からの兵が一杯で寝る所もなかった。 その時上海陥落の放送があった。5日の午前5時、広州湾へ上陸開始命令。私達300人にスコップが渡されて上陸。上海領事館には「100万上陸成功」とアドバルーンが揚がったが本当は10万人の上陸だった。クリーク《=中国の小運河》を埋めながら自分達で道を作って行く。 日本人か分らない死体が累々。軍からの食料支給もなく、現他のさつま芋を掘って食べた。1カ月後上海へ。停泊場司令部の計画課で暗号を受け渡しする係だった。昭和14年9月に帰国。 再び昭和20年7月1日に召集、東京目黒の近衛師団へ。 45名の主計《しゅけい=会計をつかさどる》下士官要員だった。そこで終戦。これからどうなるのかと不安だった。何とか人並みになろうと一生懸命生きてきた。 (お話を聞いて) 信雄さんに戦争を語っていただいて私がとても心に懸かったこと、それは国家がどのように国民を兵士に仕立て、信雄さんがそれをどのように受け止めていたかという心の軌跡《きせき》であった。 農家の次男として穏やかなラリーマン生活を送っていた23歳の信雄さんに召集令状が届いたのは昭和12年の秋のこと。「いよいよ来たか」とそんな心境で赤紙を開いたという。入隊までの一週間は出征祝いが続き、出発の朝は村中総出の見送り、高揚した心は様々の憂いを断ち切らせてしまった。そして入隊してからの一週間に訓練されたことは「情感(上官?)に対する絶対服従」の徹底した教えだけであった。上官の命今によってのみ働くロボットに改造されたのである。上官の命令、すなわち国家の命令に一極集中させ、個人の意思や思考は遮断され、死への恐怖さえ削《そ》いでしまったのである。国家が国民にかけたマインドコントロールではなかっただろうか。戦場で目にした参状を語るとき、信雄さんは声を詰まらせ、タオルを顔に押しあてた。辛い過去を容赦なく快っているようで私も辛かったが、信雄さんの痛みをしっかり受け取らなければとテープを回し続けた。 戦士としての信雄さんは銃をペンに持ち換えることが出来て、計画係りという事務職の任に就いた。この選択は信雄さんの強い意志が働いた結果であり、戦争という極限状態の中で強靭《きょうじん=強く粘りある》な精神を持ち続けた証《あかし》でもあった。しかし戦地での2年半を終え、帰国を果たした時の記憶がすっかり抜け落ちているという。極度の緊張状態から解き放たれた時、人間はきっと心の糸が切れてしまうのだろう。その傷も癒えぬ昭和20年夏、信雄さんには2度目の赤紙が届いたのである。 憲法9条(戦争放棄)改正も取り沙汰される今、平和の希求に託す私の一票は信雄さんによっていっそうその重みを加えた。 聞き手 清水茂代 昭和20《1945》年生まれ |
| 編集者 | 投稿日時: 2007-8-27 8:30 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
『肉声史』 戦争を語る (24) 「焼夷弾はザーという音で降ってきた」
藤沢市 小野 進(大正14《1925》生) (あらすじ) 昭和20年5月29目、横浜の大空襲で中心部はほとんど焼き尽くされた。その日は朝からラジオで空襲警報。私と母と同居の女性は、家の前に掘った防空壕に入った。当時は皆、家の前の道端に穴を掘り、板で土留めしてその上に土を被せた防空壕を作っていた。3人も入れば一杯で、弟は隣の家の防空壕に入った。入り口から上空を見ていたら、保土ケ谷方面から山下公園の方へ9機編隊で飛んで行くのが見え、落とした焼夷弾がゴマを撒《ま》く様に散って落ちてくる。3波目の9機が落とした焼夷弾がザーッと者を立てて落ちて来た。 防空壕の蓋を閉め、ダンダンと破裂音がした。 B29が通過したのを見て家へ飛んで入ったら、奥の部屋の床の間付近で掛け軸が燃えていたので、座布団で叩き消した。2階へ上がったら、壁に1発突き刺さり、壁の芯の竹が燃えていた。当時の壁は竹を編んで土を塗り漆喰《しっくい》で仕上げたものだった。これは消せないと、裏山の小学校へ避難。轟々と音を立てて飛んでいく飛行機とボウボウ燃える音。学校へ避難する途中もザーザーと(焼夷弾が)落下してくる音。早く逃げたので煙にも巻かれず4人一緒に学校へ行けた。死者3700人、負傷者1万人程出たらしい。山の上の学校から見ても煙一面で何も見えなかった。正午頃静かになり、煙も少なくなったので町を見たら一面の焼け野原。やられたと思い、悔しいという思いはなかった。これでもう空襲は来ないなという気持ちだった。戦争は普段の暮らしをダメにするもの。平和が何よりだ。 「地面がノート、苦しい疎開先の生活」 藤沢市 西川 美津子(昭和8《1933》年生) (あらすじ) 私は当時小学5年生で田舎がなかったので学童疎開した。疎開先は愛甲郡《=神奈川県の》の寺だった。 初めての経験で遠足に行くような気特ちで出発したが、疎開先でも食糧不足で朝から雑炊。 だんだん要領を覚えて、後方に並ぶと鍋底に沈むご飯粒が食べられることが分かり、なるべく後の方に並んだ。週2回農家にお風呂を貰いに行くと、風呂上りにもらえる蒸《ふ》かし芋が楽しみだった。 疎開先がお寺だから、皆お供えを狙《ねら》っていた。朝礼で、皇后様の教を暗唱した。未だは忘れちれない。頂いたビスケットも10日間程食べた。勉教はしなかった。ほとんど生活に費やした。 自分達のことは自分達でやった。兄弟の多い子が生活の知恵を持っていて、リーダーシップをとっていた。教科書は不足していた。地面がノート、新聞紙で習字練習した。疎開する前は配給制度。3人兄弟の末っ子で、母が早くに亡くなっていたが近所が助けてくれた。自分達の子と一緒に育ててくれた。今は豊かだけど殺伐として、子供がかわいそう。豊かなのに何か足りない。昔は皆助け合って生きていた。 戦争終わって疎開から親元へ戻れるのが嬉しかった。灯火管制《=夜間敵に悟られないように減光、遮光、消灯》がなくなっで家が明るくなったのも嬉しかった。生きることに無我夢中だった。爆弾がもう落とされないのが嬉しかった。 |
| 編集者 | 投稿日時: 2007-9-6 7:11 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
『肉声史』 戦争を語る (25) (お話を聞いて)
“ガツン"胸に、体中に感じたことのない衝撃《しょうげき》を受けました。 西川さんは疎開されていた時のつらい生活とその心の内を話しでくれました。同席された高橋さんは、この地[善行]がおかれていた状況とご主人が外地に行かれ残された家族のことを話してくれました。 「空襲警報」発令で防空壕へ、「警戒警報」発令では家の電灯を黒い布で覆って真っ暗に。 「現役」と「召集」の違い、予科練、機銃、赤紙・‥。映画や本でしか聞いたことのない言葉を直接耳にし、お話についていくのに必死でした。現実とは思えない出来事の数々‥・。“実際に体験されたことなのだ。本当におこった事実なのだ" そう何度も心は訴たえなければとても考えられない事ばかりでした。 灼熱の太陽の下(もと)逃げまどう 又めぐり来る 戦(いくさ)の記憶 西川さんはいいました。夏の暑い時期がくると毎年おもいだすのよ。 そしてもうひとり同席された91歳の斉藤さんはいいました。 「つらいことは、なかっったよ」・・・と。その言葉がずしりと重く心に突さ刺さり残っています。 私は、今日聞かせていただいた貴重なお話をしっかり受けとめ心に刻み、自分の友人や子供達に伝えていきたいと思いました。 そして平和への感謝の気持ちと大切なもの、守っていくべきものを見失ってはならないということを改めで感じました。 (聞き手 石塚由加里 昭和39《1964》年生) 「引揚船 乗り遅れで命拾う」 藤沢市 武田きよ子(昭和3《1928》年生) (あらすじ) 昭和20年8月15日、樺太川上町から女子供だけの引き上げが始まった。慌しく食物と着替え少々をリュックに詰め、父と別れて母と2人、北海道の親戚を頼りに身を寄せることになった。その日の夜、大泊港に向けて、土砂降りの雨の中汽車で出発。汽車は木材運搬用で屋根もなく横板もなかった。雨の中13時間汽車に揺られ、朝8時頃着いた。大泊港は多くの倉庫が立ち並び、内地からの品物が荷揚げされる所だった。倉庫には空きがなく、人々で一杯だった。倉庫を仮住まいにして自炊する人もいた。 私達は役場の人からお握りや味噌汁等を貰った。私達6人は郵便局員だったので、そのうち船に乗れるだろうと思っていたが、私は風邪をひき38度の熱が出た。 そんな時に逓信局の船が出ると知らせがあり、郵便局関係の人も乗れたが、私はまだ熱があったので乗船しなかった。仲間も「私を残して行けない」と一緒に残り、3日程遅れて出港した。それで命が助かったのだと後に分った。逓信局関係の船は、魚雷でやられていた。樺太とは音信不通で2年位は生死が分らなかった。私の父も半分はあきらめていたらしい。 5年程前に詩吟《しぎん=漢詩を詠う》「氷雪の門」と出合った。樺太真岡で電話交換手9名の乙女が交換台を最後まで守り通して内地に連絡し、ソ連軍と戦いあの世に旅立った話だった。私も交換台や電報通信機を守り、局に泊まり込んでお国の為と頑張った。空襲警報は1日に何回となくあったが、本当の空襲には遭わずに終戦を迎えた。 (お話を聞いて) 樺太から引き上げ船で本土に帰国寸前の夜、幸か不幸か、発熱のため帰国を遅らせた体験は、生死の境で、先に乗船した方々は魚雷による沈没のお話で、心に残るお話で胸が熱くなりました。まさに「九死に一生を得た」辛く悲しい心の内を思い感動しました。 当時、樺太から本土北海道への海中は、魚雷が水面下にあったと同様だとのこと。真岡電話局にソ連軍が侵攻したが、最後まで内地の皆さんのためと交換台を守り抜き、あの世に旅立った9人の女性がおり、最後に「さようなら、さようなら‥・」と打電したそうです。私たちの知らない樺太でのソ連軍の侵略も詩吟「氷雪の門」を通して知りました。 武田きよ子さんの詩吟を聞き、感慨無量です。そして、この感動を次の世代へ伝えていこうではありませんか。平和への願いと共に。 (聞き手 川勝良子 昭和7《1932》年生) 「斬り込み作戦隊長戦死、始まるジャングル生活」 茅ヶ崎市 青木 功(大正12《1923》年生) (あらすじ) 昭和19年3月に教育召集で東部第8部隊に入隊。3ケ月の教育の後臨時召集になり、引き続き同隊に入隊。7月に門司港を出てマニラへ。セブを経てミンダナオ島《フィリッピン群島南東部》ザンボアンガに上陸。私は経理の経験があったので、大隊本部の経理部で帳簿記録や各隊への食糧配布勤務につき、陣地構築などの労働は免れた。 20年3月10日にはアメリカ軍が上陸してきて、13日から3日間の夜間の斬り込み作戦で大隊長が戦死した。20日には半島の西海岸を目指して退却、ジャングル生活が続いた。この間には食糧調達の為、現地の民家を襲撃して籾《もみ》を盗んだり、畑で芋を盗んだりした。フィリピンの人には申し訳ないことをした。 困ったのは塩。夜間に海岸まで行って塩を汲んできた。水と火がないと生活できないので、ねぐらを探すのは水のあるところだった。マラリヤや栄養失調で山の中で死んでいる人をたくさん見た。隊についていけない人は死んでしまった。結果的には隊の3分の2が戦死や戦病死だった。 もう少し早く終戦がわかって、投降していればこんなに犠牲者は出なかったかも。10月20日にやっと米軍のザンボアンガ収容所に投降、25日にレイテ島タクロバン収容所に移送された。ここにほとんどの兵が収容された。11月28日浦賀港に帰国。帰ってきた同僚で、フィリピンの山中に慰霊碑を作った。1年おきに参拝していたが、昭和50年からはあまり行けてない。私は3月10日の米軍上陸の日は忘れられない。絶対に戦争はダメだ。 (お話を聞いて) 青木功さんは82歳、お元気です しかし、戦後体を悪くし入院されたこともあるそうです。子育ての時期で、奥さんが大変ご苦労されたとのことです。やはり、戦地でのご苦労が原因のようです。山中でさ迷い食料調達が困難で、水牛なども食べた話もされました。アメリカ軍に拘留《こうりゅう=捕らえられる》されてからは、缶詰などが中心であっても、十分な食事が出来たこと、コーヒーまでも出されたことなど、当時の日米の物量の差について青木さんの口から感慨深く語られました。戦中・戦後に食糧難(ひもじい思い)を経験した聞き手の私としても、感慨を新にした次第です。しかし、青木さんは拘留中、朝夕ともにアメリカの国旗に敬礼しなければならなかったことを屈辱と感じたと話されました。さもありなんとの思いです。 お孫さんたちの話の中で「再び戦争はすべきではない」と強い口調で発言されたことは、さすがに立派だと感じました。部隊の3分の2が帰らぬ人となったのですから、その方々の分まで元気で長生きされることを願って青木宅を後にしました。畑の大根を二本、日本お土産として頂戴しました。有難うございました。 (聞き手 岡崎不二夫 昭和11《1936》年生) |
| 編集者 | 投稿日時: 2007-9-7 7:46 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
『肉声史』 戦争を語る (26) 「内地生活食料苦労」
茅ヶ崎市 中島 昇(大正9《1920》年生) 昭和7年に父を亡くし、母の実家がある茅ヶ崎市小出村で家族4人下宿していた。昭和15年に徴兵検査を受け、村の農業会へ勤めることになった。第2国民兵だったが、私は召集されなかった。 神奈川県農業会《=後に農業協同組合ができたので解散》小出村駐在として村の食糧増産と米の供出割り当ての確保が主な仕事だった。各自治会毎に生産組合があって、個人別に県からの割り当てを振り分ける。村には町からの縁故疎開《えんこそかい=空襲を逃れて親戚等に身をよせる》が大勢いた。1軒家を借りている人と農家の納屋を借りている人がいたが、惨めな思いをしたのは後者。 農家本家はたっぷりの食事で、自分達は芋や雑穀の配給だけだったから。近隣からの買出し者も多かった。私は駐在がはかりでチェックする手伝いをしていた。嫌だったのは、子供がせっかく着物と交換してきたうどん粉等が駐在のチェックにかかって取り上げてられてしまったこと。国民学校6年の女の子が泣いていたので、卵をこっそりあげた思い出がある。買出しの品は芋やうどん粉が多かった。野菜は自家用程度しか作っていなかった。主食が一番の時代だった。厚木航空隊に卵を納めていたこともあった。 電車を乗り継いで代金を取りに行き、途中で空襲にあった。翌日マッカーサーが来るという時に行ったら、格納庫にも滑走路にも飛行機なく、兵もいない。びっくりした。平塚の火薬廠《かやくしょう》や横浜がやられているのも見た。村は養蚕が主だったのに、食糧増産で桑畑がさつま芋畑に。昭和18年には桑畑がなくなった。終戦には呆然自失だった。 (お話を聞いて) 内地(地元小出)での戦争体験談でした。旧小出村は、堤、芹沢、行谷、遠藤、下寺尾の5つで構成され、当時610戸1800人ほどの村だったとの事。 徴兵検査で「丙」となり食料供出の検査を担当、さまざまな経験をされた由。疎開で納屋を借りた母子は、一戸建ての家を借りた母子と違い、母屋の農家の子は、食物に恵まれていたが、納屋の子供はそれを見ながら食物が悪く「ひもじい思い」をしており可哀想だった話。農家に「買出し」に着た小さな子供から、駐在が食料を取り上げたため、泣いている子が不偶と、中島さんは、卵をそっと渡してかえらせた話。食料を供出できない農家に供出要請に同行訪問したときは、障子の影から「帰れ」と言われた話。 食料にまつわる話に、戦前戦後を茅ヶ崎で食糧難を経験し、「ひもじい思い」を今でも忘れない世代として「さもありなん」という思いを強くしました。中島さんから戦後になってからも「軍隊に協力した」と悪口を浴びた話などあり「戦争はいけない」「争いはいけない」との思いを静かに語ってくれました。 (聞き手 岡崎不二夫 昭和11《1936》年生) |
| 編集者 | 投稿日時: 2007-9-8 7:04 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
『肉声史』 戦争を語る (27) 「美しくも恐ろしい艦砲射撃《かんぽーしゃげき》」
伊勢原市 永井 満慈子(大正8《1919》年生) (あらすじ) 太平洋戦争開戦時、私は22歳で水戸の小学校教員だった。昭和18年に結婚して退職。戦争が激しく、結婚といっても嫁入り道具もなくトランクの中に着物を入れて嫁いだ形だけの式だった。あるもので皆がまんした。 灯火管制《とうかかんせい=夜間敵機の来襲に備え遮光・消灯する》と空襲、敵機の音は生きた心地しなかった。これが一番怖かった。当時1歳になる前の子供を連れていたので、体を休めることもできなかった。初めての子供は風邪で亡くした。内地には薬がなく、ろくな手当てもできず死なせてしまった。教師時代の苦い思い出は、本当は随分やられているのに学校では戦果の話をしたこと。太平洋から水戸方面に向かって大砲が撃たれる艦砲射撃は怖かった。皆「かんぽちゃん」と言っていた。紫、赤、ピンクと花火のように色が変わり、すごい爆撃音だった。水戸の空爆で家が焼けて、何もなくなった。弟が引っ張る大八車に家財道具を積んで、子供をおぶって水戸のはずれに疎開した。恐ろしい思いでした。楽しみは何もなかった。 教師時代には、北満方面に行った「満蒙開拓義勇隊」《ぎゆうたい=有志人民ががみずから編成した隊》を慰問、見学して報告する役に茨城県で一人選ばれ、1ケ月間行ってきた。向こうの人達は大変な苦労だった。こちらでも食糧がなく、ふすま《小麦を粉にしたときに残る皮のくず》、芋のつる、雑草など食べた。「欲しがりません勝つまでは」だった。内地では竹やり部隊の訓練もしていた。井戸からの水汲みは重労働だった。空襲サイレンの音は命を断ち切られる音だった。今は無駄が多い。食べ物も粗末にしすぎる。 (お話を聞いて) 取材は永井さんのご自宅にお邪魔して実施させていただきました。永井さんは御年86歳(平成17年)になられたが、足腰が痛くて正座することが出来ないといわれ、藤の椅子に腰掛けての対談となりましたが、「今日は少し体調が悪い」と仰ってはおられたが、どうしてどうして、いつものように綺麗《きれい》にお化粧もされ、尚いっそうふくよかで美しいお顔をされていました。 永井さんには「戦争を語る」の中、ご婦人の立場での内地(当時は銃後といっていた)での体験を聞かせて貰いたいとお願いし、予め御相談を致しましたが、「古いことで忘れたことが多く、余り難しいことは話せませんよ」といわれながらも、結構はっきりと答えて下さいました。 永井さんは茨城県の水戸市に近いところで生まれられ、太平洋戦争開戦時には二十二歳で、すでに数年小学校の先生として、児童の教育に携わっておられたが、当時の国策を忠実に履行され少しでも立派な中国民を育てようと、子供達からは「おっかない先生」と恐れられた反面、優しい愛情をもって接しられ、今でも毎年お米を送ってきてくれる子供がいたり、クラス会への招待や東京見物もさせてくれたりで、我が子以上にいろいろ心配してくれると聞くと、「よい先生」であったに違いないと思った。 永井さんの旦那さんは、有名な三之宮比々田神社の神官を務められていたが、召集され陸軍の軍人(階級は軍曹)を帰還後、永井さんと結婚された。戦争は次第に激しくなり、米国の艦隊による艦砲射撃の轟音には恐れおののき、艦載機による射撃攻撃で、大勢の市民が殺された。 そうした恐しい思いの毎日の生活で、やはり食べ物が無くてひもじい思いをしたことが辛かったが、唯一の楽しみは、隣近所同士で「お芋がふけたよ」との呼び掛けやお喋りすることだったという。 戦争が終わったときは、さすがにほっとして、明るい蛍光の光のなんと眩《まぶ》しかったことか。 戦争を知らない人々へ強く訴えたいことは何でも豊富にある現在、贅沢三昧《ぜいたくざんまい》の生活を反省し「もったいない」(質素)という気持ちが大切であるといわれた。 (聞き手 川口博 昭和2《1927》年生) |
| 編集者 | 投稿日時: 2007-9-9 8:08 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
『肉声史』 戦争を語る (28) 「敗戦、点灯、平和を感じたひと時」
伊勢原市 倉前 敏子(大正10《1921》年生) (あらすじ) 昭和13年佐賀県看護養成学校入学、15年国家試験合格。市内の病院に勤務の後、17年日赤陸軍病院へ。昭和20年以降は陸軍病院に隣接する48連隊めがけてB29《アメリカの長距離爆撃機》の爆撃が多くなった。私達看護婦は警戒警報で出動命令となり、病院に赴くことになっていたので、自分も雨戸が閉ざされた真っ暗な街中を病院へと急いだ。48連隊が爆撃を受ける度にどんどん負傷兵が病院に運ばれてくる。一手術室に黒いカーテンを引き、ローソクの明かりで手術が行われた。 たくさんの方が亡くなった。ある時赤痢が流行って、30名程の患者が1日に30、40回の下痢をする。点滴といっても今のように細い針ではなく、布団針のような太い針でリンゲルを打つ。それでも皆助かった。ダメだったのは結核患者。栄養失調と特効薬がなかったから。戦後、赤痢から生還した兵士に偶然会ってお礼を言われた時は、看護婦になってよかったと思った。 8月15日の敗戦で町々に明かりが灯り、一度に明るくなった。平和の良さをしみじみと感じた。8月7日の原爆後は長崎から被爆患者が佐賀へ運ばれてきた。耳たぶや手の甲など、被爆したところにウジ虫が湧いていた。それを一つ一つピンセットで取った。戦後は食糧難の為、隣の練兵所で農作業に従事し、200人余りの患者の食糧も補った。昭和20年秋に陸軍病院は国立病院となり、私は22年に結婚で退職した。私の青春時代は生きていくので精一杯だった。今の若者は平和な時代に感謝してほしい。 (お話を聞いて) 戦時下女性体験、看護婦を目指した動機 幼児虚弱、近隣医院での看護婦の献身さに感動、女性の職業、教師、看護婦看護学校入学 昭和15年資格取得佐賀市内2病院、勤務3年 昭和19年日本赤十字病院正看採用佐賀陸軍病院勤務、傷病兵の看護、昭和20年6月~7月隣接地48連隊がB29爆撃を受ける。警報発令にて、軍医看護婦被爆者救護。陸軍も空爆波及し援護活動従事。 特に8月7日の長崎市原爆被災は想像を絶する。長崎より死傷者が搬送され、身体各部損傷箇所にウジ虫が発生、ピンセットで除去する無残な状況は想像外。搬送された方々以外の重傷者は現地でどのような治療が施されたのか、原爆の縮図を語られました。 食料自給自足のため隣接敷地に下肥《しもごえ=人の糞尿を肥料にしたもの》を運び農作業にも従事。 青春時代はモンペのみ。昭和22年国立病院に改編を機に結婚、退職された由でした。 「銃後の守り」「欲しがりませんは勝つまでは」の言葉に惑わされ献身的な努力は、終戦で一切無に帰しました。戦争の悲惨さは言語に尽せません、平和こそ何物にも変えがたい貴重な宝物であることが実感されました。 (聞き手 吉原信司 大正13《1924》年生) |
| 編集者 | 投稿日時: 2007-9-10 7:23 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
『肉声史』 戦争を語る (29) 「聖戦などなし 失うものあまりに多し」
伊勢原市 小林 繁雄(大正10《1921》年生) (あらすじ) 昭和18年3月に入隊が決まった。当時、同じ職場に恋人がいたが自分は戦争に行く身で、いつまでも思いを残させてはいけないと抱きしめたい気持ちを堪えた。3月10日第3師団の通信隊に入隊。 内務班で衣服が支給された。軍服2着、下着2枚、雨合羽、外套、編み上げ革靴2足、靴下、軍帽。厳しい訓練は覚悟していたが、古年兵の意地悪には苦労した。演習からくたくたになって帰ると、衣服がぐちゃぐちゃになり、枕に落書きされていた。この落書きが洗ってもなかなか落ちず、落ちないままだと枕くわえて犬の真似をさせられた。ビンタは日常茶飯事《にちじょうさはんじ=いつものこと》だが、教育係の上等兵に目をつけられたのが大変だった。電気の試験で上等兵が答えられない問題を私が解いたら、呼び出されて気絶するまで殴られた。除隊するまでそういう扱いだった。 外地で無人の部落に宿営することになったが、夜に手相弾が投げ込まれて戦死者が出た。後に犯人の中国人が捕まった。初年兵の肝試しだと処刑係に私が指名された。銃剣で左胸を突いたがとどめをさせず、人目を盗んで血だらけの捕虜を納屋《なや》へ運んだ。しばらくしたらいなくなっていた。また、みぞれの晩に機材を運ぶための馬の番をさせられた。夜行軍だったのでつい寝入ってしまい、ふと目覚めると2頭のうちの1頭がいない。慌てて捜すと、深田でもがいていた。私も飛び込んだが、馬と一緒に沈んでいく。 その時、小さい頃のおじさんの手綱さばきを思い出し、何とか助かった。その後、マラリアで入院もした。戦争の後に残るのは廃墟《はいきょ》と苦しい生活だけ。私達は聖戦だと信じていたが、かけがえのないものをたくさん失った。 (お話を聞いて) 語り手の小林さんとは、同じ老人クラブでご一緒している仲間で、外地での戦争体験者と私が推薦して今回、色々と貴重な体験を聞かせて貰いましたが、年齢は84歳とは思えぬ元気さと記憶力の良さに終始感心させられながら聞かせて頂きました。 限られた時間(60分)でしたので、聞き漏らしたことも有ったようですが、その中で特に私が感銘を受けた点について書いてみます。小林さんは旧制中学(現在の高校)の電気化を卒業されたキャリアを生かされ、入隊前までは東京M電機メーカーに勤められ、軍隊でも通信兵に編入され、ほかの兵科同様、厳しい新兵教育を受けられたが、日本陸軍軍人として、立派にお国のためにつくそうと日夜頑張られ、常に「積極的に行動」されたことが、皮肉にも上官(0上等兵)の反感をかい、以後執拗《しつよう》なまでに酷い仕打を受ける破目になりました。「積極的な行動」を詳しく記述できませんが、小林さんが上官に正解できなかった電気の計算問題を簡単に解いたことで「恥をかかされた」と上官の憤慨《ふんがい》を買い、何回も嫌がらせを受けたということです。霧の降る寒い夜誰もが嫌がる二頭の馬当番を指名され、中一頭が姿を消したときに驚き、普通新兵では任命されない歩哨《ほしょう=警戒・監視の任にあたる》に立たされたときの責任の重大さに身の縮む思いがしたことなどがその実例です。 そうした試練に何度か「死」を覚悟したが、その度毎に瞼に「母」の顔が浮かんできてそれを思いと止めさせられましたが、生憎と「マラリア」にかかり、足も上がらぬ重症になるまで行軍を続けたが、流石に耐えられなくなり入院生活を送り、満足の行く御奉公が出来ず敗戦を迎えたことが、今でも残念に思っている。最後に、戦争を知らない人達に対するメッセージはと聞くと、再びあの忌まわしい戦争の無い平和な日本であって欲しいと誰もが叫ぶことは勿論、何度かの自殺を思いとどまった経験から「命」の大切さを強調されていた。 (聞き手 川口博 昭和2《1927》年生) |
| 編集者 | 投稿日時: 2007-9-11 7:27 |
 登録日: 2004-2-3 居住地: メロウ倶楽部 投稿: 4289 |
『肉声史』 戦争を語る (30) 「時代に翻弄《ほんろう》させられた青春」
伊勢原市 折井 武(大正14《1925》年生) (あらすじ) 戦争が始まったと聞いたときは怖くて体が震えた。考えれば時代と制度に翻弄されたと思う。徴用《ちょうよう=注》令で海軍航空技術廠へ。寮生活で朝早くから夜遅くまで射撃用兵器部品を作る。 海兵団のカッター漕ぎは競争で負けると制裁があるので戦々恐々で負ければ、精神棒などで尻をたたかれた。また、東京の大空襲の悲惨さは、目に余るものがあった。戦時特例法等々法律は、自分たちの自由を奪っていくことを身をもって知った。 (お話を聞いて) 折井さんとは、伊勢原市老人クラブ連合会の「老連便り」(年4回発行A4版6~12ページ)の編集を担当している仲間ですが、年齢既に80歳を越えた今、ますます元気いっぱいで、ボランティア活動は勿論のこと、私は大の苦手の電子機器(パソコン、インターネット)の大ベテランで、今回の「戦争を語る」の内地での体験報告もあらかじめ作成してくれたので大いに助かりました。その資料はA4で10ページもあり、限られた時間(60分)内には、そのすべてをお聞きすることが出来ず、はなはだ残念でした。しかしせっかくの貴重な体験を無にするのが惜しくて多少早口になって聞きづらといことがあったら お許しを頂きたいと思います。 折井さんは、開戦時16歳でしたが、充分戦争に対する覚悟を決められ、既に施行されていた国家総動員法による各種の統制とさらに施行された国民徴用令により、海軍航空技術廠に就職されたが、人手不足により、毎日5時間残業の厳しい日課に耐えられました。 一方、家業(鍍金業)は、ニッケル、クロム、銅等の材料が入手困難となり廃業し、父は軍需工場に就職、中国に出兵の兄が戦死され、折井さんも学校を繰り上げ卒業し、海軍航空技術廠の射撃部に就職し、試作工場で部品の試作をした後、海軍工員養成所で勉強もしました。その後、横須賀海兵団に入団してからの新兵教育は厳しいもので、「精神棒」で思い切りお尻を叩かれたり「お神輿」「ぶら下がり罰」「鴬の谷渡り」「蜂の子罰」「食事抜き」(詳細省略)等の刑罰や手旗信号の訓練も出来なければ食事ができませんでした。その後、本当の海軍軍人になる召集令状を貰ったが、軍艦にも乗らず、鉄砲も撃ったことはありませんでしたが、空襲は何度も経験し、電車が不通となり、東京から上野間や、東京から南千住間は積雪や、空襲による大火災の真っ暗な夜道を歩かされましたが、何といっても3月10日の東京大空襲はひどかったし、実際に体験した焼夷弾による空襲時の恐ろしかったことは、今でも鮮明に覚えておられます。横須賀海兵団での軍人らしい体験は、辻堂の海岸での演習での「蛸壷《たこつぼ》作戦」(内容省略)は正に人命軽視の特攻作戦でありました。そうして迎えた8月15日の終戦の放送を聞き「これで生きられる」との思い出で一杯でした。 最後に戦争を知らない人たちへのメッセージは、悲しい戦争を繰り返さないよう主権在民の平和国家を続けて下さいとのことです。 (聞き手 川口 博 昭和2《1927》年生) 注 徴用=国家が国民を強制的に動員し一定の業務につかせる |
| « 1 2 (3) 4 5 6 ... 8 » | |
| スレッド表示 | 新しいものから | 前のトピック | 次のトピック | トップ |
| 投稿するにはまず登録を | |